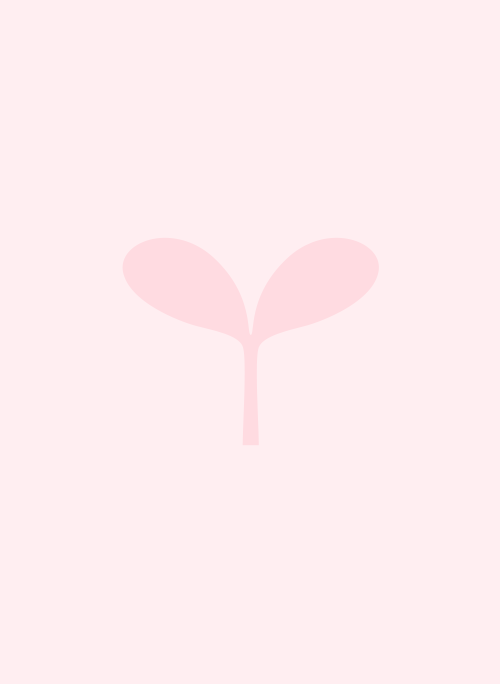「行こう、紅玉。」
ガチガチと歯を鳴らしだしたうさぎを、黒曜が労るように抱き上げた。
「嫌じゃ… ゆけぬ…
景時が…」
「わかっている。」
苦笑いを浮かべた黒曜が、揺れる赤い瞳を覗き込む。
「だが、おまえには時間が必要だ。
そうだろう?」
黒曜の言葉を聞いたうさぎは、もう一度部屋の様子に目をやり、唇を噛んで俯いた。
「う…さぎ…」
低い呻き声がする。
誰の声かはすぐにわかる。
だがうさぎは彼を見ることが出来ず、黒曜の胸に顔を埋めた。
「大…丈夫だから…
ごめ…ん…ね。
うさ… 大好」
「景時!」
黒曜の胸に縋りついたまま、うさぎが悲鳴を上げて遮った。
沈黙の中、ようやく景時がうさぎに向かって手を伸ばす。
秋時も片手で頭を撫でながら、上半身を起こす。
二人の視線を痛いほど感じながらも、うさぎは顔を背けたまま呟いた。
「景時、秋時…
本当に、すまなかった。
必ず戻るから…
待っていてくれ。」