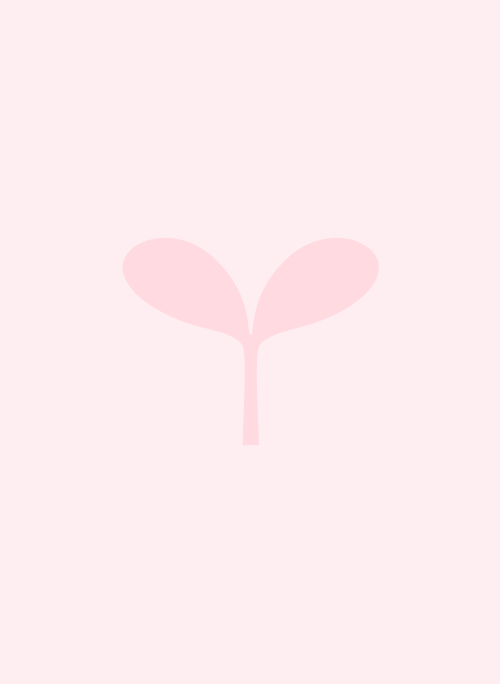約束の時間だ。
そっと、殺し屋を部屋の中に招き入れる。
あの人はまだベッドの中だ。
殺し屋はちらっと私を見たが、ニコリともせずに真っ直ぐにベッドに向かった。
有無を言わさず、素っ裸の彼の口をガムテープで塞ぎ、気がつくと彼は後ろ手に縛り上げられていた。
ただただ怯えていただけのあの人も、状況がわかってくると憎しみに満ちた表情で私をにらみ付けた。
「違うの。これはショーなのよ」
彼には決して理解できないだろう。
しかし、それは殺し屋とて同じ事。
殺し屋にショーをやるつもりなど微塵もなかった。
振り向くと、殺人ショーを前に感慨にふける私の胸になんの躊躇もなくナイフを突き刺した。
胸が燃えるように熱い。
こ、声も出ない。
どうして?
こんな簡単に殺さないで。
まだ、恨みのひとつも言ってない。
(あの人は、あの人は・・・)
私の最後を見届けるはずのあの人の視線は、あろうことか、あの人に迫るナイフに注がれていた。
(その人は殺さなくていいの。だっ、だめ。その人は殺さないで)
最後の力を振り絞って、あの人を覆い隠すように倒れると今度は背中に熱いものがねじこまれた。
そして、髪の毛をつかまれ、皮を剥がすようにあの人から引き離された。
「どけ、目撃者は始末する」
(お願い、この人は・・・)
しかし、それは言葉にならなかった。
そして、意識はどんどん薄れていった。
おわり