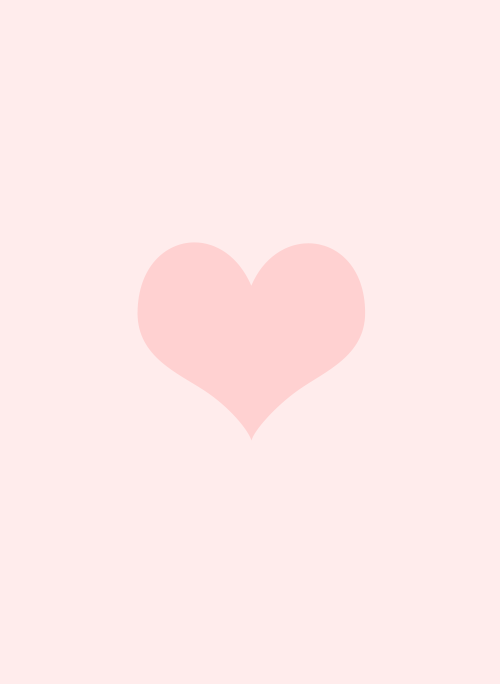「いいよ、入って来て」
部屋の入り口で茫然と立ち竦むぼくに、満央は入室の許可を与えた。
ぼくは満央の部屋にいた時と同じように、水色のベッドの端に遠慮がちに腰を掛けると、ギギギッと小さく軋む音がした。
「満央のお姉ちゃんって、あんまり部屋を飾ったりしなかったの?」
殺風景な部屋の理由を、極力差し障りのないような遠回しな言い方で聞いた。
満央はぼくの質問に対して、一瞬何かを考えるように間を置いてから、「ううん」と否定の返事をした。
「少しだけ私が片付けたの」
「そうなんだ‥‥‥」
ベッドと机と本棚、そしてタペストリー。
それ以外何も無い部屋で、少しだけ何を片付けたというのだろう。
けれど深く追求する事でもないと思い、敢えてそれ以上は何も聞かなかった。
それにこの部屋の雰囲気が、まるであの《ためいき色》みたいに感じるだなんて、到底口には出せなかった。
むしろ、ぼくらが以前から話していた話題として、満央自身がその事に気付いていないのだろうかと疑問に思う。
この部屋が《ためいき色》に染まっているということを。
そんなことを考えながら、もう一度部屋の中を見回すと、タペストリーの中の月が異様に大きく、そしてリアルの浮かび上がって見えた。
「ねえ、満央のお姉ちゃんって、月が好きだったの?」
ぼくは、タペストリーを指差しながら満央に訊いた。