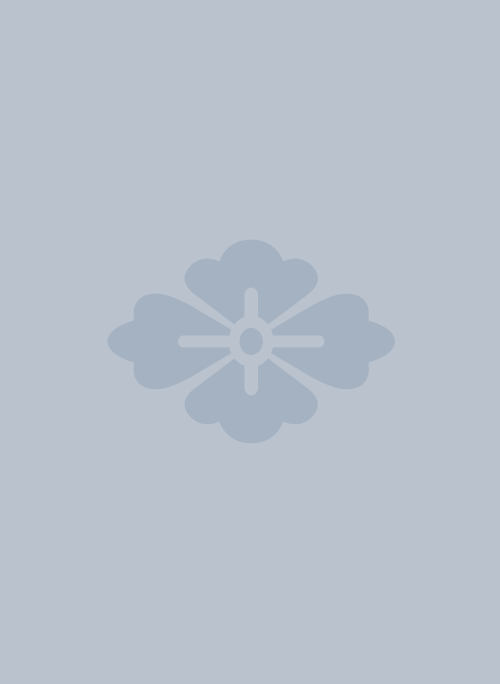四月二十二日、早朝。
永福寺下の屋敷を出陣した二階堂勢百五十騎は、途中貞時の命で加勢を命ぜられた武蔵七郎の五十騎を合わせ二百騎で滑川を車大路の方へ駈け、和賀江から入った経師ヶ谷の頼綱の屋敷を、たちまち包囲した。
そこで行藤は不思議な行動に出た。
矢文を放ったのである。
「降伏せよ」
といった内容である。
すると。
文が返ってきた。
「降伏はせぬが、交渉はする」
といった話であった。
幾度か矢文のやりとりを経て、屋敷の門前で頼綱は、行藤と交渉をする旨が決まった。
──変わった戦だな。
打ち物を取っての立ち回りが戦だと思い込んでいる武士たちは、この奇妙な戦いを物珍しげに眺めている。
頼綱の屋敷の門前には幕が立て回され、そこには傷で苦しげに床几に腰をかけた行藤と、直垂姿の頼綱という、なんとも変わった対談の場が用意された。
「まず頼綱どの、嫌疑のことについて申し開きがあれば行藤が承る」
「取り立ててござらぬ」
「降伏はいたさぬとのことだが、多勢に無勢のこの戦で勝てるとお思いか」
「思っておらぬ」
「では頼綱どのは、ここへ死にに参ったのか」
「いかにも」
「それだけのお覚悟がおありならば、許しを乞うて再び幕府に戻るつもりはござらぬか」
「ござらぬ」
「今一度たずねる。頼綱どのは、命を捨てるおつもりか」
「然り」
そういうと、頼綱は打刀をやおら首にあてがい、
「政所判官どのに頼みがある。わが首を、執権御所にお届けいただきたい」
「それは」
北条時輔のときと似た事態ではないか。
「かつてそれがしは、北条時輔どのを同じように自害に追いやった。その因果がきっと、めぐって参ったのであろう」
首を北条家の者に渡すのであれば刀の折れるまで戦うつもりだが、といってから、
「なれど、政所判官どのが参られた」
そなたとは戦いたくはないのだ、と頼綱はいった。
「何ゆえ、かようなときに」
「そなたもわしも、ともに鎌倉を、この島国をよき国としたい志は同じ。されど」
生まれが違うと考えが違う、と続け、
「わしには朝廷という強い後ろ楯も、判官という輝かしき官位もなかった。後ろ楯も官位もなくては力などつけられるはずもない」
行藤は黙った。
「そなたを憎いと思うたこともあったが、それ以上にわしは北条が、鎌倉が、この世が憎かった」
それを改めるにはこれしかなかったのだ、と頼綱はいい、
「だが事が露見した以上、申し開きは見苦しい」
ゆえにこういたす、というと首にあてがった打刀を、
「…!」
というと同時に滑らせ、見事に自刃して果てた。
取り巻いていた武者たちが首をかこうとした。
「…ならぬ!」
介錯はこの行藤がいたす、というと不自由そうに右腕一本で太刀を操って首級をあげた。
屋敷は、静まっている。
改めさせると百人近い自害した武士たちがあった。
「丁重に荼毘にふせよ」
行藤は頼綱の首級を小袖にくるむと、静かに引き上げを命じた。
頼綱の首級を携えた行藤は、輿で執権御所までたどり着いた。
いろいろな意味で力を使い果たした行藤に、馬に乗る気力まで残されてる風には思われなかったであろう。
貞時の前に首級を差し出した行藤は、
「見事な武士らしいご最期にございました」
といった。
晒し首にしてはどうか、と赤橋久時がいうと、
「いやしくも頼綱どのは侍所別当、それを火付や盗賊も同様に首をさらすのは、およそ天下に恥をさらすようなものにございます」
赤橋どのがみずから、恥をおさらしになられたいのであれば話は別にございますが…というと晒し首の案件はいつしか沙汰やみとなった。
月が改まった。
連署として行藤は、まだ実は目立った仕事を果たしていない。
というより。
むしろ仕事をさせてもらえなかったようで、ほとんどが追認という形であとから加判してあるに過ぎない。
その間にも時は進んでいる。
新田の開発は、山や地面を領有する荘園の園主からの反発が凄まじいこととなっていた。
とりわけ比叡山や興福寺などの寺院は、頼綱の年貢米の徴収の件以来幕府に反旗を翻すことがあって、神輿動座をおこない六波羅へ乗り込むという一幕すらあったのである。
行藤は、無力を痛感した。
「みな、おのれが可愛いばかりにああなる」
だが。
二度の異国合戦以来、財政は逼迫し始めている。
交易も宋がなくなり、高麗が元の配下にある以上、期待は望めない。
そこで。
「御内人を減らされてはどうか」
と提言を出した。
これは貞時が許さず、
「もう打つ手だてがございませぬ」
行藤は連署の辞任を願い出た。
事実。
もう手がないのである。
が、
「ここで二階堂がいなくなれば、誰も幕府を支えるものがおらなくなる」
貞時は辞職すら許さない。
「幕府を壊すつもりで変えてくれ」
とはいうのだが、変えられる場は残っていない。
(どうしろというのだ)
そのようにして。
無為に連署の座に行藤はとどまらざるを得なかったのであった。
ところで。
一度、行藤は名前が歴史上に出てくる。
永仁五年三月に発布された徳政令のとき、加判を拒否した咎で、連署でありながら謹慎を命ぜられたのである。
このとき行藤は強硬に反対を表明しており、
「やみくもに借金を棒引きにしても、それはいわば目先の金子の話で、国家百年の大計には非ず」
と推進派であった長崎高綱(光綱の子)を満座のなかで非難し、何の益にもならないことを滔々といい明かした。
これにより。
面目を潰された長崎高綱の讒訴によって、翌年に越訴奉行に左遷を命ぜられている。
このとき、長崎高綱からの罵詈雑言を次々よどみなく道理を説いて切り返し、誰が見ても行藤の勝ちにしか見えないほど完膚なきまでに論破してみせたが、
「あれは問答としては政所判官どのの勝ちである」
誰が裁定してもそうなるであろう、といってから大仏宣時は続けた。
「だが世の中、正論ほど通らぬものだ」
根拠のないものほど流布しやすい、と珍しく慰めにも似たことをいった。
さて。
越訴奉行となった行藤は司法に通じており、徳政令と選銭によって混乱していた経済に関する訴訟を数多く処理し、正安元年には引付五番頭人としていわば法務のプロフェッショナルとして幕府を支えるに至る。
こうして裁判官として世を終えようとしていた正安二年、行藤は出家した。
「道暁」
という名を新長谷寺から授かった行藤は、嫡男の貞藤を六波羅から鎌倉へ呼び戻すと、みずからは京へ入れ替わりに向かった。
また朝廷が騒がしくなったのである。
体調を心配したようで、藤子は留まるように説得を試みたが、
「駆り出されては、動かぬわけにも行くまい」
そういうと振り切るように、東海道を西へ向かった。
永福寺下の屋敷を出陣した二階堂勢百五十騎は、途中貞時の命で加勢を命ぜられた武蔵七郎の五十騎を合わせ二百騎で滑川を車大路の方へ駈け、和賀江から入った経師ヶ谷の頼綱の屋敷を、たちまち包囲した。
そこで行藤は不思議な行動に出た。
矢文を放ったのである。
「降伏せよ」
といった内容である。
すると。
文が返ってきた。
「降伏はせぬが、交渉はする」
といった話であった。
幾度か矢文のやりとりを経て、屋敷の門前で頼綱は、行藤と交渉をする旨が決まった。
──変わった戦だな。
打ち物を取っての立ち回りが戦だと思い込んでいる武士たちは、この奇妙な戦いを物珍しげに眺めている。
頼綱の屋敷の門前には幕が立て回され、そこには傷で苦しげに床几に腰をかけた行藤と、直垂姿の頼綱という、なんとも変わった対談の場が用意された。
「まず頼綱どの、嫌疑のことについて申し開きがあれば行藤が承る」
「取り立ててござらぬ」
「降伏はいたさぬとのことだが、多勢に無勢のこの戦で勝てるとお思いか」
「思っておらぬ」
「では頼綱どのは、ここへ死にに参ったのか」
「いかにも」
「それだけのお覚悟がおありならば、許しを乞うて再び幕府に戻るつもりはござらぬか」
「ござらぬ」
「今一度たずねる。頼綱どのは、命を捨てるおつもりか」
「然り」
そういうと、頼綱は打刀をやおら首にあてがい、
「政所判官どのに頼みがある。わが首を、執権御所にお届けいただきたい」
「それは」
北条時輔のときと似た事態ではないか。
「かつてそれがしは、北条時輔どのを同じように自害に追いやった。その因果がきっと、めぐって参ったのであろう」
首を北条家の者に渡すのであれば刀の折れるまで戦うつもりだが、といってから、
「なれど、政所判官どのが参られた」
そなたとは戦いたくはないのだ、と頼綱はいった。
「何ゆえ、かようなときに」
「そなたもわしも、ともに鎌倉を、この島国をよき国としたい志は同じ。されど」
生まれが違うと考えが違う、と続け、
「わしには朝廷という強い後ろ楯も、判官という輝かしき官位もなかった。後ろ楯も官位もなくては力などつけられるはずもない」
行藤は黙った。
「そなたを憎いと思うたこともあったが、それ以上にわしは北条が、鎌倉が、この世が憎かった」
それを改めるにはこれしかなかったのだ、と頼綱はいい、
「だが事が露見した以上、申し開きは見苦しい」
ゆえにこういたす、というと首にあてがった打刀を、
「…!」
というと同時に滑らせ、見事に自刃して果てた。
取り巻いていた武者たちが首をかこうとした。
「…ならぬ!」
介錯はこの行藤がいたす、というと不自由そうに右腕一本で太刀を操って首級をあげた。
屋敷は、静まっている。
改めさせると百人近い自害した武士たちがあった。
「丁重に荼毘にふせよ」
行藤は頼綱の首級を小袖にくるむと、静かに引き上げを命じた。
頼綱の首級を携えた行藤は、輿で執権御所までたどり着いた。
いろいろな意味で力を使い果たした行藤に、馬に乗る気力まで残されてる風には思われなかったであろう。
貞時の前に首級を差し出した行藤は、
「見事な武士らしいご最期にございました」
といった。
晒し首にしてはどうか、と赤橋久時がいうと、
「いやしくも頼綱どのは侍所別当、それを火付や盗賊も同様に首をさらすのは、およそ天下に恥をさらすようなものにございます」
赤橋どのがみずから、恥をおさらしになられたいのであれば話は別にございますが…というと晒し首の案件はいつしか沙汰やみとなった。
月が改まった。
連署として行藤は、まだ実は目立った仕事を果たしていない。
というより。
むしろ仕事をさせてもらえなかったようで、ほとんどが追認という形であとから加判してあるに過ぎない。
その間にも時は進んでいる。
新田の開発は、山や地面を領有する荘園の園主からの反発が凄まじいこととなっていた。
とりわけ比叡山や興福寺などの寺院は、頼綱の年貢米の徴収の件以来幕府に反旗を翻すことがあって、神輿動座をおこない六波羅へ乗り込むという一幕すらあったのである。
行藤は、無力を痛感した。
「みな、おのれが可愛いばかりにああなる」
だが。
二度の異国合戦以来、財政は逼迫し始めている。
交易も宋がなくなり、高麗が元の配下にある以上、期待は望めない。
そこで。
「御内人を減らされてはどうか」
と提言を出した。
これは貞時が許さず、
「もう打つ手だてがございませぬ」
行藤は連署の辞任を願い出た。
事実。
もう手がないのである。
が、
「ここで二階堂がいなくなれば、誰も幕府を支えるものがおらなくなる」
貞時は辞職すら許さない。
「幕府を壊すつもりで変えてくれ」
とはいうのだが、変えられる場は残っていない。
(どうしろというのだ)
そのようにして。
無為に連署の座に行藤はとどまらざるを得なかったのであった。
ところで。
一度、行藤は名前が歴史上に出てくる。
永仁五年三月に発布された徳政令のとき、加判を拒否した咎で、連署でありながら謹慎を命ぜられたのである。
このとき行藤は強硬に反対を表明しており、
「やみくもに借金を棒引きにしても、それはいわば目先の金子の話で、国家百年の大計には非ず」
と推進派であった長崎高綱(光綱の子)を満座のなかで非難し、何の益にもならないことを滔々といい明かした。
これにより。
面目を潰された長崎高綱の讒訴によって、翌年に越訴奉行に左遷を命ぜられている。
このとき、長崎高綱からの罵詈雑言を次々よどみなく道理を説いて切り返し、誰が見ても行藤の勝ちにしか見えないほど完膚なきまでに論破してみせたが、
「あれは問答としては政所判官どのの勝ちである」
誰が裁定してもそうなるであろう、といってから大仏宣時は続けた。
「だが世の中、正論ほど通らぬものだ」
根拠のないものほど流布しやすい、と珍しく慰めにも似たことをいった。
さて。
越訴奉行となった行藤は司法に通じており、徳政令と選銭によって混乱していた経済に関する訴訟を数多く処理し、正安元年には引付五番頭人としていわば法務のプロフェッショナルとして幕府を支えるに至る。
こうして裁判官として世を終えようとしていた正安二年、行藤は出家した。
「道暁」
という名を新長谷寺から授かった行藤は、嫡男の貞藤を六波羅から鎌倉へ呼び戻すと、みずからは京へ入れ替わりに向かった。
また朝廷が騒がしくなったのである。
体調を心配したようで、藤子は留まるように説得を試みたが、
「駆り出されては、動かぬわけにも行くまい」
そういうと振り切るように、東海道を西へ向かった。