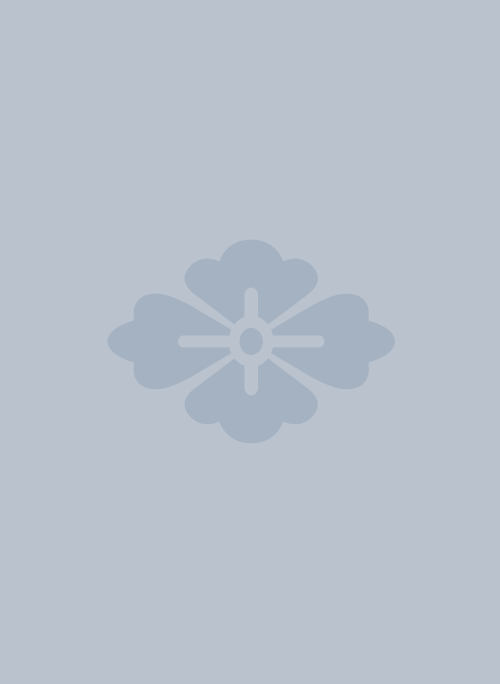その日が来た。
冷泉家の使者から指定されたのは清水寺である。
「そのような寺は、どこにあるのだ?」
と行藤は使者が帰ったあと、そばの家来にきいたほどである。
落ち着かなかったのは行藤だけではない。
一条家経もやってくるなり、
「今様とはまた考えよったな」
と驚いた。
行藤が着ていたのは浅黄と紫の、左右で色が違う片身違いの直垂である。
ところで。
清水寺が二十一世紀の我々が知る姿になったのははるかな後代だが、寺そのものは往時からある。
道中、行藤が坂の中ほどで振り返ると、見事なまでに京じゅうが見渡せた。
「このようなところがあったとは」
思えば鎌倉は町が狭い。
(町が狭いと人の心も狭くなるのだろうか)
行藤の脳裏にふとよぎった。
本堂への石段を昇った先に、人だかりがある。
「行藤、桜や」
家経が指差した先には、満開に咲き誇る桜の巨樹があった。
「もう咲いたのやな」
鎌倉の桜は、花こそ大きめだが白っぽい。
そこへゆくと、京の桜は花こそ小ぶりだが淡い紅色で、それが抜けるような空によく映える。
「…この美しさは鎌倉にはないものだな」
本堂から少し奥まった御所風の建物に、極楽寺時茂がいた。
「これは行藤どの」
隣は、黒い直垂の目の鋭い武士である。
「時輔どの。こなたは二階堂判官行藤どのじゃ」
行藤は一礼した。
「これは時輔どの、鎌倉の御座所以来でございます」
行藤が頭を下げると、
「行藤どの、ご無沙汰をしておりまする」
「時輔どのには、きけばお子がおわすとか」
「元服して今は時朝となりました」
「左様であられたか」
それより、と時輔はいう。
「さすが二階堂どの。京が長いと、装束もどことなく京風でございますな」
「いずれ時輔どのとて京の気風に染まりましょう」
それに、と行藤は続ける。
「播磨には小山長村どのもおわす。ときには水入らずで昔語りなどもできましょう」
ついでながら、小山長村は時輔の舅である。
宴ははじまった。
境内はやわらかい陽射しが降り注ぎ、時折どこからか田楽の笛のような調べが流れてくる。
が。
行藤はそもそも宴といった賑々しいものは苦手な性質で、出来れば避けたいのが本音である。
(いったい何の因果で)
このようなことになったか…と、行藤には何とも怨めしい思いがあった。
一条家経は気づけばどこかに去ってしまっている。
はぐれたらしい。
ほどなく北条時輔に御座所まで案内され、
「それがしはこれにて」
と離れてしまうと、
(何とも心許ないものよ)
と、行藤はかすかに不安になった。
「こちらにございます」
従者に桟敷に招かれると、奥には機嫌よくきこしめした様子の為家卿が女に酒を注がせている。
「よう参ったのう行藤、こなたへ来りゃれ」
と、杯が出された。
「聞けば武士の習わしでは一度は引き合わせると申すゆえ」
かの者を呼んである、といった。
行藤はすっかり忘れていたが、
「久我の右大将どのの姫ぎみの藤子どのじゃ」
と、為家卿は呼ばわった。
平伏した瞬間、向こうから衣擦れの音がする。
座ったらしい。
「二階堂判官行有が嫡男、藤原行藤にございます」
公卿の世界で二階堂という名字は、どうも通用しないものらしい。
まだ行藤は頭を下げている。
為家卿がすかさず、
「手を上げられよ」
おもてを上げると、例の男装の小姓が、袿姿で座っているのである。
左の頬にえくぼがある。
間違いない。
一瞬、目が泳いだ。
「いかがした行藤。気色がすぐれぬようやが」
為家卿がいぶかるのも無理はない。
「いえ。…斯様にやんごとなき姫様に拝謁をたまわることが、なにぶん初めてのことにございますれば」
「そうか。それは是非もあるまい」
為家卿というこの老公卿は人がよいのか、若い行藤と藤子のために酒肴をととのえていた。
そこへ、
「行藤っ、探したぞ」
と、一条家経の甲高い声がした。
「ここにおったか」
「これは一条の若様。随分ご酒を過ごされたご様子で」
「…これはこれは為家どの、ご無礼つかまつりました」
為家卿には一条家経があらわれた、というだけで良かった。
「実は二階堂の行藤どのと久我の藤子どのとの輿入れの話をしておっての」
「…それは何ともめでたい限りにあられますなあ」
若くても公卿で最高の五摂関家の一員である一条家経をこの場の証人にすることが、どうやら為家卿の真意であったらしい。
(家経も軽々しいのう)
行藤は飲んでる酒の味が分からなくなった。
為家卿にすれば、幕府でも重臣格の二階堂家と堂上人の久我家を結びつけておくことで、鎌倉と京に小さな楔を打ち込むことが深意にあったようで、
「二階堂家も久我家も共に名家ゆえ、この縁組みにはどなたもよもや異議を挟みますまい」
と、一条家経に同意を促した。
家経は頷いた。
行藤は酒の味が混乱でますます分からなくなった。
件の酒宴のあと、行藤と藤子の縁組みが冷泉為家卿の計らいで披露され、晴れて婚約者となった。
そこまではよい。
文永元年当時、すでに京と鎌倉の間にはただならぬ空気が渦巻き始めていた。
きっかけは、一条家経の従兄弟にあたる五代将軍・藤原頼嗣が帰洛、代わりに宗尊親王が将軍として下向した件にはじまる。
宗尊親王。
為家卿が仕える後嵯峨上皇の第一皇子で、
──母の生家が卑賤の出である。
という理由で、皇位を弟に譲ることになり、半分厄介払いの体で鎌倉へ下ったという事情がまずある。
鎌倉に下ると宗尊親王は、いわば飾り物に止まらない言動が目立つようになった。
いわゆる御所派というべき派閥を形成しはじめたのである。
行藤にとって困ったのは、嫁いだばかりの妹の熙子の婚家でもある名越家に、御所派が接触しはじめたことであった。
歳上の義弟にあたる名越時章は、庭に牡丹を植えるのが好きで、争いを好まない性分であった。
名越家は数ある北条一族の中でも、極楽寺家と並んで連署や評定衆を出してきた家でもある。
が。
すぐ下の弟の教時というのが問題で、以前時章の兄が藤原頼嗣の失脚の折、執権の北条時頼の粛清に遭って自害に追い込まれた過去があり、
「時頼の血筋だけは許さぬ」
という恨みを抱いてたのもあって、隙あらばと転覆を狙うふしがあったらしいのであった。
いわば名越家の小さなほころびを糸口に、宗尊親王が将軍としての権威の回復をはかりはじめたのである。
一方。
執権は極楽寺時茂の兄・長時から、一族の重鎮である北条政村へとすでに代替わりしている。
行藤の父・行有と並ぶ和歌の詠み手であり、地方の行政に強い人物でもある。
その北条政村が手をつけた異動は、宗尊親王の近侍にいた二階堂行有を、新しく設置された引付衆という役職に据えるといういわゆる引き抜き人事であった。
行藤の縁談はいわば、そうした朝廷と幕府の力の綱引きのはざまにある話でもある。
が。
藤子も行藤もそうした込み入った懸案は知らなかったらしく、単に、
「見も知らぬ相手と夫婦になるよりは良い」
という程度の認識でしかない。
その辺りの行藤の楽観的な見方を危惧していたのは、北条時輔である。
「判官どのももう少し気をつけられてはどうか」
と、時輔に忠告されるのはしばしばで、行藤が露骨に嫌な顔をすると、
「それでは二階堂家は滅びますぞ」
と、時輔にたしなめられるのが毎度のことであった。
冷泉家の使者から指定されたのは清水寺である。
「そのような寺は、どこにあるのだ?」
と行藤は使者が帰ったあと、そばの家来にきいたほどである。
落ち着かなかったのは行藤だけではない。
一条家経もやってくるなり、
「今様とはまた考えよったな」
と驚いた。
行藤が着ていたのは浅黄と紫の、左右で色が違う片身違いの直垂である。
ところで。
清水寺が二十一世紀の我々が知る姿になったのははるかな後代だが、寺そのものは往時からある。
道中、行藤が坂の中ほどで振り返ると、見事なまでに京じゅうが見渡せた。
「このようなところがあったとは」
思えば鎌倉は町が狭い。
(町が狭いと人の心も狭くなるのだろうか)
行藤の脳裏にふとよぎった。
本堂への石段を昇った先に、人だかりがある。
「行藤、桜や」
家経が指差した先には、満開に咲き誇る桜の巨樹があった。
「もう咲いたのやな」
鎌倉の桜は、花こそ大きめだが白っぽい。
そこへゆくと、京の桜は花こそ小ぶりだが淡い紅色で、それが抜けるような空によく映える。
「…この美しさは鎌倉にはないものだな」
本堂から少し奥まった御所風の建物に、極楽寺時茂がいた。
「これは行藤どの」
隣は、黒い直垂の目の鋭い武士である。
「時輔どの。こなたは二階堂判官行藤どのじゃ」
行藤は一礼した。
「これは時輔どの、鎌倉の御座所以来でございます」
行藤が頭を下げると、
「行藤どの、ご無沙汰をしておりまする」
「時輔どのには、きけばお子がおわすとか」
「元服して今は時朝となりました」
「左様であられたか」
それより、と時輔はいう。
「さすが二階堂どの。京が長いと、装束もどことなく京風でございますな」
「いずれ時輔どのとて京の気風に染まりましょう」
それに、と行藤は続ける。
「播磨には小山長村どのもおわす。ときには水入らずで昔語りなどもできましょう」
ついでながら、小山長村は時輔の舅である。
宴ははじまった。
境内はやわらかい陽射しが降り注ぎ、時折どこからか田楽の笛のような調べが流れてくる。
が。
行藤はそもそも宴といった賑々しいものは苦手な性質で、出来れば避けたいのが本音である。
(いったい何の因果で)
このようなことになったか…と、行藤には何とも怨めしい思いがあった。
一条家経は気づけばどこかに去ってしまっている。
はぐれたらしい。
ほどなく北条時輔に御座所まで案内され、
「それがしはこれにて」
と離れてしまうと、
(何とも心許ないものよ)
と、行藤はかすかに不安になった。
「こちらにございます」
従者に桟敷に招かれると、奥には機嫌よくきこしめした様子の為家卿が女に酒を注がせている。
「よう参ったのう行藤、こなたへ来りゃれ」
と、杯が出された。
「聞けば武士の習わしでは一度は引き合わせると申すゆえ」
かの者を呼んである、といった。
行藤はすっかり忘れていたが、
「久我の右大将どのの姫ぎみの藤子どのじゃ」
と、為家卿は呼ばわった。
平伏した瞬間、向こうから衣擦れの音がする。
座ったらしい。
「二階堂判官行有が嫡男、藤原行藤にございます」
公卿の世界で二階堂という名字は、どうも通用しないものらしい。
まだ行藤は頭を下げている。
為家卿がすかさず、
「手を上げられよ」
おもてを上げると、例の男装の小姓が、袿姿で座っているのである。
左の頬にえくぼがある。
間違いない。
一瞬、目が泳いだ。
「いかがした行藤。気色がすぐれぬようやが」
為家卿がいぶかるのも無理はない。
「いえ。…斯様にやんごとなき姫様に拝謁をたまわることが、なにぶん初めてのことにございますれば」
「そうか。それは是非もあるまい」
為家卿というこの老公卿は人がよいのか、若い行藤と藤子のために酒肴をととのえていた。
そこへ、
「行藤っ、探したぞ」
と、一条家経の甲高い声がした。
「ここにおったか」
「これは一条の若様。随分ご酒を過ごされたご様子で」
「…これはこれは為家どの、ご無礼つかまつりました」
為家卿には一条家経があらわれた、というだけで良かった。
「実は二階堂の行藤どのと久我の藤子どのとの輿入れの話をしておっての」
「…それは何ともめでたい限りにあられますなあ」
若くても公卿で最高の五摂関家の一員である一条家経をこの場の証人にすることが、どうやら為家卿の真意であったらしい。
(家経も軽々しいのう)
行藤は飲んでる酒の味が分からなくなった。
為家卿にすれば、幕府でも重臣格の二階堂家と堂上人の久我家を結びつけておくことで、鎌倉と京に小さな楔を打ち込むことが深意にあったようで、
「二階堂家も久我家も共に名家ゆえ、この縁組みにはどなたもよもや異議を挟みますまい」
と、一条家経に同意を促した。
家経は頷いた。
行藤は酒の味が混乱でますます分からなくなった。
件の酒宴のあと、行藤と藤子の縁組みが冷泉為家卿の計らいで披露され、晴れて婚約者となった。
そこまではよい。
文永元年当時、すでに京と鎌倉の間にはただならぬ空気が渦巻き始めていた。
きっかけは、一条家経の従兄弟にあたる五代将軍・藤原頼嗣が帰洛、代わりに宗尊親王が将軍として下向した件にはじまる。
宗尊親王。
為家卿が仕える後嵯峨上皇の第一皇子で、
──母の生家が卑賤の出である。
という理由で、皇位を弟に譲ることになり、半分厄介払いの体で鎌倉へ下ったという事情がまずある。
鎌倉に下ると宗尊親王は、いわば飾り物に止まらない言動が目立つようになった。
いわゆる御所派というべき派閥を形成しはじめたのである。
行藤にとって困ったのは、嫁いだばかりの妹の熙子の婚家でもある名越家に、御所派が接触しはじめたことであった。
歳上の義弟にあたる名越時章は、庭に牡丹を植えるのが好きで、争いを好まない性分であった。
名越家は数ある北条一族の中でも、極楽寺家と並んで連署や評定衆を出してきた家でもある。
が。
すぐ下の弟の教時というのが問題で、以前時章の兄が藤原頼嗣の失脚の折、執権の北条時頼の粛清に遭って自害に追い込まれた過去があり、
「時頼の血筋だけは許さぬ」
という恨みを抱いてたのもあって、隙あらばと転覆を狙うふしがあったらしいのであった。
いわば名越家の小さなほころびを糸口に、宗尊親王が将軍としての権威の回復をはかりはじめたのである。
一方。
執権は極楽寺時茂の兄・長時から、一族の重鎮である北条政村へとすでに代替わりしている。
行藤の父・行有と並ぶ和歌の詠み手であり、地方の行政に強い人物でもある。
その北条政村が手をつけた異動は、宗尊親王の近侍にいた二階堂行有を、新しく設置された引付衆という役職に据えるといういわゆる引き抜き人事であった。
行藤の縁談はいわば、そうした朝廷と幕府の力の綱引きのはざまにある話でもある。
が。
藤子も行藤もそうした込み入った懸案は知らなかったらしく、単に、
「見も知らぬ相手と夫婦になるよりは良い」
という程度の認識でしかない。
その辺りの行藤の楽観的な見方を危惧していたのは、北条時輔である。
「判官どのももう少し気をつけられてはどうか」
と、時輔に忠告されるのはしばしばで、行藤が露骨に嫌な顔をすると、
「それでは二階堂家は滅びますぞ」
と、時輔にたしなめられるのが毎度のことであった。