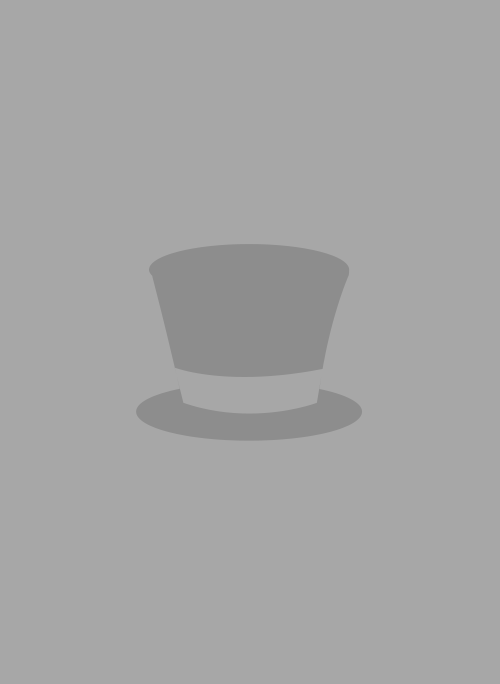花の季節が終わり、柔らかな緑の葉が青空に映える午後、初めて逢った日と同じ桜色のワンピースを着たさくらは、小さな紙袋一つを持って退院した。
紙袋の中身は入院中に翔が用意してやった身の回りの品だけで、今のさくらにとって、それが彼女の持ち物の全てだった。
事故から2週間余り経ってもさくらの記憶は相変わらずだったが、毎日見舞う翔には誰よりも心を開き笑顔を見せるようになっていた。
自分に全幅の信頼を置く無垢な彼女は、まるで歩き始めたばかりの幼子(おさなご)のようだと、翔は時々思う。
何をするにも頼りなく、手を引いてやらなくては歩みすら危ういのではないかと不安になるほどだ。
彼女にとって自分は親鳥で、唯一無二の絶対的存在なのだと思うと、不思議なほどに近い存在のように感じるし、愛しくも思えてくる。
男として庇護欲を掻きたてるのとは少し違うこの感覚は、もしかしたら父親の心境なのだろうかと、齢二十歳(よわいはたち)にして既に娘を持ったような複雑な気持ちになった。
紙袋の中身は入院中に翔が用意してやった身の回りの品だけで、今のさくらにとって、それが彼女の持ち物の全てだった。
事故から2週間余り経ってもさくらの記憶は相変わらずだったが、毎日見舞う翔には誰よりも心を開き笑顔を見せるようになっていた。
自分に全幅の信頼を置く無垢な彼女は、まるで歩き始めたばかりの幼子(おさなご)のようだと、翔は時々思う。
何をするにも頼りなく、手を引いてやらなくては歩みすら危ういのではないかと不安になるほどだ。
彼女にとって自分は親鳥で、唯一無二の絶対的存在なのだと思うと、不思議なほどに近い存在のように感じるし、愛しくも思えてくる。
男として庇護欲を掻きたてるのとは少し違うこの感覚は、もしかしたら父親の心境なのだろうかと、齢二十歳(よわいはたち)にして既に娘を持ったような複雑な気持ちになった。