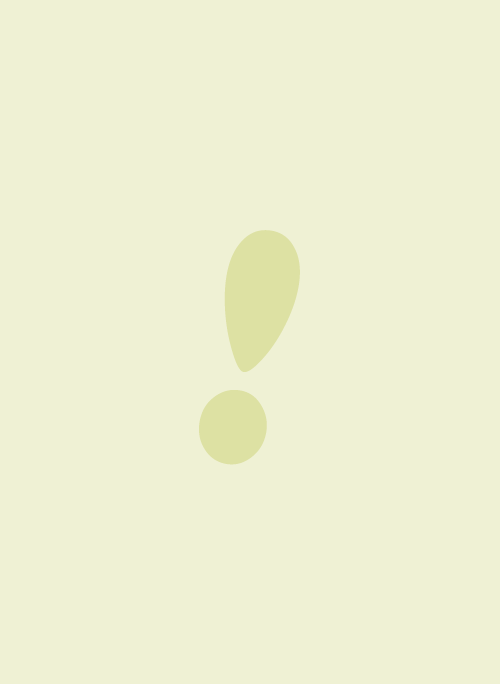バッグの中で携帯が鳴っている。
「もしもし麗ちゃん。これから行くから。」
「一行、連れて行ってほしい所があるの。」
「どこ?」
「彼女が歌っているお店。」
一行は、わかったと静かに言った。
身の丈に合った生き方をすることは、挑戦しない事とは違うと、ずっと思って来た。
プライドを持って信じて来た。
でも一行、弱音は吐いていいんだよ。
他の方法があるんだと、立ち止まって、うずくまって、天を仰いでも、人生は簡単に見捨てる事はないはずだから。
そして遠くにいても、私を認めてくれた夫を、私は一時だって忘れる事はない。
ゆっくりドアの開く音がした。
「あっ、キャリアウーマンだ。」
「人をスーパーマンみたいに。
ただいま。」
「おかえり。」
笑っているのに、涙がこぼれるのはなぜ?
旅立つあの日、涼に見せたそれとは違う涙は、暖かく此の上ない幸せなものだった。
手をつないで歩く道は、一歩一歩確実にその店へ向かっている。
「園さんだったよね。」
「北原 園」
涼の志が決断させたというその歌声を、どうしても聞きたいと思った。
一行が作ったというその曲を聞かずに、アメリカへ戻るわけにはいかなかった。
「M」のドアを開ける手が少し震えていたけど、中に入るとすぐにその歌声は、身体を包み込むほどの迫力を放った。
”誰も立ち止まる時がある。
そんな時もある。
愛されているはずなのに…
愛しているはずなのに…“
歌い終わって、園は私達の方を向き、私にゆっくり礼をした。
私は何度も拍手をし、そしてまたゆっくり頭を下げた。
涼が夢を追い、園が魂をぶつけ、その中で一行は私の存在とそれを比べたのかもしれない。
「楽園」と云う真実を探して…
「もしもし麗ちゃん。これから行くから。」
「一行、連れて行ってほしい所があるの。」
「どこ?」
「彼女が歌っているお店。」
一行は、わかったと静かに言った。
身の丈に合った生き方をすることは、挑戦しない事とは違うと、ずっと思って来た。
プライドを持って信じて来た。
でも一行、弱音は吐いていいんだよ。
他の方法があるんだと、立ち止まって、うずくまって、天を仰いでも、人生は簡単に見捨てる事はないはずだから。
そして遠くにいても、私を認めてくれた夫を、私は一時だって忘れる事はない。
ゆっくりドアの開く音がした。
「あっ、キャリアウーマンだ。」
「人をスーパーマンみたいに。
ただいま。」
「おかえり。」
笑っているのに、涙がこぼれるのはなぜ?
旅立つあの日、涼に見せたそれとは違う涙は、暖かく此の上ない幸せなものだった。
手をつないで歩く道は、一歩一歩確実にその店へ向かっている。
「園さんだったよね。」
「北原 園」
涼の志が決断させたというその歌声を、どうしても聞きたいと思った。
一行が作ったというその曲を聞かずに、アメリカへ戻るわけにはいかなかった。
「M」のドアを開ける手が少し震えていたけど、中に入るとすぐにその歌声は、身体を包み込むほどの迫力を放った。
”誰も立ち止まる時がある。
そんな時もある。
愛されているはずなのに…
愛しているはずなのに…“
歌い終わって、園は私達の方を向き、私にゆっくり礼をした。
私は何度も拍手をし、そしてまたゆっくり頭を下げた。
涼が夢を追い、園が魂をぶつけ、その中で一行は私の存在とそれを比べたのかもしれない。
「楽園」と云う真実を探して…