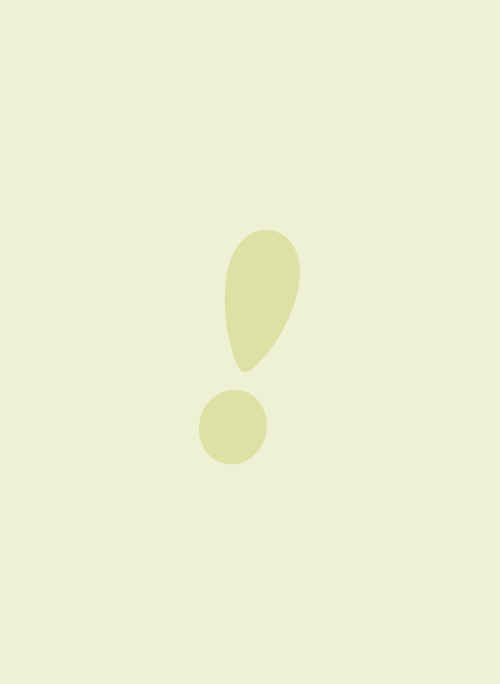慌てて駆け込んだ空港で、私はチケットを買い、すぐ一行に電話を入れた。
ちょっとした着替えだけを詰め込んで、履き慣れたスニーカーで、化粧っけもなく、まるで何かに追われて、慌てて逃げて来たかのようにここまで来た。
夢中だった。
「もしもし一行、寝てた?
もうすぐ発つからね。
着いたらまた連絡いれるから。」
「うん、わかった。
ありがとう、麗ちゃん。
気を付けて来て。
途中で気が変わったなんて、言いっこなしだよ。」
「何言ってんの。
スッピンで走って来たのよ。
リレーの選手だったって言わなかったっけ?
まだ少しは寝られるでしょ。
一行、起こしちゃってごめんね。
もう一度寝て。
おやすみ。」
明るく振る舞おうとして、ちょっと浮いてしまったかな。
電話を切り、出発の時間が来るまで、ゲート近くのカフェで軽い食事をとることにした。
そして、涼が会社を辞め、プロ棋士を目指して歩き出したという真実が、どれだけ一行の心に衝撃を与えたのかを考えていた。
もちろん私にとっても、耳を疑うほどの事だった。
あの長い手紙のどこにも、会社の事、囲碁の事なんか、一切触れられてはいなかったから。
ただ、ただ、熱い想いだけが綴られていたその手紙は今はもうどこにもない。
その手紙の事はいつか話そうと思っていたけれど、一行に話すべき事ではないと、今私は強く心に釘を刺した。
夢は、闘うものじゃない。
頑張った人が報われる世の中が誰にでも当てはまる未来なら、希望も、野望も、遠望も、容易い日常となって、たいした価値を持たなくなってしまうだろう。
私が会社を辞める決心をしたのだって、涼が言った
「麗子さんが幸せじゃないと、一行も幸せにはなれないですよ。」
その言葉だったはず。
自ら、より厳しい世界を目指して行こうとしていた涼だから、言えた言葉だったのだ。
コーヒーを飲みながら、
「これから急に帰国する事になりました。
戻りましたら、連絡させていただきます。」
と、岩沢へ宛てたメールを入れた。
ちょっとした着替えだけを詰め込んで、履き慣れたスニーカーで、化粧っけもなく、まるで何かに追われて、慌てて逃げて来たかのようにここまで来た。
夢中だった。
「もしもし一行、寝てた?
もうすぐ発つからね。
着いたらまた連絡いれるから。」
「うん、わかった。
ありがとう、麗ちゃん。
気を付けて来て。
途中で気が変わったなんて、言いっこなしだよ。」
「何言ってんの。
スッピンで走って来たのよ。
リレーの選手だったって言わなかったっけ?
まだ少しは寝られるでしょ。
一行、起こしちゃってごめんね。
もう一度寝て。
おやすみ。」
明るく振る舞おうとして、ちょっと浮いてしまったかな。
電話を切り、出発の時間が来るまで、ゲート近くのカフェで軽い食事をとることにした。
そして、涼が会社を辞め、プロ棋士を目指して歩き出したという真実が、どれだけ一行の心に衝撃を与えたのかを考えていた。
もちろん私にとっても、耳を疑うほどの事だった。
あの長い手紙のどこにも、会社の事、囲碁の事なんか、一切触れられてはいなかったから。
ただ、ただ、熱い想いだけが綴られていたその手紙は今はもうどこにもない。
その手紙の事はいつか話そうと思っていたけれど、一行に話すべき事ではないと、今私は強く心に釘を刺した。
夢は、闘うものじゃない。
頑張った人が報われる世の中が誰にでも当てはまる未来なら、希望も、野望も、遠望も、容易い日常となって、たいした価値を持たなくなってしまうだろう。
私が会社を辞める決心をしたのだって、涼が言った
「麗子さんが幸せじゃないと、一行も幸せにはなれないですよ。」
その言葉だったはず。
自ら、より厳しい世界を目指して行こうとしていた涼だから、言えた言葉だったのだ。
コーヒーを飲みながら、
「これから急に帰国する事になりました。
戻りましたら、連絡させていただきます。」
と、岩沢へ宛てたメールを入れた。