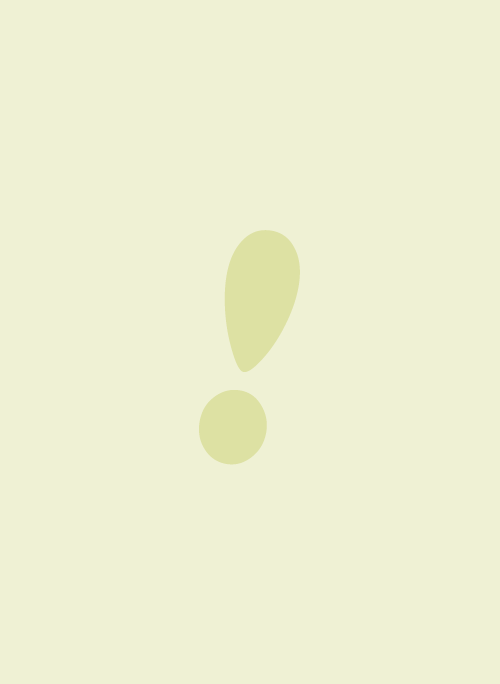涼のそんな事実は何も知らぬまま、新しい暮らしは、予想以上にハードな毎日の繰り返しになった。
覚悟はしていたつもりだったけれど、会社勤めの、ある意味慣れてしまった流れとはまったく違う、確立された組み立て方や、控え目が得とされる古い形式は、置いていかれるばかりの厳しい現実の中にいる。
専門的な分野になれば、なおさら深い知識を必要とされ、勢いに任せ、会社帰りに語学スクールにも通うことにした。
一行とは、メールがほとんどになり、声を聞きたいと、たまに電話しても、時差やら、タイミングやら、なかなか難しく、パソコンを開けるのが最大の楽しみになってしまっている。
こうして得られるだけの力を蓄え、一行の元に帰り着く日まで、どれだけの朝を迎えるのだろうかと考えるだけで、気が遠くなりそうだけれど、考え方によっては、その日までのカウントダウンでもあると、自分で自分を慰めている。
そうでも思わないと、恋しくて、切なくて、身の置き場が見つからないのだ。
まだ形も何も、始まってさえいないと言うのに。
今の私に出来る事。
それは、すべてを受け入れてくれた夫に、期待以上の成果を披露すること。
それが私の目標のひとつでもある。
もちろん、日本で会社を起ち上げ、私が私である生き方を示して行く事が、根底にはあるのだけれど。
顔をあげて夢を語る事に、照れていてはいけない。
叶わない夢はないんだと、強く言い聞かせて、ここまで来た事を忘れてはならない。
そう、改めて誓うのだ。
疲れきった身体は、このままベッドに入ればすぐに記憶が無くなるほどだけれど、今晩も語学スクールの扉が私を待っている。
幾人かの顔見知りも出来、少しずつ緊張も無くなり、こんな事がこの地の住人となって行く事なんだと、ふと思う。
「あっ、岩沢さんじゃないですか?」
見覚えのある横顔が、私を追い越して行った。
「おぉ、やっぱり会いましたね。
こんな日が来るんじゃないかと、楽しみにしていましたよ。」
覚悟はしていたつもりだったけれど、会社勤めの、ある意味慣れてしまった流れとはまったく違う、確立された組み立て方や、控え目が得とされる古い形式は、置いていかれるばかりの厳しい現実の中にいる。
専門的な分野になれば、なおさら深い知識を必要とされ、勢いに任せ、会社帰りに語学スクールにも通うことにした。
一行とは、メールがほとんどになり、声を聞きたいと、たまに電話しても、時差やら、タイミングやら、なかなか難しく、パソコンを開けるのが最大の楽しみになってしまっている。
こうして得られるだけの力を蓄え、一行の元に帰り着く日まで、どれだけの朝を迎えるのだろうかと考えるだけで、気が遠くなりそうだけれど、考え方によっては、その日までのカウントダウンでもあると、自分で自分を慰めている。
そうでも思わないと、恋しくて、切なくて、身の置き場が見つからないのだ。
まだ形も何も、始まってさえいないと言うのに。
今の私に出来る事。
それは、すべてを受け入れてくれた夫に、期待以上の成果を披露すること。
それが私の目標のひとつでもある。
もちろん、日本で会社を起ち上げ、私が私である生き方を示して行く事が、根底にはあるのだけれど。
顔をあげて夢を語る事に、照れていてはいけない。
叶わない夢はないんだと、強く言い聞かせて、ここまで来た事を忘れてはならない。
そう、改めて誓うのだ。
疲れきった身体は、このままベッドに入ればすぐに記憶が無くなるほどだけれど、今晩も語学スクールの扉が私を待っている。
幾人かの顔見知りも出来、少しずつ緊張も無くなり、こんな事がこの地の住人となって行く事なんだと、ふと思う。
「あっ、岩沢さんじゃないですか?」
見覚えのある横顔が、私を追い越して行った。
「おぉ、やっぱり会いましたね。
こんな日が来るんじゃないかと、楽しみにしていましたよ。」