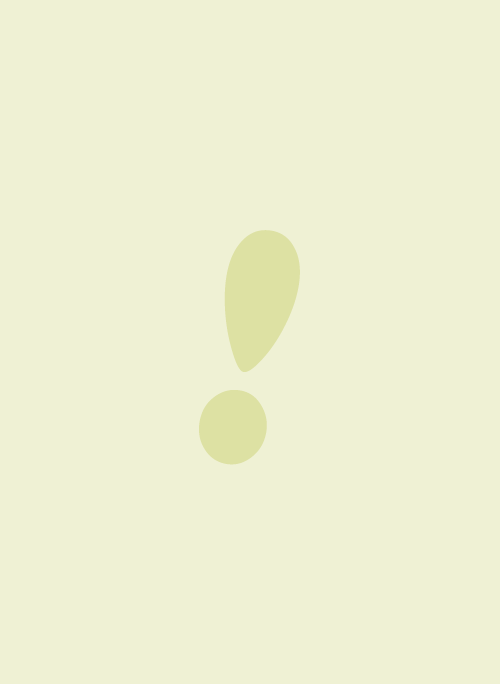奇跡とは 信じる者の内側にあるものが、祈りで実現させるものなのだろうか。
さぁ 道は開かれたのだ。
私達が結婚したことを、涼は知る時を間違えたのかもしれないと、一行は私に言った。
空港で起きてしまった、二人を待ち構えていた一部始終を、アメリカに着いたその時、私は全てを知らされたのだ。
私がそのまま知らないでいても、時の力が働いて、過去に起きた出来事だったと、記憶の枠から外されて行く日が来るのは承知していても、一行にしてみれば片腕をもぎ取られるような想いだったに違いないのだ。
出発の時、私が触れた涼のその同じ頬には、一行が放った溺れる程の悲しすぎる涙が流れ続け、そしてそれが、二人の履歴をそこまでのものにしてしまったのだとしたら、私に課せられた罪は、やはり重いものになるのかもしれない。
生きている事の保証は、生きて行く事の好奇心と上手に付き合って行く事や、自己愛ばかりを抱えて、身動き出来ない姿にならない日常や、大切なものを確認する”ふるい“に、自ら立ち向かう決断だったりするんだろう。
「一行、私が涼君といた所 見たのね。」
「うん。
走って行けば間に合ったのかもしれない。
だけど、足が動かなかったんだよ。
今考えたら、麗ちゃんをちゃんと見送る事の方が大事だったのに、冷静ではいられなかったんだ。
なんでこんな事になったんだろう。」
「ごめんね、一行。
私、一行に会えずに行く事を覚悟して、踏ん張ったつもりだったの。
だけど、あんまり寂しくて、涼君の顔見たら少しだけ嬉しいと思った自分がいたの。
涼君の姿に、一行を見たのよ。
だけど、あんなとこ見たら、怒るに決まってるよね。」
一行は黙ったまま、少し時間を置いて
「涼と、ちゃんと話して見るよ。
麗ちゃんは、しっかり仕事と勉強と…」
一行が泣いている。
自分の人生より、一行が大事なんだという事を、どうやって伝えたらいいのか、必死で言葉を探している。
「昨日より、もっと一行の事が好きよ。」
柵があればあるほど、人は胸を張って進まなければならない時がある。
さぁ 道は開かれたのだ。
私達が結婚したことを、涼は知る時を間違えたのかもしれないと、一行は私に言った。
空港で起きてしまった、二人を待ち構えていた一部始終を、アメリカに着いたその時、私は全てを知らされたのだ。
私がそのまま知らないでいても、時の力が働いて、過去に起きた出来事だったと、記憶の枠から外されて行く日が来るのは承知していても、一行にしてみれば片腕をもぎ取られるような想いだったに違いないのだ。
出発の時、私が触れた涼のその同じ頬には、一行が放った溺れる程の悲しすぎる涙が流れ続け、そしてそれが、二人の履歴をそこまでのものにしてしまったのだとしたら、私に課せられた罪は、やはり重いものになるのかもしれない。
生きている事の保証は、生きて行く事の好奇心と上手に付き合って行く事や、自己愛ばかりを抱えて、身動き出来ない姿にならない日常や、大切なものを確認する”ふるい“に、自ら立ち向かう決断だったりするんだろう。
「一行、私が涼君といた所 見たのね。」
「うん。
走って行けば間に合ったのかもしれない。
だけど、足が動かなかったんだよ。
今考えたら、麗ちゃんをちゃんと見送る事の方が大事だったのに、冷静ではいられなかったんだ。
なんでこんな事になったんだろう。」
「ごめんね、一行。
私、一行に会えずに行く事を覚悟して、踏ん張ったつもりだったの。
だけど、あんまり寂しくて、涼君の顔見たら少しだけ嬉しいと思った自分がいたの。
涼君の姿に、一行を見たのよ。
だけど、あんなとこ見たら、怒るに決まってるよね。」
一行は黙ったまま、少し時間を置いて
「涼と、ちゃんと話して見るよ。
麗ちゃんは、しっかり仕事と勉強と…」
一行が泣いている。
自分の人生より、一行が大事なんだという事を、どうやって伝えたらいいのか、必死で言葉を探している。
「昨日より、もっと一行の事が好きよ。」
柵があればあるほど、人は胸を張って進まなければならない時がある。