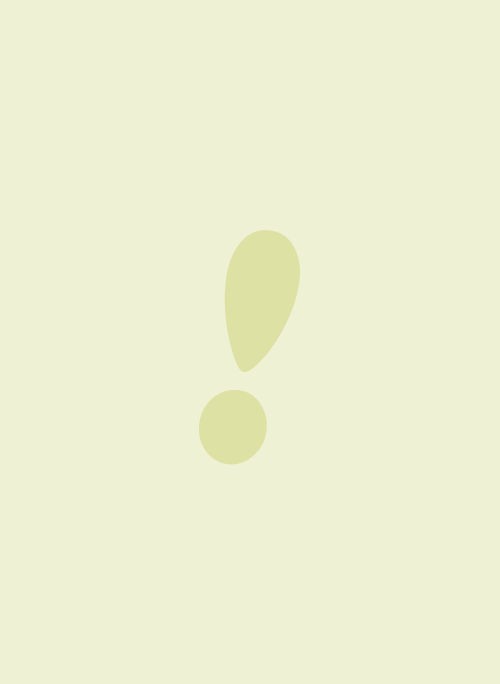僕の名前じゃなかった。
一緒にいたはずなのに、妻が故郷へ帰りたい気持ちも、その淋しさも後回しにして、ずっと隣にいるものだと思っていたんです。
これから先の人生をひとりで考えてみろと、妻は私に大きな宿題を置いていきました。」
「失礼を承知でお聞きしますが、その男性は奥様とは…」
「僕と結婚する前の恋人だとわかりました。
不貞があったわけじゃないんです。
故郷を忘れられなかったんでしょう。
そうでも思わないと、こんな歳でも耐えられませんから。」
孤独は、素直な問いかけにさえも、その答えを受け付ける余裕や、導き出す方法を簡単には教えてくれない。
「すみません。
聞いてはいけない事でした。」
「いや、そんな事はないですよ。
私こそ、結婚されたばかりの方に、話すべき事ではなかったかな。」
それぞれの心と会話をするのに、少しの間
沈黙が流れた。
「あの、教えて頂けますか。
私が今日からアメリカで過ごす数年は、妻の役目を放棄することになるんでしょうか。」
「あなたは面白い方ですね。
どういう事情であなたがアメリカへ行くのか、僕は何も分からないけど、あなたの顔はちゃんと答えを見つけているように見えますよ。」
暗闇から見えて来たのは、果てしなく続くネオンの海。
ここに、私は立つ。
「道案内ぐらいは出来ますよ。」
と、差し出された名刺は、私の知っている会社名が書いてあった。
「どこかで擦れ違ったら、飲みにでもお誘いしますよ。
新婚さんには断わられるかな。」
「もしもし、一行。
聞こえる?」
「麗ちゃん、ごめん。間に合わなくて。
ちゃんと着いた?」
「うん。着いた。
一行、聞こえる?
ちゃんと聞いて。
一行の奥さんにしてくれてありがとう。」
「えっ?
麗ちゃん、改まってどうしたのさ。」
「ちゃんと言ってなかったから。」
「どういたしまして」
一緒にいたはずなのに、妻が故郷へ帰りたい気持ちも、その淋しさも後回しにして、ずっと隣にいるものだと思っていたんです。
これから先の人生をひとりで考えてみろと、妻は私に大きな宿題を置いていきました。」
「失礼を承知でお聞きしますが、その男性は奥様とは…」
「僕と結婚する前の恋人だとわかりました。
不貞があったわけじゃないんです。
故郷を忘れられなかったんでしょう。
そうでも思わないと、こんな歳でも耐えられませんから。」
孤独は、素直な問いかけにさえも、その答えを受け付ける余裕や、導き出す方法を簡単には教えてくれない。
「すみません。
聞いてはいけない事でした。」
「いや、そんな事はないですよ。
私こそ、結婚されたばかりの方に、話すべき事ではなかったかな。」
それぞれの心と会話をするのに、少しの間
沈黙が流れた。
「あの、教えて頂けますか。
私が今日からアメリカで過ごす数年は、妻の役目を放棄することになるんでしょうか。」
「あなたは面白い方ですね。
どういう事情であなたがアメリカへ行くのか、僕は何も分からないけど、あなたの顔はちゃんと答えを見つけているように見えますよ。」
暗闇から見えて来たのは、果てしなく続くネオンの海。
ここに、私は立つ。
「道案内ぐらいは出来ますよ。」
と、差し出された名刺は、私の知っている会社名が書いてあった。
「どこかで擦れ違ったら、飲みにでもお誘いしますよ。
新婚さんには断わられるかな。」
「もしもし、一行。
聞こえる?」
「麗ちゃん、ごめん。間に合わなくて。
ちゃんと着いた?」
「うん。着いた。
一行、聞こえる?
ちゃんと聞いて。
一行の奥さんにしてくれてありがとう。」
「えっ?
麗ちゃん、改まってどうしたのさ。」
「ちゃんと言ってなかったから。」
「どういたしまして」