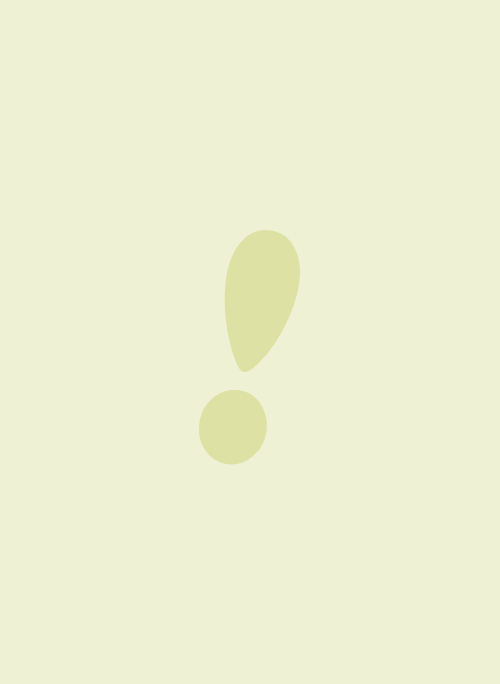「お仕事ですか?」
静かな声でコーヒーを手渡された時から、アメリカへ到着するまでの間、私は見知らぬその紳士に、私の知らない生き方を教わる事になる。
「はい。
半分は勉強です。
先ほどは恥ずかしい姿をお見せして、失礼致しました。」
「いや、恥ずかしいことなどないですよ。
人には、それぞれの事情ってものがありますから。」
五十代後半ぐらいだろうか、慣れたスーツの着こなしは、それなりの山場を踏んで来た、品格のある、自信にあふれた、余裕さえ感じさせるものに見える。
「失礼ですが、観光にはお見受け出来ませんが。」
「えぇ、東京へは二十年ぶりに戻りました。
妻の分骨を済ませて、帰る所です。」
優しいと思っていた微笑みの裏には、折りたたんだ哀しみがあった。
「あっ、そうでしたか。
それは、痛ましい事でした。
まだお若くていらっしゃったでしょうに…」
「亡くなって、半年経ちます。
やっと妻の想いを叶えてあげる事が出来ました。
僕は、あまり良い夫ではなかった事に、妻が亡くなってから気付いた愚か者なんですよ。
アメリカへ行ってから、一度も日本へ帰る事はなかったんです。
帰りたいと、何度も聞いていながら、実現出来ずに見送ってしまった事が悔まれます。
骨になって戻っても、妻は喜んでくれているかどうか、わからないんですが。
失礼ですが、ご結婚は?」
「はい。
十日程前にしたばかりです。」
「おぉ、それはおめでとうございます。
そうすると、見送りされていた方は、ご主人でしたか。
ちょうどあなたの後ろにいて、目に入ってしまいました。」
「いえ、彼は夫の友人です。
夫は間に合いませんでした。」
何か共通の哀しみを見つけた気がした。
私の事には触れず、彼は話し始めた。
「僕は仕事ばかりしていて、妻が病気になっている事にも気付いてあげられなかったんです。
ばちが当たったんですよ。
最期の時に意識が混濁して、私の手を握りながら、妻は私の知らない男の名前を呼んだんです。
静かな声でコーヒーを手渡された時から、アメリカへ到着するまでの間、私は見知らぬその紳士に、私の知らない生き方を教わる事になる。
「はい。
半分は勉強です。
先ほどは恥ずかしい姿をお見せして、失礼致しました。」
「いや、恥ずかしいことなどないですよ。
人には、それぞれの事情ってものがありますから。」
五十代後半ぐらいだろうか、慣れたスーツの着こなしは、それなりの山場を踏んで来た、品格のある、自信にあふれた、余裕さえ感じさせるものに見える。
「失礼ですが、観光にはお見受け出来ませんが。」
「えぇ、東京へは二十年ぶりに戻りました。
妻の分骨を済ませて、帰る所です。」
優しいと思っていた微笑みの裏には、折りたたんだ哀しみがあった。
「あっ、そうでしたか。
それは、痛ましい事でした。
まだお若くていらっしゃったでしょうに…」
「亡くなって、半年経ちます。
やっと妻の想いを叶えてあげる事が出来ました。
僕は、あまり良い夫ではなかった事に、妻が亡くなってから気付いた愚か者なんですよ。
アメリカへ行ってから、一度も日本へ帰る事はなかったんです。
帰りたいと、何度も聞いていながら、実現出来ずに見送ってしまった事が悔まれます。
骨になって戻っても、妻は喜んでくれているかどうか、わからないんですが。
失礼ですが、ご結婚は?」
「はい。
十日程前にしたばかりです。」
「おぉ、それはおめでとうございます。
そうすると、見送りされていた方は、ご主人でしたか。
ちょうどあなたの後ろにいて、目に入ってしまいました。」
「いえ、彼は夫の友人です。
夫は間に合いませんでした。」
何か共通の哀しみを見つけた気がした。
私の事には触れず、彼は話し始めた。
「僕は仕事ばかりしていて、妻が病気になっている事にも気付いてあげられなかったんです。
ばちが当たったんですよ。
最期の時に意識が混濁して、私の手を握りながら、妻は私の知らない男の名前を呼んだんです。