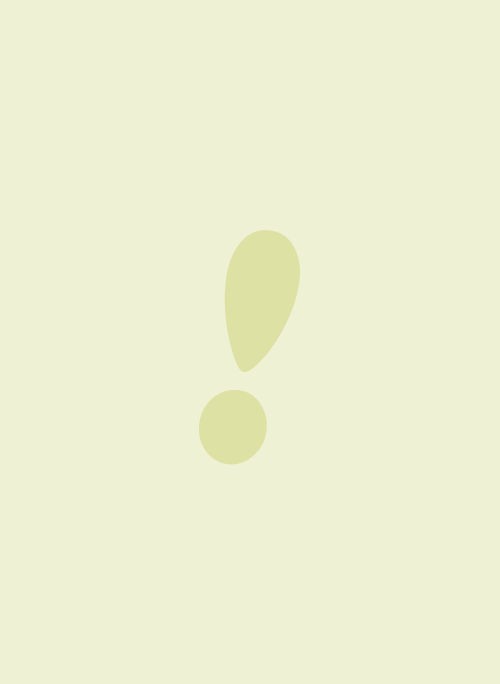さっき、麗子が触れたその同じ頬を。
足を止め、人々が振り返る。
座り込んだまま、涼は動かない。
立ち向かう気など、はなから無いように。
「涼、大丈夫か。」
差し出した手の方が、涼の頬より痛い事を、これからしっかり話さなければならないのだ。
今をどう生かして、これからどう生きようとしているのか、友達なら聞き入れる覚悟はあるだろう。
「涼、ちゃんと聞いてくれ。
俺は麗子と結婚した。
麗子は俺の妻だ。
もう関わらないでくれ。」
涼の背中が丸く、小さく、消えて行く。
私は泣かずにこの手紙を読み終えた。
長い手紙は、自分の情熱でこじあけようとしている重い扉の鍵のような気がした。
意欲と、危険な賭けの狭間で、もがき苦しんでいる。
私はこの長い手紙を、読みかけの雑誌にはさみ、通りかかった搭乗員に渡した。
「捨ててください。」
そう言って。
「お仕事ですか?」
テーブルには二杯目のコーヒーが差し出された。
足を止め、人々が振り返る。
座り込んだまま、涼は動かない。
立ち向かう気など、はなから無いように。
「涼、大丈夫か。」
差し出した手の方が、涼の頬より痛い事を、これからしっかり話さなければならないのだ。
今をどう生かして、これからどう生きようとしているのか、友達なら聞き入れる覚悟はあるだろう。
「涼、ちゃんと聞いてくれ。
俺は麗子と結婚した。
麗子は俺の妻だ。
もう関わらないでくれ。」
涼の背中が丸く、小さく、消えて行く。
私は泣かずにこの手紙を読み終えた。
長い手紙は、自分の情熱でこじあけようとしている重い扉の鍵のような気がした。
意欲と、危険な賭けの狭間で、もがき苦しんでいる。
私はこの長い手紙を、読みかけの雑誌にはさみ、通りかかった搭乗員に渡した。
「捨ててください。」
そう言って。
「お仕事ですか?」
テーブルには二杯目のコーヒーが差し出された。