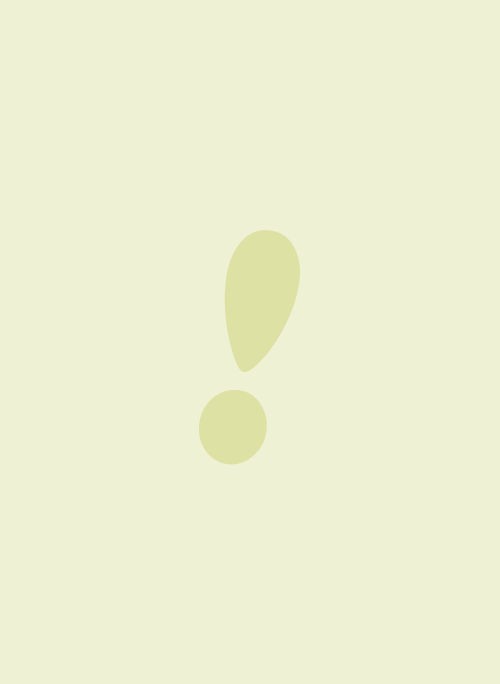曇の上から切目のない空を、ずっと見ている。
離れたからこそ、解る真実もあるのだろうと、到着するまで、果てしないと感じるだろう耐えがたい孤独感に打ち克つ術を、私の心は模索している。
時の癒しを求めるのは、もう自分の心しか無いのかもしれないと、言い聞かせてはため息をつく。
手渡されたこの手紙に書いてある事は、今の私が見つめなければならない将来なのか、開けるタイミングがわからないでいる。
離陸する瞬間、一行がどこかでしっかり見送ってくれていたと信じてはいても、触れてはいないその姿に、私の心は置き去りにされたようだ。
この手の中にある、強く握った指の跡がついた封筒は、私に何を語ると言うのだ。
「市川麗子様
初めて会った日の事を覚えていますか?
僕は決して忘れる事はありません。
あの日、テーブルの一番奥で笑っていたあなたは、聞いていたキャリアウーマンではなく、とても美しい、僕には特別な女性でした。
僕は目が離せなかった。
あれからあなたはずっと、僕の前を歩き続けています。
僕の心には、いつもあなたがいます。」
恋は、したもの勝ちなのか。
時を癒してと悶える私に、この今の空間は、何の自由も許してはくれない。
なぜ今なの。
一行が一足違いで空港に駆け込んだ時、やっと見つけた彼女の前には、見慣れたはずの涼の姿があった。
手を振り、力の限り
また手を振り、それは愛している人に向けられた、それ以外のなにものでもないように見えた。
だけど、涼がそうして見送る姿は、一行の耐えすぎた気持ちを抑えさせはしなかった。
ただひとり見送る事になった涼を、一行は許しはしなかった。
「涼、何してるんだよ。」
涼は、身じろぎもせず顔だけ振り返った。
驚いた顔は、あまりの事に表情がない。
「涼、何してるんだよ。
なんで電話に出なかったんだよ。
電話もメールも、何度したと思ってるんだよ。」
「ごめん。」
言葉が出尽す前に、一行の拳が涼の頬を貫いた。
離れたからこそ、解る真実もあるのだろうと、到着するまで、果てしないと感じるだろう耐えがたい孤独感に打ち克つ術を、私の心は模索している。
時の癒しを求めるのは、もう自分の心しか無いのかもしれないと、言い聞かせてはため息をつく。
手渡されたこの手紙に書いてある事は、今の私が見つめなければならない将来なのか、開けるタイミングがわからないでいる。
離陸する瞬間、一行がどこかでしっかり見送ってくれていたと信じてはいても、触れてはいないその姿に、私の心は置き去りにされたようだ。
この手の中にある、強く握った指の跡がついた封筒は、私に何を語ると言うのだ。
「市川麗子様
初めて会った日の事を覚えていますか?
僕は決して忘れる事はありません。
あの日、テーブルの一番奥で笑っていたあなたは、聞いていたキャリアウーマンではなく、とても美しい、僕には特別な女性でした。
僕は目が離せなかった。
あれからあなたはずっと、僕の前を歩き続けています。
僕の心には、いつもあなたがいます。」
恋は、したもの勝ちなのか。
時を癒してと悶える私に、この今の空間は、何の自由も許してはくれない。
なぜ今なの。
一行が一足違いで空港に駆け込んだ時、やっと見つけた彼女の前には、見慣れたはずの涼の姿があった。
手を振り、力の限り
また手を振り、それは愛している人に向けられた、それ以外のなにものでもないように見えた。
だけど、涼がそうして見送る姿は、一行の耐えすぎた気持ちを抑えさせはしなかった。
ただひとり見送る事になった涼を、一行は許しはしなかった。
「涼、何してるんだよ。」
涼は、身じろぎもせず顔だけ振り返った。
驚いた顔は、あまりの事に表情がない。
「涼、何してるんだよ。
なんで電話に出なかったんだよ。
電話もメールも、何度したと思ってるんだよ。」
「ごめん。」
言葉が出尽す前に、一行の拳が涼の頬を貫いた。