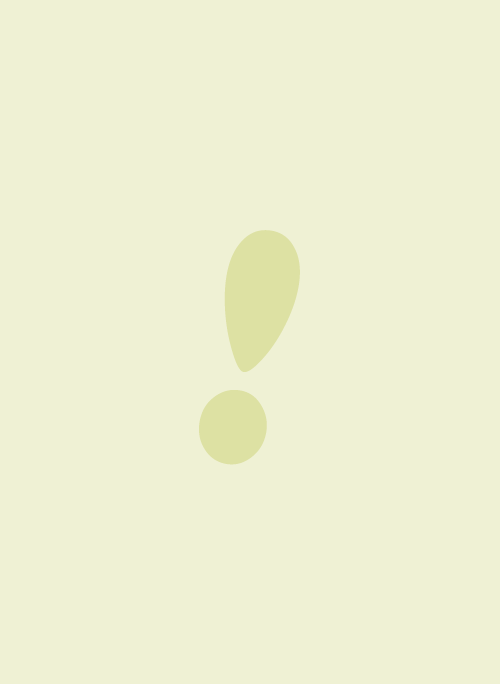「叱られるかな。」
「大丈夫だよ。
麗ちゃんに会えば、解ってくれるよ。」
心が折れるような思いを、一行もしていたんだ。
私達はその日、早い時間から移動し、一行の家族が待つ一行の故郷へ向かった。
ふたりで生きて行くということは、こういう事なんだと、責任の上に成り立つ、信用を得ることなんだと、改めて知らされる思いだった。
そして、有難うございますと涙した日が、私達の約束を現実のものにしようとしていた。
空港が近づき、込み合う人の流れに負けそうになりながら、大阪から来る一行を待った。
窓際の隅に座り、コーヒーを飲みながら、私の目に入ってきたものは、目立たないようにベンチに座る涼の姿だった。
自動ドアから離れたカウンターを見つめ、動かない涼に、
”行って来ます“
とつぶやいた。
会わないつもりでいるのはわかっているから、声はかけないで行くね。