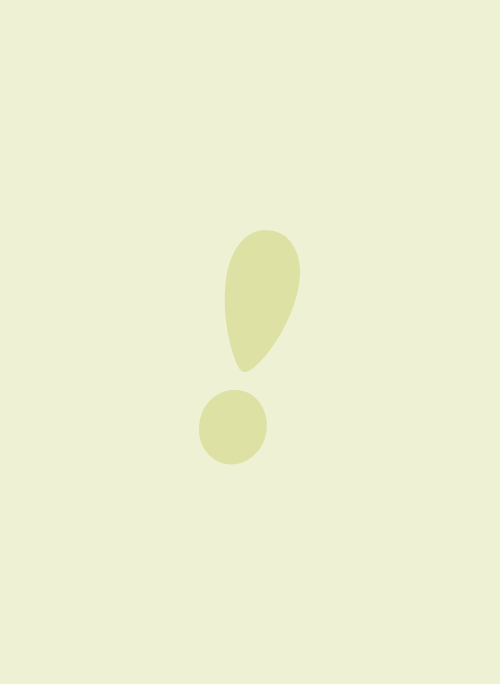土曜日は早くから家を出て、現実から少しだけ遠くへと云う想いが、歩幅を広めに歩いている気がするほどだ。
ちょっと会わないだけで、一行は急に大人びて、ひとまわり成長したように見えた。
あまり片付いていない部屋で、一緒にいた頃のように笑い合う事だけで、私達は充分だった。
一行が得意なパスタは、特別美味しく、私は何処かで、こんな日が続くと信じていた自分を恨んでいた。
アメリカへの準備のこと。
会社との兼ね合いで、出発が一ヶ月半後になったこと。
遅くまで話が尽きる事はなかった。
そして日曜、一行が行こうと私の手を取ったその場所へ、私は泣きながら向かうことになった。
死ぬまで私は、決してこの日を忘れる事はないだろう。
そしてそれから、離れようとしている恋人に、してあげられる事は何だろうと、ずっと答えを探している。
早朝、太陽がまた美しく輝く時、眩しそうに手をかざして、指の隙間からこぼれる陽射しに顔を預けている。
私は 空港に向かっている。
震えているのは朝露のせいだ。
右手にはパスポートが握られている。
緊張気味に写った写真に向かって、しっかりしろと拳を作る。
パスポートには
「鈴木麗子」
と 書いてある。
ちょっと会わないだけで、一行は急に大人びて、ひとまわり成長したように見えた。
あまり片付いていない部屋で、一緒にいた頃のように笑い合う事だけで、私達は充分だった。
一行が得意なパスタは、特別美味しく、私は何処かで、こんな日が続くと信じていた自分を恨んでいた。
アメリカへの準備のこと。
会社との兼ね合いで、出発が一ヶ月半後になったこと。
遅くまで話が尽きる事はなかった。
そして日曜、一行が行こうと私の手を取ったその場所へ、私は泣きながら向かうことになった。
死ぬまで私は、決してこの日を忘れる事はないだろう。
そしてそれから、離れようとしている恋人に、してあげられる事は何だろうと、ずっと答えを探している。
早朝、太陽がまた美しく輝く時、眩しそうに手をかざして、指の隙間からこぼれる陽射しに顔を預けている。
私は 空港に向かっている。
震えているのは朝露のせいだ。
右手にはパスポートが握られている。
緊張気味に写った写真に向かって、しっかりしろと拳を作る。
パスポートには
「鈴木麗子」
と 書いてある。