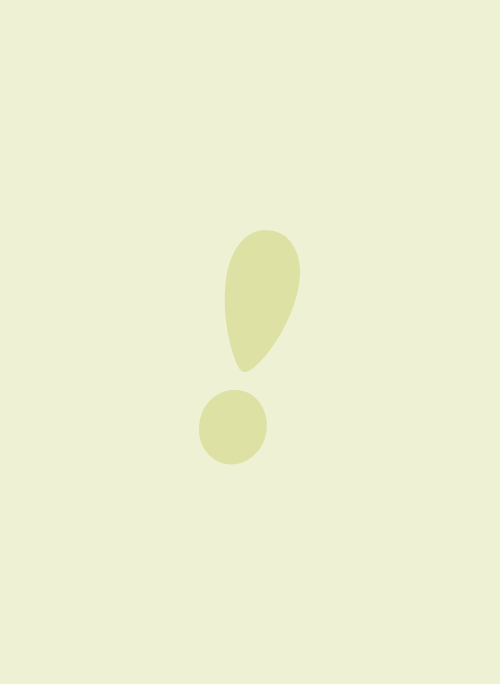お酒でフラフラした上に、若い男性にクラクラするとは、この歳にして初めての経験である。
ただ もちろん "恋" などというものなどとは違い、おそらく韓流スターにうっとりする奥様たちは、こんな気持ちなのかと想像させる、そんなものである。
私だってそこまで図々しくはない。
身の程ってものの尺度は、ここまで独り身で生きて来た大人の女には、すぐ判断してしまう力がすでに身についている。
それにしても良くできている。
勇気を出して
「綺麗な顔してるね」
と言ってみた。
「キライなんですよ、この顔。
コンプレックスです。」
なるほど、本人にしてみたら顔の話題ばかりでうんざりなのかもしれない。
「一行、あんたの顔、貸してあげれば。」
「いやっすよ。
この顔でモテモテっすよ。
今よりもててどうするんすか。
涼と何処か違ってるっすか?」
「全部よ、全部。
一から千まで。」
「千すか。
百くらいにしといて下さいよ」
一行と涼が親友だというのが、解る気がする。
私の緊張も和らぎ、 "涼くんは" なんて言えるようになり、いつの間にか私の方が質問される立場になっていた。
「なんで結婚しないんですか?」
「ストレートにまぁ。
そんなこと聞くの一行ぐらいよ。」
なんだか気持ち良かった。
気を使われて、会社では触れてはいけない禁句のようになっていたその壁を、新人があっさり蹴破ってくれた。
「なんでかなぁ。
魅力が無かったからかなぁ。」
「魅力ありますよ。」
「涼がそんな事いうの珍しいな。」
ドキドキしている。
幸い、お店の暗さが、赤面しているのを隠してくれているからいいものの、どんな対応をしたら良いものか、どこの引き出しを探しても当てはまるものは見付からない。
「仕事も楽しかったしね。」
独身でいることの焦りは、跡継ぎの正幸さんも同じだと、『せっぱつまった会』を作ろうと大笑いした。
と言うことは、お互いその気がないと云うことだと、また笑った。
「麗子さんは休みの日は何してるんですか?」
ただ もちろん "恋" などというものなどとは違い、おそらく韓流スターにうっとりする奥様たちは、こんな気持ちなのかと想像させる、そんなものである。
私だってそこまで図々しくはない。
身の程ってものの尺度は、ここまで独り身で生きて来た大人の女には、すぐ判断してしまう力がすでに身についている。
それにしても良くできている。
勇気を出して
「綺麗な顔してるね」
と言ってみた。
「キライなんですよ、この顔。
コンプレックスです。」
なるほど、本人にしてみたら顔の話題ばかりでうんざりなのかもしれない。
「一行、あんたの顔、貸してあげれば。」
「いやっすよ。
この顔でモテモテっすよ。
今よりもててどうするんすか。
涼と何処か違ってるっすか?」
「全部よ、全部。
一から千まで。」
「千すか。
百くらいにしといて下さいよ」
一行と涼が親友だというのが、解る気がする。
私の緊張も和らぎ、 "涼くんは" なんて言えるようになり、いつの間にか私の方が質問される立場になっていた。
「なんで結婚しないんですか?」
「ストレートにまぁ。
そんなこと聞くの一行ぐらいよ。」
なんだか気持ち良かった。
気を使われて、会社では触れてはいけない禁句のようになっていたその壁を、新人があっさり蹴破ってくれた。
「なんでかなぁ。
魅力が無かったからかなぁ。」
「魅力ありますよ。」
「涼がそんな事いうの珍しいな。」
ドキドキしている。
幸い、お店の暗さが、赤面しているのを隠してくれているからいいものの、どんな対応をしたら良いものか、どこの引き出しを探しても当てはまるものは見付からない。
「仕事も楽しかったしね。」
独身でいることの焦りは、跡継ぎの正幸さんも同じだと、『せっぱつまった会』を作ろうと大笑いした。
と言うことは、お互いその気がないと云うことだと、また笑った。
「麗子さんは休みの日は何してるんですか?」