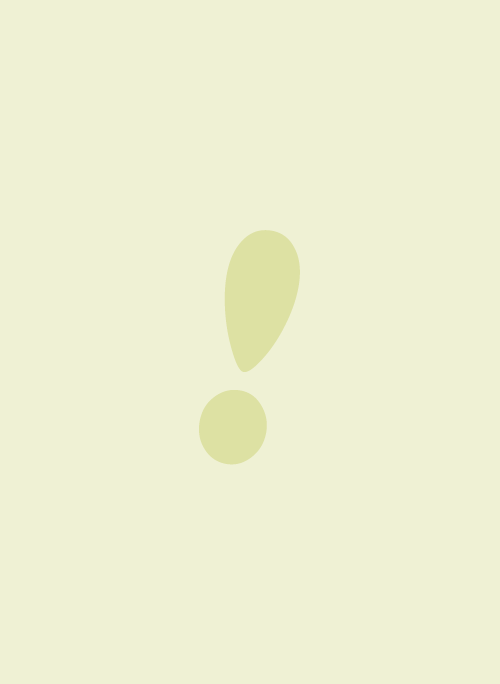一行が自信がないと言った時、私は迷わず
「仕事はみんな、はっきりとした始まりがあるのよ。
一行ならやっていけるわ。」
そう言った。
「そうじゃないんだ。
麗ちゃんのことだよ。
自信がないのは、二人の事だよ。
俺の気持ちじゃなくてさ、麗ちゃんの気持ちが、ここでずっと変わらずにやって行けるのかなって。
誘惑されないように出来る?
でも麗ちゃんは、一人が好きだからさ、それも心配だし。」
胸がつぶされて、痛い。
私は決めたはずだ。
社会に出たばかりの青年の、輝いた将来を想う時、たとえ離れた場所からでもサポートする方法はあるのだと。
「一行、大阪にはいつまで行く事になるの?」
「二週間後」
たったの二週間で、おはようと微笑む朝はやって来なくなる。
その間、何度か大阪に出向き、仕事だけではなく、生活の準備もしなくてはならないだろう。
「私の所には少し前に知らせが来てたけど、どうしても言えなかったの。
ごめんね。」
「麗ちゃん、今すぐじゃないよ。
今すぐじゃないけど、大阪勤務希望とか、無理なのかな。
会社はOK出さないかな。」
「どうだろう。
ご承知の通り、結構重要な位置にいるもので。」
希望とか、あきらめとか、急に訪れる出来事に、私だけの考えで突っ走る事はもうしない。
だけど一行、私もそんな風にキャリアを積んで来たのよ。
あなたが認めてくれた今の私は、長い年月が育ててくれたもの。
あなたはまだ、始まったばかり。
「あの彼女のことだけど、パーティの時に麗ちゃんの事見たらしくて、もう連絡しないって言ってた。
驚いてたよ。
上司っていうから、目のつり上がった怖い人を想像してたって。
悪い事したってさ。」
「涼くんといたから分かったのね。
じゃぁ、私も一行と歩いてる所見かけたし、おあいこだ。」
あの日捨ててしまった涼からのメールは、私への激励だったのかもしれない。
きっとそうだと信じよう。
「仕事はみんな、はっきりとした始まりがあるのよ。
一行ならやっていけるわ。」
そう言った。
「そうじゃないんだ。
麗ちゃんのことだよ。
自信がないのは、二人の事だよ。
俺の気持ちじゃなくてさ、麗ちゃんの気持ちが、ここでずっと変わらずにやって行けるのかなって。
誘惑されないように出来る?
でも麗ちゃんは、一人が好きだからさ、それも心配だし。」
胸がつぶされて、痛い。
私は決めたはずだ。
社会に出たばかりの青年の、輝いた将来を想う時、たとえ離れた場所からでもサポートする方法はあるのだと。
「一行、大阪にはいつまで行く事になるの?」
「二週間後」
たったの二週間で、おはようと微笑む朝はやって来なくなる。
その間、何度か大阪に出向き、仕事だけではなく、生活の準備もしなくてはならないだろう。
「私の所には少し前に知らせが来てたけど、どうしても言えなかったの。
ごめんね。」
「麗ちゃん、今すぐじゃないよ。
今すぐじゃないけど、大阪勤務希望とか、無理なのかな。
会社はOK出さないかな。」
「どうだろう。
ご承知の通り、結構重要な位置にいるもので。」
希望とか、あきらめとか、急に訪れる出来事に、私だけの考えで突っ走る事はもうしない。
だけど一行、私もそんな風にキャリアを積んで来たのよ。
あなたが認めてくれた今の私は、長い年月が育ててくれたもの。
あなたはまだ、始まったばかり。
「あの彼女のことだけど、パーティの時に麗ちゃんの事見たらしくて、もう連絡しないって言ってた。
驚いてたよ。
上司っていうから、目のつり上がった怖い人を想像してたって。
悪い事したってさ。」
「涼くんといたから分かったのね。
じゃぁ、私も一行と歩いてる所見かけたし、おあいこだ。」
あの日捨ててしまった涼からのメールは、私への激励だったのかもしれない。
きっとそうだと信じよう。