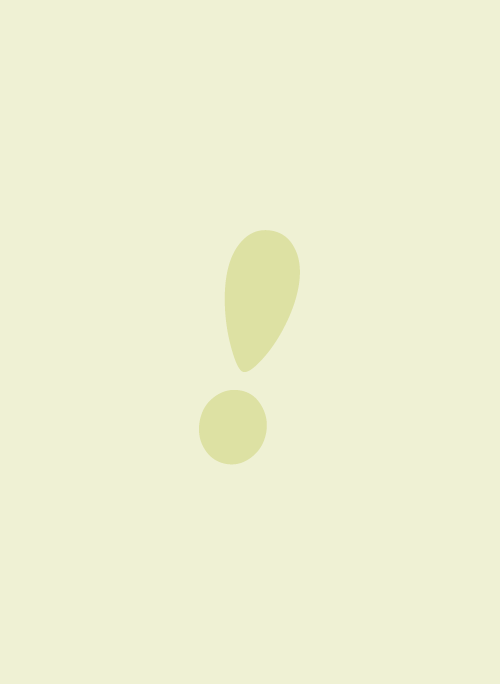ジャニーズ系も真っ青なほど、キラキラ美しい青年は、やはり今年社会人になったばかりの今時の若者だった。
今日は親友の付き合いで顔を出したに違いない。
だって、何もこんな所へ出向かなくても、引くてあまただろうに。
現に他の男性は、私以外の女子が彼のそばに移動したことにショックを隠せない。
こんな時、欣也さん、いや、本当は正幸さんというらしい彼達に声をかける役目は私しかいない。
母親のようだ。
私だってそのキラキラに吸い込まれそうだったけど、流石に駆け寄る勇気は持ちあわせていなかった。
今までの免疫があまりに乏しく、応用のきかない四十前の女は、仕事の話で場を持たせるしかないのだ。
でも、「っす」しか言えないと思っていた新人は、ちゃんと夢を持ち未来を語り、もう一人の友人も正幸さんも家業の跡継ぎだと、熱く語るのを聞くことはとても新鮮なことだった。
時々、チラっと目をやると、彼女たちには申し訳ないが、まるでキャバクラ状態に彼は困り果てていた。
「あいつ"涼"って名前なんすけど、ホストみたいっすよね。
いつもこんな感じっす。」
もはや、我々は同士となり、男とか女とかを越えた、ちょっとイイ感じの時間を過ごしていた。
合コンってのも悪くない。
意気込んでお洒落しなくても、素敵な夜を過ごせるじゃないの。
「おい新人!」
「鈴木一行っすよ。」
「銀行の見本みたいな名前だよね」
「先輩の市川麗子ってのも期待させる名前っすよ。」
「悪かったわね。
期待にそえなくて。」
まぁ今日は帰り際に挨拶でもして、"涼"さんのことは諦めよう。
「何の話?」
うわっ!
キラキラが隣に来た。
「涼、この人が例の先輩」
例のってなによ。
ここに来る前から私を知ってたってこと?
「研修の話で、先輩のこと話してたんすよ。」
ニコッとするだけで、ふぬけになりそうだ。
「は・は・はじめまして」
今日は親友の付き合いで顔を出したに違いない。
だって、何もこんな所へ出向かなくても、引くてあまただろうに。
現に他の男性は、私以外の女子が彼のそばに移動したことにショックを隠せない。
こんな時、欣也さん、いや、本当は正幸さんというらしい彼達に声をかける役目は私しかいない。
母親のようだ。
私だってそのキラキラに吸い込まれそうだったけど、流石に駆け寄る勇気は持ちあわせていなかった。
今までの免疫があまりに乏しく、応用のきかない四十前の女は、仕事の話で場を持たせるしかないのだ。
でも、「っす」しか言えないと思っていた新人は、ちゃんと夢を持ち未来を語り、もう一人の友人も正幸さんも家業の跡継ぎだと、熱く語るのを聞くことはとても新鮮なことだった。
時々、チラっと目をやると、彼女たちには申し訳ないが、まるでキャバクラ状態に彼は困り果てていた。
「あいつ"涼"って名前なんすけど、ホストみたいっすよね。
いつもこんな感じっす。」
もはや、我々は同士となり、男とか女とかを越えた、ちょっとイイ感じの時間を過ごしていた。
合コンってのも悪くない。
意気込んでお洒落しなくても、素敵な夜を過ごせるじゃないの。
「おい新人!」
「鈴木一行っすよ。」
「銀行の見本みたいな名前だよね」
「先輩の市川麗子ってのも期待させる名前っすよ。」
「悪かったわね。
期待にそえなくて。」
まぁ今日は帰り際に挨拶でもして、"涼"さんのことは諦めよう。
「何の話?」
うわっ!
キラキラが隣に来た。
「涼、この人が例の先輩」
例のってなによ。
ここに来る前から私を知ってたってこと?
「研修の話で、先輩のこと話してたんすよ。」
ニコッとするだけで、ふぬけになりそうだ。
「は・は・はじめまして」