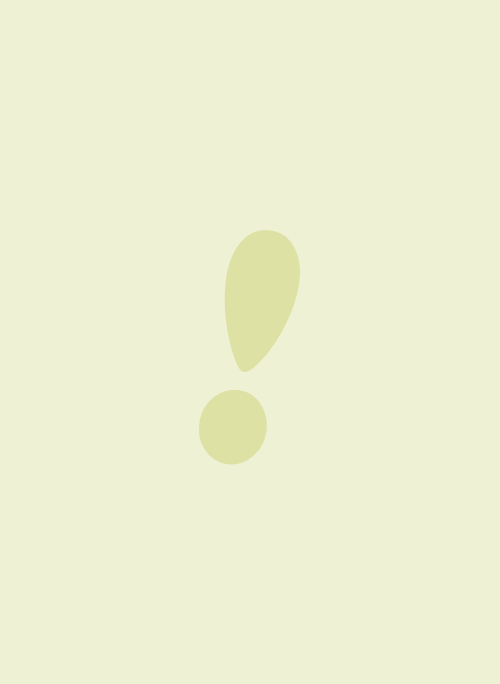早朝、行くあてもなく電車に乗り、人気のない休日の静けさの中にいる。
中刷り広告で
“アンコールワット展”
の告知を見つけた。
いつか行こうと決めている憧れの地。
美術館なんて思い出せないほど訪れていないけど、このまま足を運んでみようか。
温泉の代わりになどならない事は何をとっても明解だけれど、じっとしているとどうにかなってしまいそうだ。
本当は怖くて怖くてたまらない。
素直に気持ちをぶつければ良かったのかと、ずっと迷っているけれど、答えがゼロになるような気持ちの良い割り切りは出来そうにはない。
朝方、
“こんな時涼なら、話を聞いてくれるだろうか”
と、想い巡らせている私がいた。
だけど、こんな時だからこそ声をかけてはいけないのだ。
私は涼を選ばず、涼を愛さず、涼の人生に踏み込む事を私の人生から除いたのだ。
涼にすがるのは、私のすべき事ではない。
私の訴えが涼の耳を汚すのは、もう一つの罪を創り出す事になる。
一行はあれからどうしただろう。
私の嘘は、逆に一行の気持ちを傷つけてしまったかもしれない。
引き止めなかった一行を待っていた、もう一人の私。
薄い意識のまま美術館の前に来てしまった。
休日の人混みは、容赦なく孤独と云う現実を押し付け、息苦しささえもプラスさせて来る。
入り口のロビーに腰掛け、展示場の中に吸い込まれて行く人々を眺めなから、本当ならこんな風に出かけていたはずだった姿を想像していた。
一緒に暮らし始めて、一行の為に私が出来た事はなんだろう。
仕事という理由付けで、私本意の日々になってはいなかったのか。
せっかくの“アンコールワット展”も、中に入る気持ちになれずに時間だけが過ぎて行く。
一行がくれた私に対するひたむきな想いを、私はあまりにも簡単に、置き去りにしてしまったのかもしれない。
まだ間に合うなら、時間を戻す勢いを、私の願いで動かせはしないだろうか。
「一行?
今どこ?」
「麗ちゃんこそ、どこにいるんだよ。」
「美術館。」
中刷り広告で
“アンコールワット展”
の告知を見つけた。
いつか行こうと決めている憧れの地。
美術館なんて思い出せないほど訪れていないけど、このまま足を運んでみようか。
温泉の代わりになどならない事は何をとっても明解だけれど、じっとしているとどうにかなってしまいそうだ。
本当は怖くて怖くてたまらない。
素直に気持ちをぶつければ良かったのかと、ずっと迷っているけれど、答えがゼロになるような気持ちの良い割り切りは出来そうにはない。
朝方、
“こんな時涼なら、話を聞いてくれるだろうか”
と、想い巡らせている私がいた。
だけど、こんな時だからこそ声をかけてはいけないのだ。
私は涼を選ばず、涼を愛さず、涼の人生に踏み込む事を私の人生から除いたのだ。
涼にすがるのは、私のすべき事ではない。
私の訴えが涼の耳を汚すのは、もう一つの罪を創り出す事になる。
一行はあれからどうしただろう。
私の嘘は、逆に一行の気持ちを傷つけてしまったかもしれない。
引き止めなかった一行を待っていた、もう一人の私。
薄い意識のまま美術館の前に来てしまった。
休日の人混みは、容赦なく孤独と云う現実を押し付け、息苦しささえもプラスさせて来る。
入り口のロビーに腰掛け、展示場の中に吸い込まれて行く人々を眺めなから、本当ならこんな風に出かけていたはずだった姿を想像していた。
一緒に暮らし始めて、一行の為に私が出来た事はなんだろう。
仕事という理由付けで、私本意の日々になってはいなかったのか。
せっかくの“アンコールワット展”も、中に入る気持ちになれずに時間だけが過ぎて行く。
一行がくれた私に対するひたむきな想いを、私はあまりにも簡単に、置き去りにしてしまったのかもしれない。
まだ間に合うなら、時間を戻す勢いを、私の願いで動かせはしないだろうか。
「一行?
今どこ?」
「麗ちゃんこそ、どこにいるんだよ。」
「美術館。」