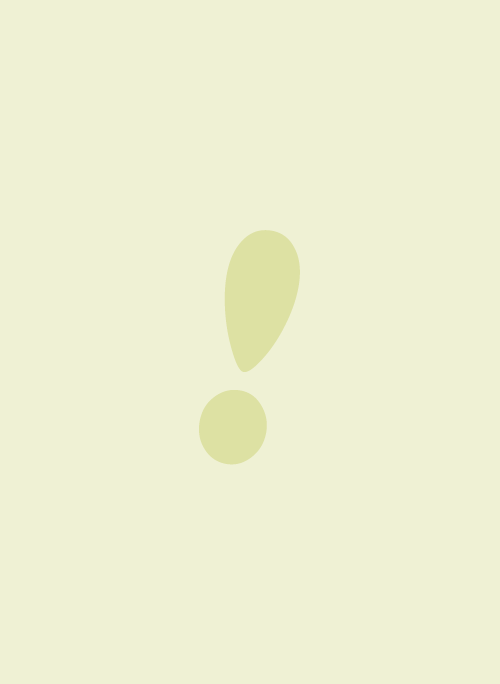「遅くなったけど、ケーキ食べようよ。」
歳が増えたとたんに、余計な引っ掛かりも増えた気がしている。
「ケーキ入刀なんてしてみたりして。
麗ちゃん、ここ持ってみる?」
一行はこういう事を、楽しそうにやってしまうけど、私には結構ドキドキするシーンだということに、気が付かないものなの?
何をするにも、ニュートラルに戻る余裕のある感覚を忘れずに来たつもりだけど、私の履歴を書き換えるくらいの何かが迫ってくる気がするのは、考え過ぎだろうか。
人生の“のりしろ”のような、余分ではない大切な役割を持つ宝を、たくさん持っていたはずなのに、今の私はなんて気弱なんだろう。
一行がきっと恥ずかしげにバースデーケーキを頼んでいただろう姿を思い浮かべれば、そんな憶測も吹き飛ぶといったとこだけど。
今日は、多すぎるロウソクでカットしにくいケーキを二人で味わいながら、面倒な話しはやめて、穏やかな一日を始めなくちゃ。
「麗ちゃん、プレゼントがあります。」
「なに? なに?」
「涼にそんなのもらっちゃって、出しにくいなぁ」
「なに?
ダイヤモンド?
マンション?」
「あたり!
んなわけないでしょ。
俺の給料知ってるくせに。」
一行が差し出したものは、封筒だった。
「ラブレター?」
「そうとも言えるけど、早く開けてみて。」
中には、温泉ホテルと観光スポットのパンフレットが入っていた。
「次の週末、予約したから。」
そのうち行きたいねと、話したばかりだった休暇を、ちゃんと現実にしてくれるなんて、こういうプレゼントは考えてもいなかった。
「また泣いてもいい?」
「どうぞ、何回でも。」
一行が優しい事を、私は充分に知っているつもりである。
だから、元カノのことをどうこう言う前に、私の心が正直に一行に向かい、愛していく事が重要なんだと云う事を、もう一度ちゃんと思い返してみよう。
「のんびりをプレゼントです。
行けるでしょ。
美味しいもの食べに行こうよ。」
歳が増えたとたんに、余計な引っ掛かりも増えた気がしている。
「ケーキ入刀なんてしてみたりして。
麗ちゃん、ここ持ってみる?」
一行はこういう事を、楽しそうにやってしまうけど、私には結構ドキドキするシーンだということに、気が付かないものなの?
何をするにも、ニュートラルに戻る余裕のある感覚を忘れずに来たつもりだけど、私の履歴を書き換えるくらいの何かが迫ってくる気がするのは、考え過ぎだろうか。
人生の“のりしろ”のような、余分ではない大切な役割を持つ宝を、たくさん持っていたはずなのに、今の私はなんて気弱なんだろう。
一行がきっと恥ずかしげにバースデーケーキを頼んでいただろう姿を思い浮かべれば、そんな憶測も吹き飛ぶといったとこだけど。
今日は、多すぎるロウソクでカットしにくいケーキを二人で味わいながら、面倒な話しはやめて、穏やかな一日を始めなくちゃ。
「麗ちゃん、プレゼントがあります。」
「なに? なに?」
「涼にそんなのもらっちゃって、出しにくいなぁ」
「なに?
ダイヤモンド?
マンション?」
「あたり!
んなわけないでしょ。
俺の給料知ってるくせに。」
一行が差し出したものは、封筒だった。
「ラブレター?」
「そうとも言えるけど、早く開けてみて。」
中には、温泉ホテルと観光スポットのパンフレットが入っていた。
「次の週末、予約したから。」
そのうち行きたいねと、話したばかりだった休暇を、ちゃんと現実にしてくれるなんて、こういうプレゼントは考えてもいなかった。
「また泣いてもいい?」
「どうぞ、何回でも。」
一行が優しい事を、私は充分に知っているつもりである。
だから、元カノのことをどうこう言う前に、私の心が正直に一行に向かい、愛していく事が重要なんだと云う事を、もう一度ちゃんと思い返してみよう。
「のんびりをプレゼントです。
行けるでしょ。
美味しいもの食べに行こうよ。」