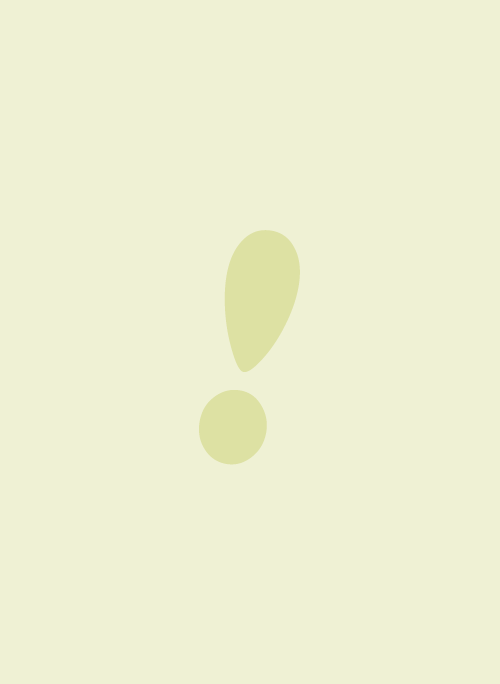筋書きを書いて、未来を決定出来るとしたら、それは思い通りの幸福を手に入れる事につながる道を、迷いも無く行く、尊い事なんだろうか。
だけどやっぱり、先の解らない毎日の、期待と不安の中で暮らす生き方を誰もが選ぶだろう。
明日を知らないでいることが、夢見ると言うことなんだから。
私の今までは、思い通りにならないことでも、きっとうまく行くと信じて乗り越えようとしてきた日々の、繰り返しだったような気がする。
一行が語ろうとしている事が、私の頑張りではどうしようもない事実なら、その時はいさぎの良い、女っぷりを演じるしかないんだろう。
だけど、そんな事を演じても、一行にはすぐ見破られてしまうだろうけど。
「この間、遅くに帰った日があったでしょ。
あの時のこと。」
「私はあのバーで、ひとりで飲んでたんだよ。」
「知らなかったなぁ。
涼に聞くまで、ここに居たと思ってた。
涼は何度もあの店に行ってたって言ってた。
偶然に会える場所は、あの店しか知らないからって。
涼がそこまでマジだったって、さっき話しててびっくりしたよ。
麗ちゃん、迷ってるんじゃないの?」
「涼くんのこと?」
「俺の知らない事って、もっとあるの?」
元カノの話じゃないの?
と思ったけど
「初めての合コンの日に、メールが来たのね。
それからは、何度か電話やメールが来たりしたかな。
それだけよ。」
「ふぅ~ん。
好きとか、付き合ってとか、そういうやつ?
でもさ、どうして言わなかったの?」
「だって、その時一行は彼氏じゃなかったよ。
正直、私も涼くんに興味あったしね。
好きとか言うんじゃなくて、あんな綺麗な男性、見たことなかったもん。
疑ってるの?」
一行は下を向いたまま、少し考えていたけど、何かふっきれた様子で話はじめた。
「麗ちゃん、学生の時バンドやってたって話したよね。
その時のドラムの奴が今度結婚することになって、レストランでパーティすることになったんだよね。
そこで演奏することになってさ、その打ち合わせだったんだ。
だけどやっぱり、先の解らない毎日の、期待と不安の中で暮らす生き方を誰もが選ぶだろう。
明日を知らないでいることが、夢見ると言うことなんだから。
私の今までは、思い通りにならないことでも、きっとうまく行くと信じて乗り越えようとしてきた日々の、繰り返しだったような気がする。
一行が語ろうとしている事が、私の頑張りではどうしようもない事実なら、その時はいさぎの良い、女っぷりを演じるしかないんだろう。
だけど、そんな事を演じても、一行にはすぐ見破られてしまうだろうけど。
「この間、遅くに帰った日があったでしょ。
あの時のこと。」
「私はあのバーで、ひとりで飲んでたんだよ。」
「知らなかったなぁ。
涼に聞くまで、ここに居たと思ってた。
涼は何度もあの店に行ってたって言ってた。
偶然に会える場所は、あの店しか知らないからって。
涼がそこまでマジだったって、さっき話しててびっくりしたよ。
麗ちゃん、迷ってるんじゃないの?」
「涼くんのこと?」
「俺の知らない事って、もっとあるの?」
元カノの話じゃないの?
と思ったけど
「初めての合コンの日に、メールが来たのね。
それからは、何度か電話やメールが来たりしたかな。
それだけよ。」
「ふぅ~ん。
好きとか、付き合ってとか、そういうやつ?
でもさ、どうして言わなかったの?」
「だって、その時一行は彼氏じゃなかったよ。
正直、私も涼くんに興味あったしね。
好きとか言うんじゃなくて、あんな綺麗な男性、見たことなかったもん。
疑ってるの?」
一行は下を向いたまま、少し考えていたけど、何かふっきれた様子で話はじめた。
「麗ちゃん、学生の時バンドやってたって話したよね。
その時のドラムの奴が今度結婚することになって、レストランでパーティすることになったんだよね。
そこで演奏することになってさ、その打ち合わせだったんだ。