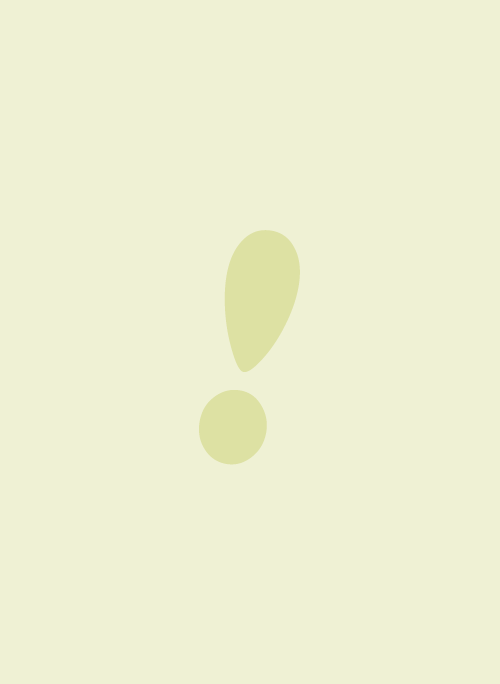「俺はいつも二番目だった気がします。
一行は意識してないけど、勝手にトップ走って、苦しい顔ひとつ見せないでいるんです。
俺には真似が出来ない。
近くにいるだけに、それがよく解るんです。」
「そうだね。
一行はいつも自然体だよね。
肩の力がいい感じに抜けてる。」
涼は私に恋したわけではなく、一行が選んだ私に憧れているんだろうと私は思った。
「涼くんは、私が好き?」
「好きですよ、すごく。」
「どんな所が?」
「どんな所って、うまく言えないけど。」
「言えないって事はそれほどじゃないって事だと思うよ。
一行が私の事を嫌いになっても、涼くんのことは愛せないと思う。
一行にフラレたからって、次は涼くんの番って話じゃないでしょ。」
「待ってようかなぁ。」
「うわっ、ひどい。
フラレると思ってるのね。」
こんな風に笑い合いたかったのよ と心で思いながら、このままひとりに戻ることにした。
「涼くん、今度は一行も一緒にね。
離れていっちゃ嫌だよ。
いい?
わかった?
これは、希望じゃなく、お願いになっちゃうのかな。」
「はい」
「聞こえないなぁ。」
「麗子さん、一行と会う前に俺と出会っていたら、どうなっていたと思いますか?」
「一行と会っていなくても、私は私よ。
“もし”は過去の話でしょ。
過去の心配はしない事にしたの。
一行が元カノと会っていたのは事実だろうけど、一行の事、信頼してるの。
たまたま見ちゃったけどね。
一行と会わなければ、涼くんとも会ってないよ、きっと。」
「麗子さん、明日誕生日でしょ。
初めて会った時、生まれた年は言わなかったけど、月日だけは教えてくれた。」
「年もバレバレ」
「最初で最後のプレゼント」
と、涼は綺麗にラッピングされた箱をくれた。
「フラレっぷりはいいんです。
お誕生日おめでとう」
そう言うと、
涼は走って私の前からいなくなった。
一行は意識してないけど、勝手にトップ走って、苦しい顔ひとつ見せないでいるんです。
俺には真似が出来ない。
近くにいるだけに、それがよく解るんです。」
「そうだね。
一行はいつも自然体だよね。
肩の力がいい感じに抜けてる。」
涼は私に恋したわけではなく、一行が選んだ私に憧れているんだろうと私は思った。
「涼くんは、私が好き?」
「好きですよ、すごく。」
「どんな所が?」
「どんな所って、うまく言えないけど。」
「言えないって事はそれほどじゃないって事だと思うよ。
一行が私の事を嫌いになっても、涼くんのことは愛せないと思う。
一行にフラレたからって、次は涼くんの番って話じゃないでしょ。」
「待ってようかなぁ。」
「うわっ、ひどい。
フラレると思ってるのね。」
こんな風に笑い合いたかったのよ と心で思いながら、このままひとりに戻ることにした。
「涼くん、今度は一行も一緒にね。
離れていっちゃ嫌だよ。
いい?
わかった?
これは、希望じゃなく、お願いになっちゃうのかな。」
「はい」
「聞こえないなぁ。」
「麗子さん、一行と会う前に俺と出会っていたら、どうなっていたと思いますか?」
「一行と会っていなくても、私は私よ。
“もし”は過去の話でしょ。
過去の心配はしない事にしたの。
一行が元カノと会っていたのは事実だろうけど、一行の事、信頼してるの。
たまたま見ちゃったけどね。
一行と会わなければ、涼くんとも会ってないよ、きっと。」
「麗子さん、明日誕生日でしょ。
初めて会った時、生まれた年は言わなかったけど、月日だけは教えてくれた。」
「年もバレバレ」
「最初で最後のプレゼント」
と、涼は綺麗にラッピングされた箱をくれた。
「フラレっぷりはいいんです。
お誕生日おめでとう」
そう言うと、
涼は走って私の前からいなくなった。