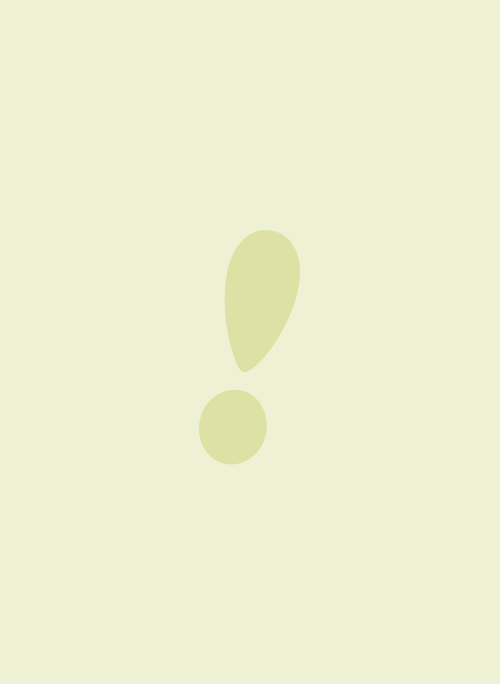涼がいないことで、女の子達は物足りなさげで、やはりつまらなそうである。
連絡も入らないのは、何か急用でも出来たのだろうか。
こんな風に、一人抜けまた一人抜け、フェイドアウトしていくというのは仕方のない事なんだろう。
寂しいけど。
一行と涼の仲が、どんな付き合いになっているのか、私は聞いていない。
もちろん、私から涼に連絡を入れる事はなく、今だって、涼が私の事を好きでいたなんて思ってはいない。
本音を言えば、そう自分に言い聞かせている。
電話やメールのやりとりを考えれば、私にだって思い込みだけでは片付けられない、感じるものがあった。
だけど、何も起きはしなかった。
一行が私を選んだように、私も一行を選んだ、それが全てである。
一行は仕事帰りに私のマンションへ寄り、そのまま泊まる事もあれば、帰る日もあり、面倒だからここに引っ越して、一緒に暮らそうと話している。
それがどういう問題を引き起こしても、今は心配することなど止めておこう。
今日は珍しく、学生時代の仲間達との集まりがあり、ここへは寄れないとメールが入った。
涼も一緒だろうかと考えたけど、聞くのはやめた。
一行が隣にいないのは、ぬるいコーヒーを飲んでるようで、何か気の抜けたようでもあるけど、久々に、バリバリのキャリアウーマンは、一人で飲みに行く事を選ぶのである。
一行と行ったっきり、あのバーのドアは開けていない。
今日はゆっくり色々考えるのもいいかもしれない。
少しお洒落して、化粧も直しドアを開けた。
まだ時間が早いのか、私が一番の客のようだ。
「いらっしゃいませ。
お久しぶりですね。」
馴染みのバーテンさんが微笑んでいる。
「本当に。
バナナダイキリ」
「かしこまりました。」
気のきいた大人は余計な事を言わない。
読みかけの本を眺めながら、ここ何ヶ月かの出来事を振り返っていた。
自分を変えようと心に決めて、それから出会った人々との関わり。
連絡も入らないのは、何か急用でも出来たのだろうか。
こんな風に、一人抜けまた一人抜け、フェイドアウトしていくというのは仕方のない事なんだろう。
寂しいけど。
一行と涼の仲が、どんな付き合いになっているのか、私は聞いていない。
もちろん、私から涼に連絡を入れる事はなく、今だって、涼が私の事を好きでいたなんて思ってはいない。
本音を言えば、そう自分に言い聞かせている。
電話やメールのやりとりを考えれば、私にだって思い込みだけでは片付けられない、感じるものがあった。
だけど、何も起きはしなかった。
一行が私を選んだように、私も一行を選んだ、それが全てである。
一行は仕事帰りに私のマンションへ寄り、そのまま泊まる事もあれば、帰る日もあり、面倒だからここに引っ越して、一緒に暮らそうと話している。
それがどういう問題を引き起こしても、今は心配することなど止めておこう。
今日は珍しく、学生時代の仲間達との集まりがあり、ここへは寄れないとメールが入った。
涼も一緒だろうかと考えたけど、聞くのはやめた。
一行が隣にいないのは、ぬるいコーヒーを飲んでるようで、何か気の抜けたようでもあるけど、久々に、バリバリのキャリアウーマンは、一人で飲みに行く事を選ぶのである。
一行と行ったっきり、あのバーのドアは開けていない。
今日はゆっくり色々考えるのもいいかもしれない。
少しお洒落して、化粧も直しドアを開けた。
まだ時間が早いのか、私が一番の客のようだ。
「いらっしゃいませ。
お久しぶりですね。」
馴染みのバーテンさんが微笑んでいる。
「本当に。
バナナダイキリ」
「かしこまりました。」
気のきいた大人は余計な事を言わない。
読みかけの本を眺めながら、ここ何ヶ月かの出来事を振り返っていた。
自分を変えようと心に決めて、それから出会った人々との関わり。