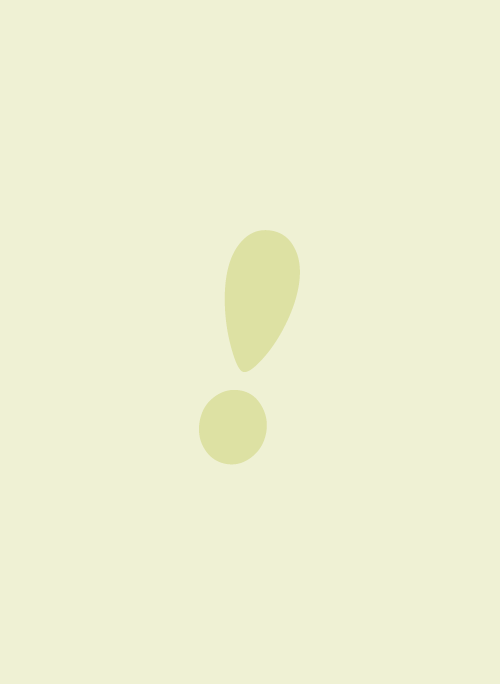一行と手をつなぎ、何も話さず、ずっと歩いた。
何か言うと放してしまいそうな指は、今はとても大切な秘密のようなもの。
「先輩、嫌じゃないですか。」
「嫌じゃないよ。」
「もう少しこのままでいいですか。」
「いいよ。」
一行、私はとっくに気付いていたよ。
はじめから、私を見つめてくれていたこと。
私だって踏ん張っていたんだよ。
気付かないふりをして、仕事仲間のままなら、一行にはその方が意味のある生き方が出来るんじゃないかって。
本気で誰かを愛する事をあんなに待ち望んでいたはずなのに、なぜこんなに切ないの。
なぜ飛込めないのって。
「一行、私ね、どうしていいか解らないの。」
「俺と涼のことですか?」
「違う。
一行は勘違いしてるよ。
涼くんは私のことなんか、何とも思ってないよ。
プレゼント選びながら、何度も一行をよろしくって頭下げられた。
涼くんのこと、一番解っているのは一行でしょう。」
「あぁ、そうかぁ。
俺は駄目だなぁ。
小さい男だなぁ。
先輩に嫌われちゃうかな。」
「私のそばにいること自体、もうずいぶん呆れてるけどね。」
「先輩を見てるとやる気が出て、仕事って楽しいものなんだって言ってる気がして、社会人になったばかりの俺には凄く頼もしかった。
こんな小さな身体の何処に、あんなエネルギーがあるのか、不思議だった。」
負け犬だのと、流行りの言葉に躍らされた昔の私は捨てたはず。
「一行、手を離すよ。」
「ごめんなさい。
やっぱり迷惑っすよね」
人生最大の告白タイムである。
爪の先まで心臓の音が響いてくるようだ。
「一行聞いて。
言うよ。
鈴木一行さん、第一印象から決めてました。
付き合ってください。
よろしくお願いします。」
右手を出し、頭を下げた。
一行は大きく目を見開き私を見つめたまま動かない。
「カッコイイなぁ。
だめ、だめ、先輩、今の撤回してください。」
えっ、死ぬほど勇気だしたのに。
何か言うと放してしまいそうな指は、今はとても大切な秘密のようなもの。
「先輩、嫌じゃないですか。」
「嫌じゃないよ。」
「もう少しこのままでいいですか。」
「いいよ。」
一行、私はとっくに気付いていたよ。
はじめから、私を見つめてくれていたこと。
私だって踏ん張っていたんだよ。
気付かないふりをして、仕事仲間のままなら、一行にはその方が意味のある生き方が出来るんじゃないかって。
本気で誰かを愛する事をあんなに待ち望んでいたはずなのに、なぜこんなに切ないの。
なぜ飛込めないのって。
「一行、私ね、どうしていいか解らないの。」
「俺と涼のことですか?」
「違う。
一行は勘違いしてるよ。
涼くんは私のことなんか、何とも思ってないよ。
プレゼント選びながら、何度も一行をよろしくって頭下げられた。
涼くんのこと、一番解っているのは一行でしょう。」
「あぁ、そうかぁ。
俺は駄目だなぁ。
小さい男だなぁ。
先輩に嫌われちゃうかな。」
「私のそばにいること自体、もうずいぶん呆れてるけどね。」
「先輩を見てるとやる気が出て、仕事って楽しいものなんだって言ってる気がして、社会人になったばかりの俺には凄く頼もしかった。
こんな小さな身体の何処に、あんなエネルギーがあるのか、不思議だった。」
負け犬だのと、流行りの言葉に躍らされた昔の私は捨てたはず。
「一行、手を離すよ。」
「ごめんなさい。
やっぱり迷惑っすよね」
人生最大の告白タイムである。
爪の先まで心臓の音が響いてくるようだ。
「一行聞いて。
言うよ。
鈴木一行さん、第一印象から決めてました。
付き合ってください。
よろしくお願いします。」
右手を出し、頭を下げた。
一行は大きく目を見開き私を見つめたまま動かない。
「カッコイイなぁ。
だめ、だめ、先輩、今の撤回してください。」
えっ、死ぬほど勇気だしたのに。