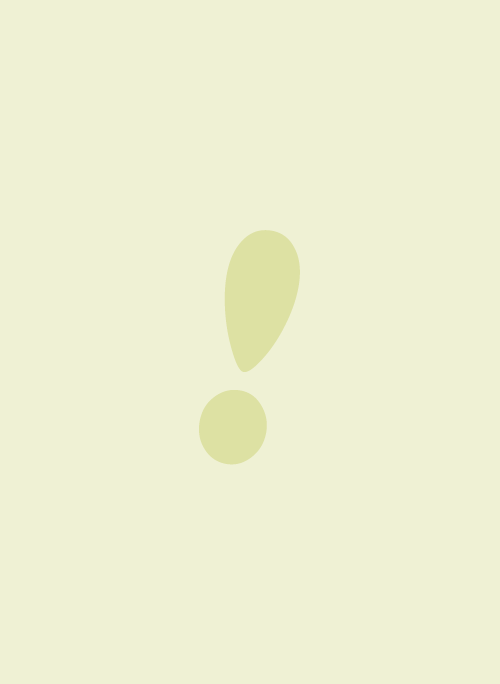私が望む私達それぞれの人生の結末が、岩沢がもたらした奇跡のような偶然と必然で、どんなサプライズを運んで来るのか、それもまた夢見るべきものなのだ。
「お墓に赤い薔薇が供えてあったのは、もしかして専務からですか?」
「そうか、飾ってくれていたか。
教会にお願いしてお参りしてもらっているのさ。
なかなか出向く事もままならないからなぁ。
私からだってどうして分かったんだ。」
「分かりますよ。
私には分かります。
あの日だって、麗子さんのお墓へ行くと言って真っ赤な薔薇を抱えていましたから。」
「そうか…
薔薇は彼女が好きだった花なんだよ。
岩沢には、またふたり一緒にいられる祝福にな。」
「専務、再来月で特修が終了しますので、日本へ帰ります。」
「聞いているよ。
頑張ったなぁ。
岩沢に見せてやりたかったなぁ。」
特修を終え日本へ戻れば、会社を興すための準備をするのに、今まで以上の決断を必然とする事柄が私の元に迫り来るだろう。
でも、生きて行く事は感謝することだと云う事を、遠いアメリカへ来て私は知った。
やってみなければ分からない、足を前へ踏み出さなくては、何処へも行けはしないのだ。
「会社へ顔を出してくれよ。
待ってるからな。」
「はい…」
足音を消して、静かに一行が横に座った。
それと同時に溢れ出た涙が声を震わせ
「専務、どうしてそんなに、人に優しく出来るんですか…
専務も岩沢さんも、私なんかに こんなに…」
一行がそっと肩を抱いた。
「誰にでも優しいんじゃないさ。
市川の夢に若い頃の自分を重ねているのかもしれないなぁ。
市川、自信を持って前進している姿を見るのは気持ちの良いものだぞ。」
久しぶりに
”市川“
と呼んだのは、独身のキャリアウーマンだったあの頃の私をずっと見て来た小池だからこそだろう。
「お墓に赤い薔薇が供えてあったのは、もしかして専務からですか?」
「そうか、飾ってくれていたか。
教会にお願いしてお参りしてもらっているのさ。
なかなか出向く事もままならないからなぁ。
私からだってどうして分かったんだ。」
「分かりますよ。
私には分かります。
あの日だって、麗子さんのお墓へ行くと言って真っ赤な薔薇を抱えていましたから。」
「そうか…
薔薇は彼女が好きだった花なんだよ。
岩沢には、またふたり一緒にいられる祝福にな。」
「専務、再来月で特修が終了しますので、日本へ帰ります。」
「聞いているよ。
頑張ったなぁ。
岩沢に見せてやりたかったなぁ。」
特修を終え日本へ戻れば、会社を興すための準備をするのに、今まで以上の決断を必然とする事柄が私の元に迫り来るだろう。
でも、生きて行く事は感謝することだと云う事を、遠いアメリカへ来て私は知った。
やってみなければ分からない、足を前へ踏み出さなくては、何処へも行けはしないのだ。
「会社へ顔を出してくれよ。
待ってるからな。」
「はい…」
足音を消して、静かに一行が横に座った。
それと同時に溢れ出た涙が声を震わせ
「専務、どうしてそんなに、人に優しく出来るんですか…
専務も岩沢さんも、私なんかに こんなに…」
一行がそっと肩を抱いた。
「誰にでも優しいんじゃないさ。
市川の夢に若い頃の自分を重ねているのかもしれないなぁ。
市川、自信を持って前進している姿を見るのは気持ちの良いものだぞ。」
久しぶりに
”市川“
と呼んだのは、独身のキャリアウーマンだったあの頃の私をずっと見て来た小池だからこそだろう。