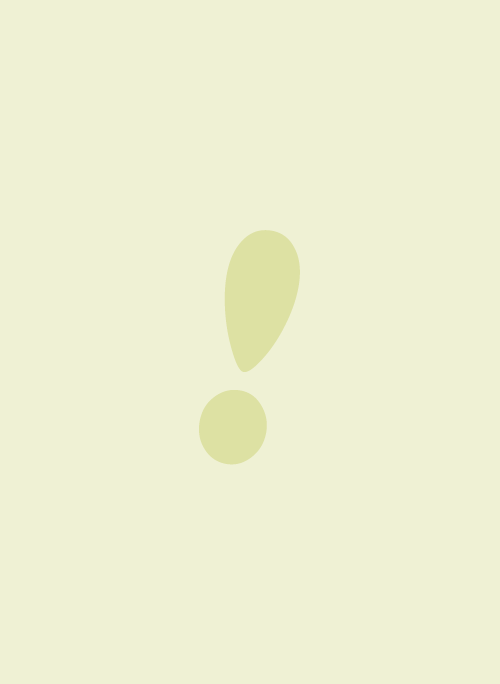「もしもし、専務ですか?
鈴木です。
鈴木麗子です。」
長旅の疲れで寝てしまった一行と、その横で幸せそうに寄り添い眠る絢の側を離れ、私は日本へ、全てを知っていたはずの専務の元へ電話をかけた。
「おぉ、元気にしていたか?」
少しおいて
「電話が来るのを待っていたよ。」
寂しくつぶやく声は、
”遅かったじゃないか“
と、私を責めるように聞こえる。
「専務、夫とふたりで息子に教会を見せて来ました。
神父様は…
岩沢さんは、長い手紙を私に残して…」
耐えきれず嗚咽した私の耳に
「あぁ、分かってる。
分かってるさ。
そうか、あいつの所へ行ってくれたか。」
と、今度は少し大きな声で
「ありがとう」
と、ゆっくり私にそう言った。
「君達には黙っていてくれとあの日岩沢に言われた約束を、私は律儀に守り通してしまったよ。
追い込みのかかった特修と、大切な出産の妨げにならないように、それが済むまでは、私にはただただ普通の日々が無事に過ぎるように祈っていてくれと、そう念を押されていたんだよ。
岩沢が神父となって最初で最後の結婚式が、今までしてきた仕事のどんな難題よりも、尊い責任と緊張感に包まれていたと言って、あいつは本当に心から喜んでいたよ。
今思えば、約束なんて破っても良かったんじゃないかと少し後悔もしている。
驚いただろう。
すまなかったなぁ。
岩沢の事、許してやってくれるか。」
岩沢と小池がこんなにも信頼しあえるのは、お互いが苦しみ悲しみを全部引き受け通り過ぎて来た長い月日と、思い通りにならないと、決して叶わないと思っていた夢が、少しずつ形を変えて認め合えるものだと云う事に気付いたからなのかもしれないと、今の私にはそう思える。
麗子と云う同じ名の隣に、二十年後の自分を重ね、まるで岩沢と小池をそこに見るように、一行と涼を想う。
鈴木です。
鈴木麗子です。」
長旅の疲れで寝てしまった一行と、その横で幸せそうに寄り添い眠る絢の側を離れ、私は日本へ、全てを知っていたはずの専務の元へ電話をかけた。
「おぉ、元気にしていたか?」
少しおいて
「電話が来るのを待っていたよ。」
寂しくつぶやく声は、
”遅かったじゃないか“
と、私を責めるように聞こえる。
「専務、夫とふたりで息子に教会を見せて来ました。
神父様は…
岩沢さんは、長い手紙を私に残して…」
耐えきれず嗚咽した私の耳に
「あぁ、分かってる。
分かってるさ。
そうか、あいつの所へ行ってくれたか。」
と、今度は少し大きな声で
「ありがとう」
と、ゆっくり私にそう言った。
「君達には黙っていてくれとあの日岩沢に言われた約束を、私は律儀に守り通してしまったよ。
追い込みのかかった特修と、大切な出産の妨げにならないように、それが済むまでは、私にはただただ普通の日々が無事に過ぎるように祈っていてくれと、そう念を押されていたんだよ。
岩沢が神父となって最初で最後の結婚式が、今までしてきた仕事のどんな難題よりも、尊い責任と緊張感に包まれていたと言って、あいつは本当に心から喜んでいたよ。
今思えば、約束なんて破っても良かったんじゃないかと少し後悔もしている。
驚いただろう。
すまなかったなぁ。
岩沢の事、許してやってくれるか。」
岩沢と小池がこんなにも信頼しあえるのは、お互いが苦しみ悲しみを全部引き受け通り過ぎて来た長い月日と、思い通りにならないと、決して叶わないと思っていた夢が、少しずつ形を変えて認め合えるものだと云う事に気付いたからなのかもしれないと、今の私にはそう思える。
麗子と云う同じ名の隣に、二十年後の自分を重ね、まるで岩沢と小池をそこに見るように、一行と涼を想う。