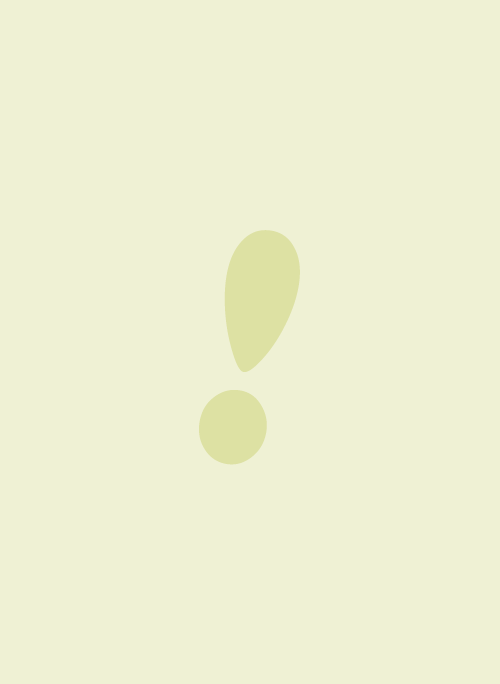岩沢の手紙の最後は、日本へ戻る私のこれからを見通しているような言葉だった。
「麗子さん、人を許すと言うことは、人を愛するという事かもしれません。
私は、二十年前に私が犯した過ちの許しを、小池君に請いました。
あなたの結婚式の日、二十年越しの気持ちのつかえを、私はやっと彼に伝える事が出来ました。
私は彼から妻を奪い、逃げるようにしてアメリカまで来たのです。
私が妻と出会う前に、彼と居たその人を、私は彼の手が届かない場所まで連れ去りました。
一度も日本へ帰らなかったのも、そうしてしまったら妻がもう二度とアメリカへ戻らないような気がして、怖くて仕方がなかったからです。
なんてずるい男だと、こんな男が神父となっていいものかと思っているかもしれませんね。
そのバチが当たって、私は最後に妻のあの言葉を聞く事になったのだと、何度も何度も自分を責めました。
でも、妻が私に宛てたあの手紙で、愛されていたのは私だったと、二十年が過ぎ、妻が亡くなった後では遅すぎると叱られそうですが、心の底からそう確信する事が出来たのです。
人を信じる心。
真っ直ぐ生きて行く力。
打ち勝って行く信念。
何もわかってはいなかった。
今、私の近い将来に起こる、やはり恐怖を感じる別れを思う時、妻を愛していたからこそ私達を許してくれた小池君を思う時…
彼がどんな痛みで、この二十年を過ごして来たのか、私には想像すら出来るものではありません。
若い過ちを詫びた私に、彼は笑って
”そんな事もあったなぁ。
昔のことさ…“
と、眩しいような瞳で天を仰ぎました。
妻が生きていたなら、きっとこんな機会は訪れなかったかもしれない。
一生会わずに、詫びもせず、人としての悔いを引きずったまま、何もなかったような顔をして、忙しく過ぎて行く日々に紛れていたでしょう。
「麗子さん、人を許すと言うことは、人を愛するという事かもしれません。
私は、二十年前に私が犯した過ちの許しを、小池君に請いました。
あなたの結婚式の日、二十年越しの気持ちのつかえを、私はやっと彼に伝える事が出来ました。
私は彼から妻を奪い、逃げるようにしてアメリカまで来たのです。
私が妻と出会う前に、彼と居たその人を、私は彼の手が届かない場所まで連れ去りました。
一度も日本へ帰らなかったのも、そうしてしまったら妻がもう二度とアメリカへ戻らないような気がして、怖くて仕方がなかったからです。
なんてずるい男だと、こんな男が神父となっていいものかと思っているかもしれませんね。
そのバチが当たって、私は最後に妻のあの言葉を聞く事になったのだと、何度も何度も自分を責めました。
でも、妻が私に宛てたあの手紙で、愛されていたのは私だったと、二十年が過ぎ、妻が亡くなった後では遅すぎると叱られそうですが、心の底からそう確信する事が出来たのです。
人を信じる心。
真っ直ぐ生きて行く力。
打ち勝って行く信念。
何もわかってはいなかった。
今、私の近い将来に起こる、やはり恐怖を感じる別れを思う時、妻を愛していたからこそ私達を許してくれた小池君を思う時…
彼がどんな痛みで、この二十年を過ごして来たのか、私には想像すら出来るものではありません。
若い過ちを詫びた私に、彼は笑って
”そんな事もあったなぁ。
昔のことさ…“
と、眩しいような瞳で天を仰ぎました。
妻が生きていたなら、きっとこんな機会は訪れなかったかもしれない。
一生会わずに、詫びもせず、人としての悔いを引きずったまま、何もなかったような顔をして、忙しく過ぎて行く日々に紛れていたでしょう。