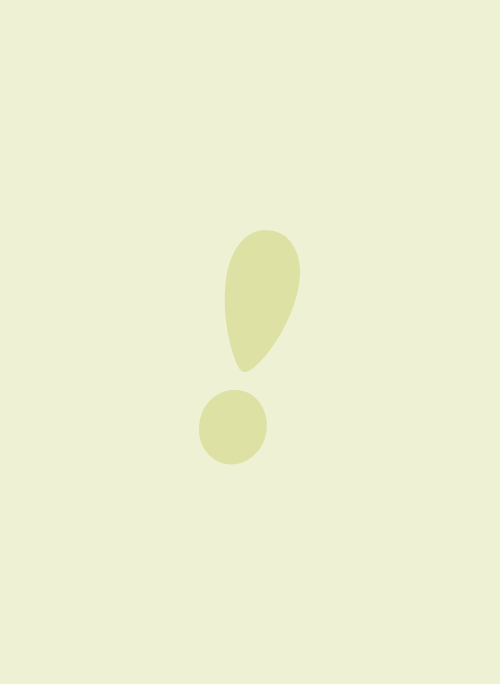みんなが集まる日、お昼に一行を誘った。
「涼くんに、ご両親へのブレゼント選び、一緒にって頼まれちゃった。
それが済んだら合流するね。」
一行には、事前に言うべきことだと思った。
おどけた返事が返って来るものとばかり思っていた。
「いつの約束ですか?
あのバーに行った時ですか?」
「そう。
メールもらって、ちょっと電話で話したかな。
なによぉ。ヤキモチ?」
「はい、ヤキモチっす。」
は? なんだ?
「一行、お昼はご馳走するわよ。
そんなヨイショしたって後はコーヒーくらいしか出ないわよ。」
顔がピクついて、うまく喋れない。
笑わない一行は、なかなか上を向かないし。
「やっぱり涼か。」
「なにがよ。
ただの買い物のお供じゃない。
特別な意味なんか何もないよ。」
まるで恋人に言い訳しているようである。
「違うんだなぁ。
涼がそんなこと頼むの、先輩だからっすよ。
まいったなぁ・・・」
よく解らない。
一行の言っている意味が。
「特別なことなの?」
「前に話したじゃないですか。
アイツは自分からは行かない奴なんすよ。」
ふぅ~ん。
でも、私が特別だとはとても思えない。
「一行、私が親に近い歳だから言いやすかったんでしょう。
一行のお母さんだって、私とそう変わらないんじゃない?」
これだけは言いたくなかった言葉だ。
親子ほども歳の離れた若者に、年齢の確認をさせている。
「しょうがないか。
でも遅れないで来て下さいよ。
まいったなぁ」
一行に黙って出かけていたら、どうなっていたんだろう。
いや、どうにもならないに決まっている。
「さ!仕事っすよ。
ボヤボヤしない!」
「うわっ、上司に向かって大胆発言」
一行は気持ちの切り換えを、さりげなく相手に合わせてくれる。
私にはとうてい真似の出来ないことだ。
午後の仕事は会議だの、打ち合わせだの、アッと言う間に時間が過ぎた。
一行は外回りらしく、”そのまま行きます“と、飛び出して行った。
「涼くんに、ご両親へのブレゼント選び、一緒にって頼まれちゃった。
それが済んだら合流するね。」
一行には、事前に言うべきことだと思った。
おどけた返事が返って来るものとばかり思っていた。
「いつの約束ですか?
あのバーに行った時ですか?」
「そう。
メールもらって、ちょっと電話で話したかな。
なによぉ。ヤキモチ?」
「はい、ヤキモチっす。」
は? なんだ?
「一行、お昼はご馳走するわよ。
そんなヨイショしたって後はコーヒーくらいしか出ないわよ。」
顔がピクついて、うまく喋れない。
笑わない一行は、なかなか上を向かないし。
「やっぱり涼か。」
「なにがよ。
ただの買い物のお供じゃない。
特別な意味なんか何もないよ。」
まるで恋人に言い訳しているようである。
「違うんだなぁ。
涼がそんなこと頼むの、先輩だからっすよ。
まいったなぁ・・・」
よく解らない。
一行の言っている意味が。
「特別なことなの?」
「前に話したじゃないですか。
アイツは自分からは行かない奴なんすよ。」
ふぅ~ん。
でも、私が特別だとはとても思えない。
「一行、私が親に近い歳だから言いやすかったんでしょう。
一行のお母さんだって、私とそう変わらないんじゃない?」
これだけは言いたくなかった言葉だ。
親子ほども歳の離れた若者に、年齢の確認をさせている。
「しょうがないか。
でも遅れないで来て下さいよ。
まいったなぁ」
一行に黙って出かけていたら、どうなっていたんだろう。
いや、どうにもならないに決まっている。
「さ!仕事っすよ。
ボヤボヤしない!」
「うわっ、上司に向かって大胆発言」
一行は気持ちの切り換えを、さりげなく相手に合わせてくれる。
私にはとうてい真似の出来ないことだ。
午後の仕事は会議だの、打ち合わせだの、アッと言う間に時間が過ぎた。
一行は外回りらしく、”そのまま行きます“と、飛び出して行った。