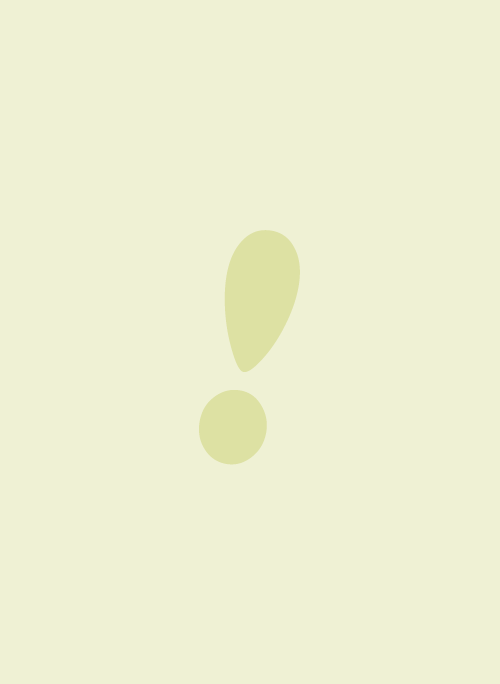たった二日の休暇が、こんなに意味あるものになろうとは、アメリカを発つ時には思ってもみない事だった。
人が生まれて、天に召されるまで、どれだけの出会いが出来るのか。
たった一年あまりの間に、私が求めていることが本当に大切な事なのかを試されてでもいるような、簡単ではない選択ばかりを迫られた月日が、あっという間に通り過ぎている。
熱いコーヒーをもう一杯オーダーし、一行とふたりで過ごすはずだった夜の予定を、その代りと云っては叱られそうだけれど、昼間キャンセルしてしまった後輩達へもう一度メールを入れてみることにした。
「何でもご馳走します。
ランチの罪滅ぼしに、夜の街へのお誘いです。」
「待ってました。
美味しいお酒と、おつまみは、アメリカでのお話をたんまりお願いします。
覚悟しておいてください。」
ふふっと、微笑んでしまう返事に、私はやっぱり彼女達の前では、ずっとキャリアウーマンなんだと、今更ながらに我が身を見る。
ここで、こんな時、あんな風に、涼と思いもよらぬ再会をし、そしてそれは私にとって、会うべくして会わせられた人生の必須事項だったに違いないのだと考える時、”運命“と云うものは創るものではなく、「頂くもの」そんな事を思うのだ。
知らん顔をして、真実を厚化粧で隠しても、スッピンまでさらけ出せるのは、一行しかいないのだと、ひとり、また思う。
こんな穏やかな気持ちは久しぶりだと、夕暮れの近い透き通った雲を見ながら、待ち合わせの時間までは少し早いから、気に入った店のある会社近くの裏通りを歩いてみる事にした。
「麗子さん」
美しい声は聞き覚えのある、やはり運命の人だった。
「あっ、園さん」
「おひとりですか?」
「はい。
彼は涼くんから連絡があったらしくて、会う事になったからって。
私は会社の後輩達と、これから待ち合わせてます。
昨日は、突然おじゃまして驚いたでしょう。
ごめんなさい。
人が生まれて、天に召されるまで、どれだけの出会いが出来るのか。
たった一年あまりの間に、私が求めていることが本当に大切な事なのかを試されてでもいるような、簡単ではない選択ばかりを迫られた月日が、あっという間に通り過ぎている。
熱いコーヒーをもう一杯オーダーし、一行とふたりで過ごすはずだった夜の予定を、その代りと云っては叱られそうだけれど、昼間キャンセルしてしまった後輩達へもう一度メールを入れてみることにした。
「何でもご馳走します。
ランチの罪滅ぼしに、夜の街へのお誘いです。」
「待ってました。
美味しいお酒と、おつまみは、アメリカでのお話をたんまりお願いします。
覚悟しておいてください。」
ふふっと、微笑んでしまう返事に、私はやっぱり彼女達の前では、ずっとキャリアウーマンなんだと、今更ながらに我が身を見る。
ここで、こんな時、あんな風に、涼と思いもよらぬ再会をし、そしてそれは私にとって、会うべくして会わせられた人生の必須事項だったに違いないのだと考える時、”運命“と云うものは創るものではなく、「頂くもの」そんな事を思うのだ。
知らん顔をして、真実を厚化粧で隠しても、スッピンまでさらけ出せるのは、一行しかいないのだと、ひとり、また思う。
こんな穏やかな気持ちは久しぶりだと、夕暮れの近い透き通った雲を見ながら、待ち合わせの時間までは少し早いから、気に入った店のある会社近くの裏通りを歩いてみる事にした。
「麗子さん」
美しい声は聞き覚えのある、やはり運命の人だった。
「あっ、園さん」
「おひとりですか?」
「はい。
彼は涼くんから連絡があったらしくて、会う事になったからって。
私は会社の後輩達と、これから待ち合わせてます。
昨日は、突然おじゃまして驚いたでしょう。
ごめんなさい。