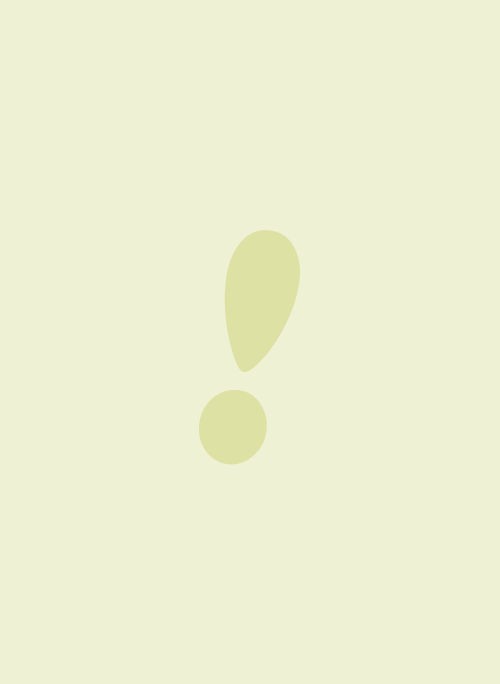私達は、二度目の園の歌を聞き終わる前に、ドア近くの席に移り、目立たないようにそのままそっと外へ出た。
彼女にとっては私の存在が、覚悟や現実を受け止めなければならない対象そのもので、ある意味私は、残酷な時を運んでしまったのかもしれないと、店の外で彼女の心を思い量っている。
優しいから、違う形の優しさでも解ってくれるだろうと、園という女性はそんな人だと信じてみたい。
私だけの勝手な願いが、受け入れられると信じたい。
「一行、園さんがもう一度付き合いたいって言った時、どうして断ったの?」
いつか聞こうと思っていた事が、自然に口から出てしまった。
「何言ってるんだよ。
麗ちゃんと、もう一緒にいたじゃない。
でもね、麗ちゃんと一緒にいなくても、付き合う事はなかったと思うよ。
彼女はいつも俺の年上だったんだ。
たったひとつだけど、俺はどんな時でも年下だった気がする。
麗ちゃんはもっと年上だけど、年下みたいな麗ちゃんも俺はちゃんと知ってるよ。
園は、ん~彼女は麗ちゃんと似ているような気がした時もあったけど、やっぱりちっとも似ていないんだ。」
知り合った頃、涼に言われた言葉を思い出していた。
”似ているんですよ。
一行の元カノに。“
園が歌い終わって、誰もいなくなったカウンターは、空になったグラスだけがそのままに置かれ、二人が確かにそこにいた事を証明しているようだった。
園はもう一度同じ席に座り、さっきまでここで流れていた、表現のし難い空間を思い出していた。
ずっと吸わないでいた煙草に、手をのばしながら。
はじめは何でも通用するはずのない事ばかりでも、それは分かっていても、強がりは諦めない事への反対側の私なりの表現なのだと、二人は気づいてくれただろうか。
姿のない椅子に漂う、自分には無い繋がりは、もう彼とはここまでなんだと、はっきり区切りを見た気がした。
一行はもうあの人のもの。
「楽園」は、一行へのラブソングだった。
「園ちゃん、電話」
彼女にとっては私の存在が、覚悟や現実を受け止めなければならない対象そのもので、ある意味私は、残酷な時を運んでしまったのかもしれないと、店の外で彼女の心を思い量っている。
優しいから、違う形の優しさでも解ってくれるだろうと、園という女性はそんな人だと信じてみたい。
私だけの勝手な願いが、受け入れられると信じたい。
「一行、園さんがもう一度付き合いたいって言った時、どうして断ったの?」
いつか聞こうと思っていた事が、自然に口から出てしまった。
「何言ってるんだよ。
麗ちゃんと、もう一緒にいたじゃない。
でもね、麗ちゃんと一緒にいなくても、付き合う事はなかったと思うよ。
彼女はいつも俺の年上だったんだ。
たったひとつだけど、俺はどんな時でも年下だった気がする。
麗ちゃんはもっと年上だけど、年下みたいな麗ちゃんも俺はちゃんと知ってるよ。
園は、ん~彼女は麗ちゃんと似ているような気がした時もあったけど、やっぱりちっとも似ていないんだ。」
知り合った頃、涼に言われた言葉を思い出していた。
”似ているんですよ。
一行の元カノに。“
園が歌い終わって、誰もいなくなったカウンターは、空になったグラスだけがそのままに置かれ、二人が確かにそこにいた事を証明しているようだった。
園はもう一度同じ席に座り、さっきまでここで流れていた、表現のし難い空間を思い出していた。
ずっと吸わないでいた煙草に、手をのばしながら。
はじめは何でも通用するはずのない事ばかりでも、それは分かっていても、強がりは諦めない事への反対側の私なりの表現なのだと、二人は気づいてくれただろうか。
姿のない椅子に漂う、自分には無い繋がりは、もう彼とはここまでなんだと、はっきり区切りを見た気がした。
一行はもうあの人のもの。
「楽園」は、一行へのラブソングだった。
「園ちゃん、電話」