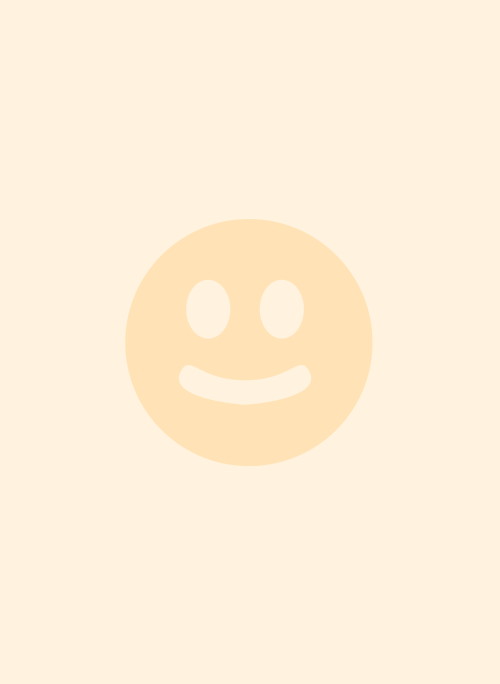「え…? 傷が…ない?」
香織の身体には刃物の傷などなく、それなりの覚悟をしていた僕は呆気に取られた。
洋服から染みた血で汚れてはいたが、出血を伴う外傷はなく、思わず安堵の息を吐く。
「…刺されて…いない?
じゃあこの血は安田さんの…?」
ガックリと脱力して膝をついた。
同時に理性が戻って、乱暴に香織の服を肌蹴たことが恥ずかしくなり、慌てて戻そうとする。
だが、その手を下げることはできなかった。
香織の身体には確かに出血を伴う傷はない。
だが僕は見つけてしまった。
さっきベッドで見た真っ白な肌にはなかったはずのものを。
闇の見せた錯覚だと思いたくて、恐る恐る携帯のライトで照らし診る。
そこには血の汚れで直ぐには気付けなかった忌まわしい傷が、ハッキリと浮かび上がった。
患部を照らすライトが怒りに震えた。