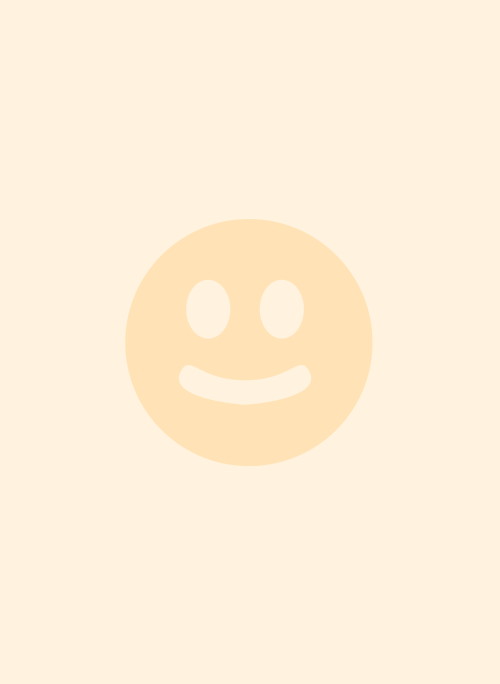夜風が運んでくる血の匂いに弾かれたように茂みを飛び出す。
まだ小村が近くにいるかもしれないとか、他にも仲間がいるかもしれないとか、そんな考えは一瞬で吹き飛んでいた。
どうか無事でいて…。
どうか生きていて…。
浮かんでくるのはそんな言葉だけだった。
二人に駆け寄り香織に覆いかぶさるようにして倒れている安田さんの脈を診る。
顔色がまるで紙のように白いのは、決して月光のせいではない。
肌蹴たシャツの間から見える包帯は赤い布と錯覚しそうなほど染まり、弱々しい脈でかろうじて命を繋いでいた。
これほどの重症でありながらも香織を護ろうとする安田さんの力は強く、引き離すことは容易ではなかった。
娘を護ろうとする父親の執念に絶句する。
だがこの状態では香織の容態を確認することができず、気持ちは焦った。
香織のブラウスはベッタリと血に染まっている。
傍(かたわ)らに落ちているナイフが生々しく血を滑(ぬめ)らせて、月の光を受け不気味に輝いている。
その血が誰のものかを考えるのが怖かった。
横たわる二人の周囲に染みた血の跡にゾクリと背中が寒くなる。
とても安田さん一人の出血量とは思えず、やはり香織もかなりの重傷を負っているのだと確信した。