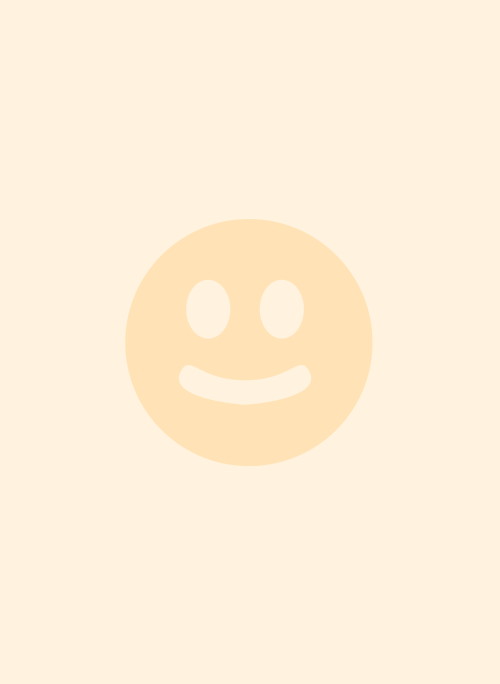闇の中を香織の気配を探りながら走る。
懐中電灯を持たずに飛び出した事を後悔したが、別荘裏の森は護身術の練習場でもあり知り尽くしている。
武さんが海外に行くまでは、毎年夏はここで合宿をしていた。
森の端々まで走らされたり木に登ったりと、忍者修行のようなことをさせられた僕に知らない場所は無いし、今夜は思いのほか月が明るいから問題は無いと思っていた。
だが実際に走り出すと、夜の森はどこまでも僕に容赦がなかった。
木々の間から漏れる僅かな月明かりだけが頼りの森は、手を伸ばした先さえも満足に見えない。
神経を張り詰め、気配を探りながら走る僕の足を、木の根が絡めとり妨害する。
嘲笑うように闇から伸びる枝が、シャツを肩口から派手に引き裂き、こめかみを叩いた。
生暖かいものが流れ出し、目尻を伝って左眼の視界が奪う。
「あぁクソッ! なんでこんな時に…」
舌打ちをして血を拭ったその時、香織の声が闇を切り裂いた。