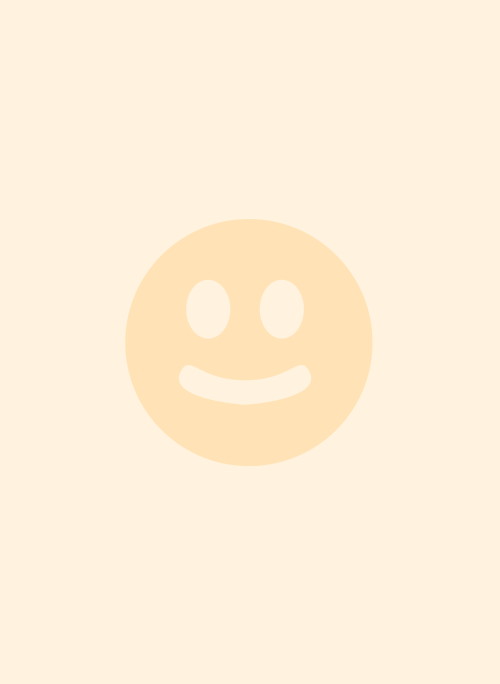ニヤリと笑ったその口が悪魔のように裂け、血走った両眼には狂気がうごめいている。
あたしを気遣っていた気が弱そうな優しい青年とは、まるで別人だった。
獲物を捕らえた肉食獣のように血走った目でお父さんを見据え、細い銀の刃を向ける。
空に浮かぶ月の様なそれは鋭い光を放ち、月明かりだけが頼りの薄暗い中でも、不気味なほどに冷たく輝いていた。
小村がジリジリと間合いを詰める。
おとうさんが身構えながら少しずつ後退していくのを、どうしてよいか分からず呆然と見つめていた。
その時
僅かに角度が変わって、お父さんのシャツが血に染まっているのが見えた。
既に小村に刺されたのか、それとも傷口が開いたのか。
どちらにしても相当の出血で、包帯も腹部を押さえる左手も鮮血で染まっている。
指の間から尚も流れ出ようとするおびただしい血の量に、あたしは悲鳴を呑み込んだ。