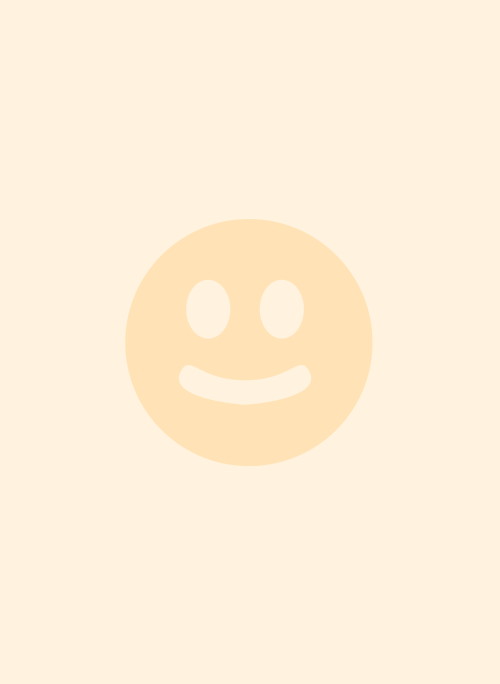一方、事故を起こした俊弥は、怪我をした足を引きずりながら必死に別荘へ向かって歩いていた。
必死に歩けども、痛みを堪えての歩みは、まるで子供を連れた女性のように遅い。
痛みは歩くたびに増し、冬の冷たい風に曝され、感覚すらなくなっていく。
それでも孤独に陣痛に耐え自分を待っている彼女を思うと、歩みを止めることはできなかった。
ようやく別荘にたどり着いた頃には、朝からちらついていた雪は本降りになり、いつもより早い冬の夕刻が足早に闇を連れてきつつあった。
雪の中に不気味なほどの静寂に包まれる別荘。
その前に立った俊弥は、別荘のドアというドアが全て外から施錠されている事に唖然とした。
周囲に警備の人影も無く、辺りはシンとしている。
彼女は無事なのだろうか。
不安は焦りに変わり、彼女の気配を捜す。
別荘内は静まり返っており、一刻を争うことを直感した。
ドアに体当たりして鍵を壊し、中に飛び込む。
彼女の姿を捜し、リビングのドアを開けたとき、俊弥は信じられないものを見た―…