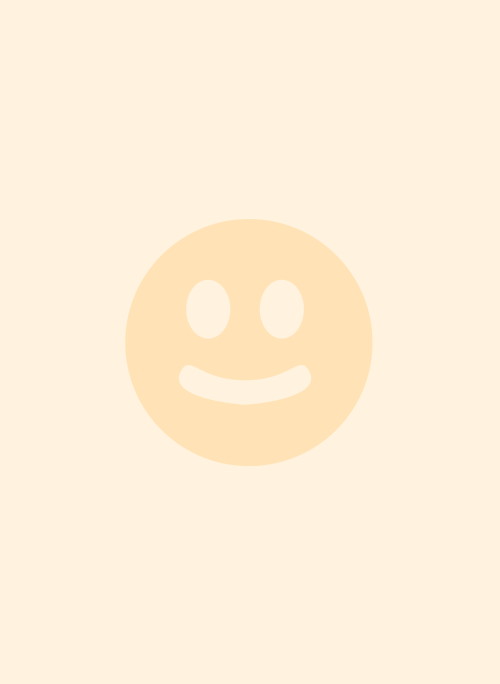おかしな言動に、いつもと違う雰囲気。
医師の言うとおりに入院させなかったことがまずかったのかと、一瞬後悔が胸を過ぎる。
とにかく少しでも休ませなければと思ったとき…
突然首に細い腕が絡んだ。
「かお…り?」
「…あたし、廉君の傍にいてもいいの?」
まるで小動物のように震えているのは、決して寒さからなどではない。
何かに脅え、大きな不安に押しつぶされそうな彼女は、いつもより更に小さく感じた。
震えの止まらない背中を宥めるように擦りながら、少しでも不安を取り除けるよう穏やかに耳元で囁く。
「好きだよ香織。ずっと僕の傍にいて欲しいんだ。もう決して離さないから」
「……本当に?」
「うん…。君がいないと僕はダメになる」
「あたしの事ずっと好きでいてくれる?」
「香織こそ、君を辛い目にばかり遭わせているこんな僕を、まだ好きでいてくれるの?」
「大好きなの。廉君でなくちゃダメなの…。お願い、あたしを捨てないで」
「捨てる? どうしてそんな事言うんだ? 僕が香織を捨てるなんて絶対にありえないよ」
「あたしが…どんな人間でも?」
「僕がどんな人間でも、香織は真っ直ぐに僕の本質を好きだと言ってくれたよね?
僕だって同じ気持ちだよ。
君がたとえ悪魔だって構わない。
地獄に堕ちると言われても、君を捨てるなんて出来ないよ」
「…だったら…証明して?」