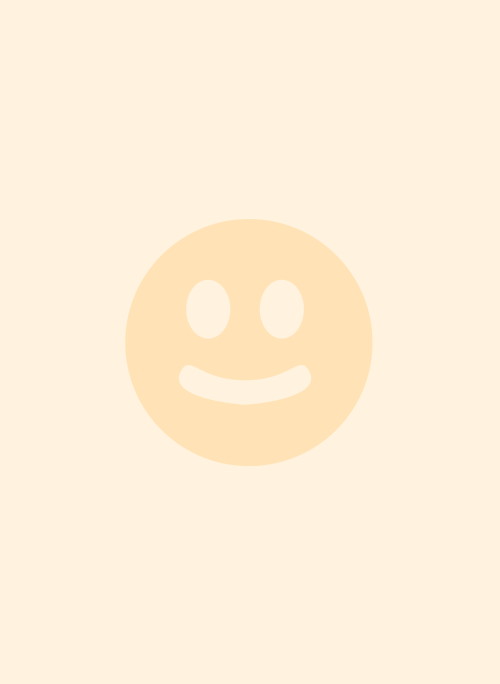「……あたし…思い出したの。あたしは…生まれてきちゃいけなかった…」
「…え?」
「あたしは…捨てられたから…だから誰にも迷惑をかけちゃいけないの」
「…何を言ってるんだ?」
「あたしは…父のようには…生きたくない…だから…消えるの」
この時になってようやく気がついた。
香織は現実を見ていない。
ショックから混乱しているのだ。
だが夏休み前に彼女の父親に会った印象からは、香織の言っている意味が理解できなかった。
「…君が消えたら、僕も後を追うよ。
君を護りきれなかったばかりか、こんな風に追い詰めて、もしもの事があったら…僕は生きていられない」
「…廉君のせいじゃない。
あたしが…みんなを不幸にしているの」
「君は誰も不幸になんてしていないよ。
色んなことがあって混乱しているだけだ。
とにかくその冷えた身体を温めてから落ち着いて話そう。いいね?」
まだ何か言いたそうな香織を、強引に抱き上げ水から引き上げると、急いで部屋へと戻り、そのままシャワーブースに飛び込んだ。
ネグリジェのままの香織の上から熱いシャワーを流して、プールの水と夏の夜風に曝され冷え切った身体を温める。