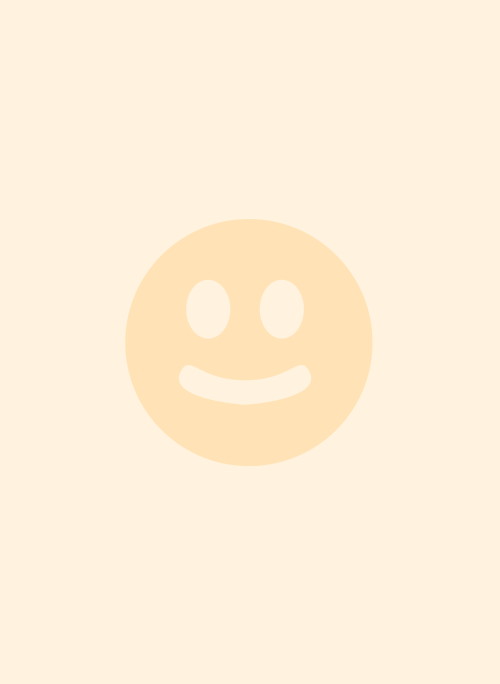驚いた父さんが声をかけると、ハッとして我に返った母さんは、自分でも何故泣いたのか解からなかったようだ。
香織のことがよほどショックだったのだろうと父さんは解釈したようで、直ぐに二人を車に乗せ、救急車と共に病院へと向かった。
病院へ向かう車の中、腕の中の香織を見つめながら、彼の言葉を繰り返し思い出していた。
『恋人だというなら、もっとシッカリ彼女を護ってやれ』
『一時(いっとき)でも目を離す訳にいかねぇんだよ。わかるだろ?』
彼ならば、恋人を護りきる事がきっと出来る…そんな気がした。
だったら僕は…?
香織が握り締めたままのハンカチを手に取りじっと見つめる。
そこには 【Tatsuya.S 】と名前が刺繍されていた。
走り去る彼を見つめ母さんが流した涙。
そして、手の中にある『タツヤ』という名前。
バラバラのピースが少しずつ集まり始めていることを
この時の僕には気付く余裕すらなかった。
香織のことがよほどショックだったのだろうと父さんは解釈したようで、直ぐに二人を車に乗せ、救急車と共に病院へと向かった。
病院へ向かう車の中、腕の中の香織を見つめながら、彼の言葉を繰り返し思い出していた。
『恋人だというなら、もっとシッカリ彼女を護ってやれ』
『一時(いっとき)でも目を離す訳にいかねぇんだよ。わかるだろ?』
彼ならば、恋人を護りきる事がきっと出来る…そんな気がした。
だったら僕は…?
香織が握り締めたままのハンカチを手に取りじっと見つめる。
そこには 【Tatsuya.S 】と名前が刺繍されていた。
走り去る彼を見つめ母さんが流した涙。
そして、手の中にある『タツヤ』という名前。
バラバラのピースが少しずつ集まり始めていることを
この時の僕には気付く余裕すらなかった。