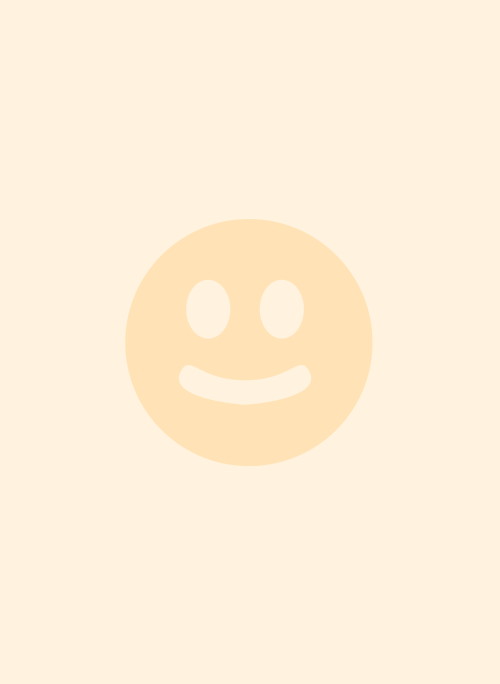「香織を…助けた?」
「お前は本当に彼女の恋人なのか?」
「そうだ」
彼は僕を値踏みするようにジロジロと見た。
僅かに紫がかった黒髪に整った顔立ちは、見るものを惹きつける美しさだが、その瞳は冷たく人を威圧するものがある。
香織を助けた事実が確かなら悪い人間では無いのかもしれない。だが、彼女が彼の手に在るうちは味方とは決して言えない。
彼の気迫に呑まれまいと睨み返した。
「僕の事を訊く前に自分の説明をしたらどうだ?
君が彼らの仲間じゃないとどうして言い切れる?
おかしいじゃないか。通常この道はこの先の別荘地に用のあるもの以外は使わない。ただ単に通りかかって香織を助けたとでも?
ありえない話だ」
「偶然通りかかった訳じゃない。
だが、誤解するな。あんな奴らの仲間だと勘違いされては困る」
「仲間じゃないと証明できるのか?
仲間が全員やられたから香織を連れて独りで逃げようとしたんじゃないか?」
僕の言葉に明らかに不機嫌に眉を寄せた男は、吐き捨てる様に言った。
「お前は本当に彼女の恋人なのか?」
「そうだ」
彼は僕を値踏みするようにジロジロと見た。
僅かに紫がかった黒髪に整った顔立ちは、見るものを惹きつける美しさだが、その瞳は冷たく人を威圧するものがある。
香織を助けた事実が確かなら悪い人間では無いのかもしれない。だが、彼女が彼の手に在るうちは味方とは決して言えない。
彼の気迫に呑まれまいと睨み返した。
「僕の事を訊く前に自分の説明をしたらどうだ?
君が彼らの仲間じゃないとどうして言い切れる?
おかしいじゃないか。通常この道はこの先の別荘地に用のあるもの以外は使わない。ただ単に通りかかって香織を助けたとでも?
ありえない話だ」
「偶然通りかかった訳じゃない。
だが、誤解するな。あんな奴らの仲間だと勘違いされては困る」
「仲間じゃないと証明できるのか?
仲間が全員やられたから香織を連れて独りで逃げようとしたんじゃないか?」
僕の言葉に明らかに不機嫌に眉を寄せた男は、吐き捨てる様に言った。