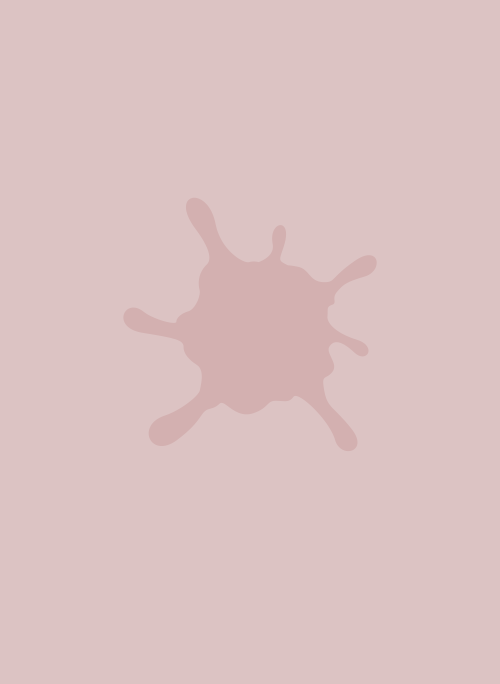いや、メルヘンさんらしいといえばらしいかと、この底知れぬポテンシャルにいつも驚かされていたし、脅威を感じていた。そういうところを含めて、わしは期待し、つらくあたってしまうのかもしれないなと、ここ最近の自分の大人気のない振る舞いを恥つつ、ご隠居は目を細めた。
「あのね
ごいんきょ
その子
ごいんきょが、飼ってくださいよー」
と、呑気なことをいつものように言う。
「嫌ですよ」
「えー、なんでー
めちゃくちゃかわいいでしょ?」
ぐりぐりとした黒く丸い両目に見つめられたご隠居は、ぐらっとは来たがなんとか持ち堪えた。
「嫌です。嫌なモノは嫌なんです」
「なんでー? こんなにかしこくてかわいいのに」
「わしのほうが早く死ぬからいやなんです」
「そんなこと、ごえっぷ」
メルヘンさんのクチから小さな黒い煙が少し漏れた。
ごくんと飲み込む。その様子にご隠居は肝を冷やした。
犬もひやひやとする。
「へ? なんだろこれへへへー」と、
笑った顔が急に真剣みを帯びて着物をただしてから言った。
「そこをなんとか
ご隠居!」
畳に、おでこを擦り付けるように土下座をした。
「あっしの家には、その子を手当をしてあげるような道具もなければ、クスリのかわりになるもんもねぇ、満足にエサも与えてやれねぇ
それじゃぁ、その子があまりにも不憫だ。
頼む。この通りだ」
メルヘン侍はご隠居を見た。ご隠居は困った顔をするばかり。
「だからどうか、おねがいします
このとおりだ
おねがいします」
さらに額をこすりつけるようにして言うとご隠居は抱いていた犬を畳に下ろした。
「メルヘンさん。いいから頭をあげなさい」
「いやです、飼ってくれるといってくれるまでは動きません」
「あのね、包帯とクスリとってきますから、ちょっと手伝いなさいよ」
「そうこなくっちゃ」
メルヘンの顔は、ぱっと明るくなった。
「あのね
ごいんきょ
その子
ごいんきょが、飼ってくださいよー」
と、呑気なことをいつものように言う。
「嫌ですよ」
「えー、なんでー
めちゃくちゃかわいいでしょ?」
ぐりぐりとした黒く丸い両目に見つめられたご隠居は、ぐらっとは来たがなんとか持ち堪えた。
「嫌です。嫌なモノは嫌なんです」
「なんでー? こんなにかしこくてかわいいのに」
「わしのほうが早く死ぬからいやなんです」
「そんなこと、ごえっぷ」
メルヘンさんのクチから小さな黒い煙が少し漏れた。
ごくんと飲み込む。その様子にご隠居は肝を冷やした。
犬もひやひやとする。
「へ? なんだろこれへへへー」と、
笑った顔が急に真剣みを帯びて着物をただしてから言った。
「そこをなんとか
ご隠居!」
畳に、おでこを擦り付けるように土下座をした。
「あっしの家には、その子を手当をしてあげるような道具もなければ、クスリのかわりになるもんもねぇ、満足にエサも与えてやれねぇ
それじゃぁ、その子があまりにも不憫だ。
頼む。この通りだ」
メルヘン侍はご隠居を見た。ご隠居は困った顔をするばかり。
「だからどうか、おねがいします
このとおりだ
おねがいします」
さらに額をこすりつけるようにして言うとご隠居は抱いていた犬を畳に下ろした。
「メルヘンさん。いいから頭をあげなさい」
「いやです、飼ってくれるといってくれるまでは動きません」
「あのね、包帯とクスリとってきますから、ちょっと手伝いなさいよ」
「そうこなくっちゃ」
メルヘンの顔は、ぱっと明るくなった。