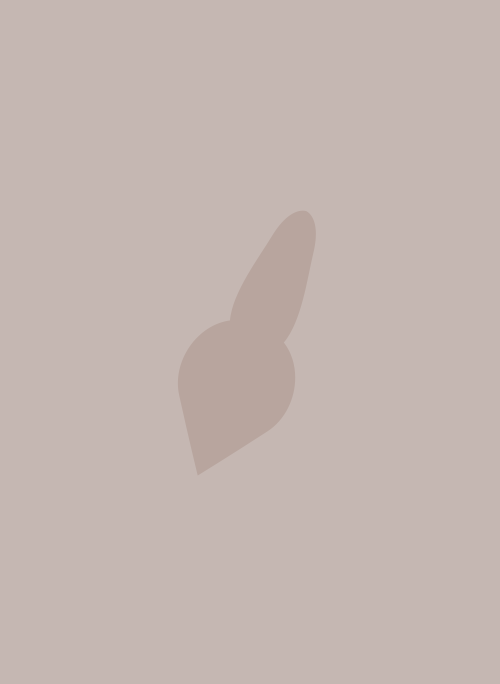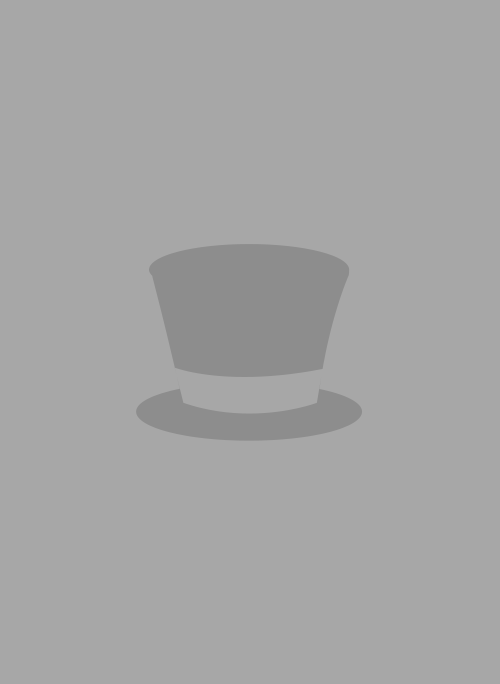見渡す限りではボスの存在を確認する事が出来なかった。やはりアーシュトレイの言った通り誘拐なんて狂言だったのかもしれない。
「よく来た、エルゼ」
言いながら仲間を押し退けて歩いてくる男は、俺のよく知っている男だった。よく知っていると言ったら誤解が生じるかもしれない。正しくは、二、三度仕事をした仲の男だ。名前などは忘れてしまったが、大きな身体つきと目下にある泣き黒子を覚えている。
それに加えて、よく考えると彼の声はさっきの電話の声と同じだ。彼がボスのやり方を気に食わないと思う輩か?
「ボスは?」
「居るわけないだろ、ボスなんて」
やはり、そうだったか。
「俺は奴の顔も知らないんだぜ」
「それは誘拐の仕様がないな」
呑気にそんな事を口にすると、後ろで扉が閉まる音がした。誰かが閉めたのだろう。薄暗い中で人が動く音が嫌に耳につく。一体何人ぐらいいるのだろうか。これは全部ボスに反発する奴か?
案外少ないが、もしかするとこの集団は一部なのかもしれないな。
「俺たちの役目はお前をぶちのめす事さ」
「俺だけを?」
目的はボスじゃないのか?
「あぁ。お前は邪魔だ」
俺は一体どうして、彼らの邪魔になっているのだろう。
彼は知った顔だが、殺しの動機はあまりよく分からない。そうこう考えているうちに、集団の一人が俺に向かって棒を振り下ろしてきた。至近距離でやられたから分かるものを、背後からなら決して避けられなかっただろう。
「誰かに言われたのか? 俺をやれって」
俺は襲い掛かってきた男に銃弾を一つくれてやった。何処に当たったかは分からない。男が呻いていたから、一発では逝けなかったのだろう。だが、申し訳ないと思っている暇もない。俺は今、まさに殺されかけているのだから。
あぁ、これこそ殺しを肯定する一言なのかもしれないな。仕方ないと心の奥底で、俺が言っているのだ。銃弾を放った時点で俺はもう人殺しを躊躇していない。
「関係ねぇさ。お前が死ねば全て解決するんだから」
一人、また一人と俺に向かって武器を振り回してきやがった。俺は話を中断して攻防に
専念する。どうせこれ以上話しをしても何も教えてくれないだろう。それに俺は話をする為に来たのではないし。
角材の様な棒、鋭いナイフ、唸る拳銃、鉄のような拳。
様々な武器が俺だけに襲い掛かってきた。幸いなのが一度に数人しか来ない事だ。誰かの流儀か、仲間を殺さない為の策かは知らないが、それで随分と助かっている。
発砲するだけに飽きた俺の漆黒はたまに鈍器と化して誰かの頭に直撃した。それが何分続いたか知れない。人数が減っていると確実に分かったのは、扉が開いて外の薄暗さが倉庫内に入り込んできた時だった。
誰が開けたのか、すぐには分からなかった。