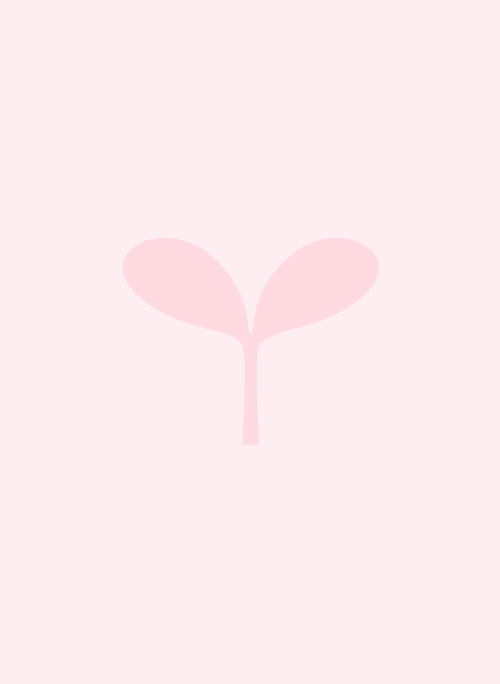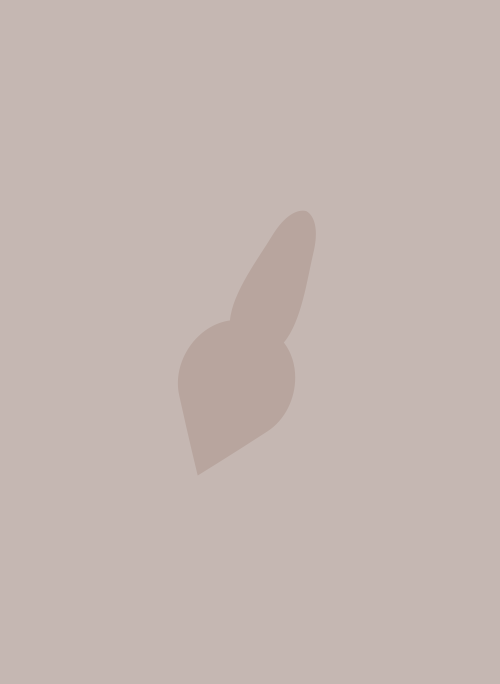ふと、かばんの中に先刻購買で買った水まんじゅうが入っていることを思い出した。一寸考え、僕は貯水槽の正面に座りその前に水まんじゅうを置いた。あの子は水まんじゅうを食べたことがあっただろうか。目を閉じて、あの子が消えていった大きな水槽に向かって小さく手を合わせながら僕はそんなことを考えていた。夏休みも近づいた七月の校舎は、吹奏楽の音色で歌いながらも少しずつ静けさを取り戻し始める。
メニュー
ふと、かばんの中に先刻購買で買った水まんじゅうが入っていることを思い出した。一寸考え、僕は貯水槽の正面に座りその前に水まんじゅうを置いた。あの子は水まんじゅうを食べたことがあっただろうか。目を閉じて、あの子が消えていった大きな水槽に向かって小さく手を合わせながら僕はそんなことを考えていた。夏休みも近づいた七月の校舎は、吹奏楽の音色で歌いながらも少しずつ静けさを取り戻し始める。