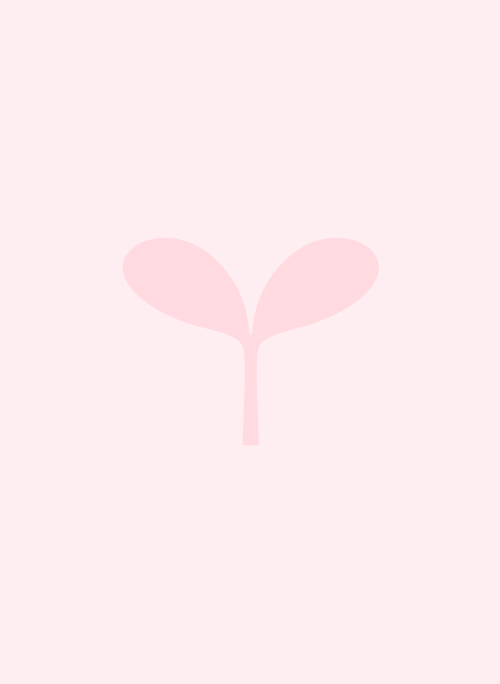「そのあと、カコってば真っ赤になってたんだ。
いつも冷静なクセにさ」
私の隣でハルが笑った。
毎週日曜になると、一週間の話題をため込んだ様に、ハルはしゃべり続ける。
そして、友人や学校のことをはなす。
だが決して、自分の話をしたがらない。
私は気にはしたけれど、彼が楽しそうなら特に尋ねたりはしなかった。
それに、私はハルとのこの時間がとても好きだった。
時間を忘れるほどに。
「あとは、2人を置いて帰ったからわかんないけど、どうにかなったんじゃないかな~?
良い方向にさ」
ハルは喜んでいたようだった。
寂しくならないか?と訊ねると、案の定、寂しそうな顔で、「少し」と言った。
「ワカはさ、『恋人』とかいないの?」
唐突だった。
しばらく何も答えないでいると、ハルは申し訳なさそうな顔をした。
「ごめん。……その、悪気はなかったんだ」
「……いや、構わないよ」
ハルは、私を見上げた。
いつも冷静なクセにさ」
私の隣でハルが笑った。
毎週日曜になると、一週間の話題をため込んだ様に、ハルはしゃべり続ける。
そして、友人や学校のことをはなす。
だが決して、自分の話をしたがらない。
私は気にはしたけれど、彼が楽しそうなら特に尋ねたりはしなかった。
それに、私はハルとのこの時間がとても好きだった。
時間を忘れるほどに。
「あとは、2人を置いて帰ったからわかんないけど、どうにかなったんじゃないかな~?
良い方向にさ」
ハルは喜んでいたようだった。
寂しくならないか?と訊ねると、案の定、寂しそうな顔で、「少し」と言った。
「ワカはさ、『恋人』とかいないの?」
唐突だった。
しばらく何も答えないでいると、ハルは申し訳なさそうな顔をした。
「ごめん。……その、悪気はなかったんだ」
「……いや、構わないよ」
ハルは、私を見上げた。