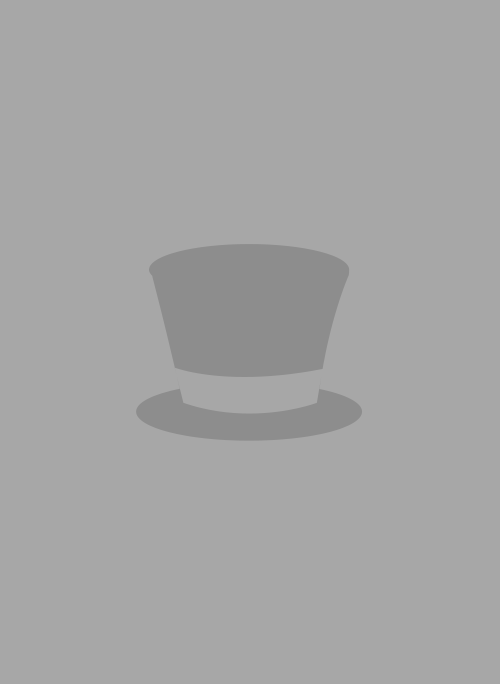案の定、その子は喜んで、あることを私に聞いた。
「ねぇ?なんでさっきから丁寧語ではなしてるの?」
「ああ、守り神ということですので、丁寧に喋った方がいいかと」
「んーもうっ!堅苦しいからよしてよぉー!これから一緒にいるんだから」
「はい… じゃなくて、うん」
一緒に…?
これからこの幽霊みたいなやつと一緒にいなければならないのか。
気が遠くなる気分だった。
「あ。勿論お婆さんの前に姿はあらわさないけ―どっと」
線香のような不思議な香りのする煙とともに、いきなりその子は消えた。
と同時にがらがらがら、と古い引き戸が開いてお婆さんが入ってきた。
「お帰りなさい!お婆さん」
時計はもう6時をさしていた。