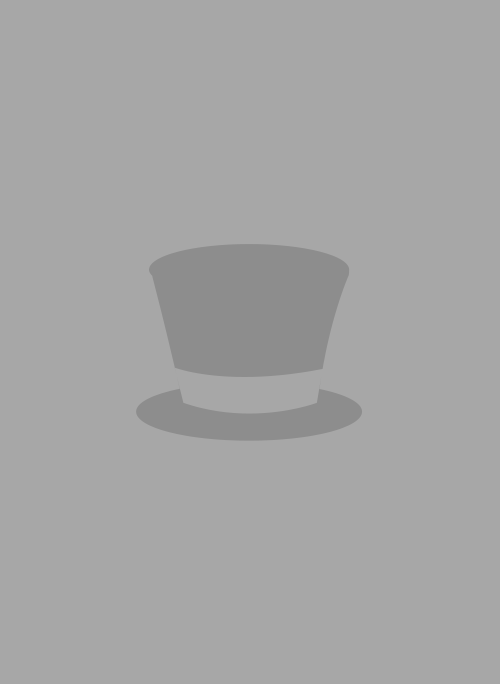相手のその言葉に、セシリアは笑い出していた。そう、この二人はセシリアとミスティリーナ。グローリアの都にいるはずの二人がこんな田舎道にいるのには理由がある。
新月の日。ウェリオの宿に戻った二人を待っていたのは、どことなく焦った表情を浮かべたジャスティンだった。そして、彼の知らせを受けてセシリアはルディアに行くことをその場で決めたのだった。
「でも、本当に大丈夫なの?」
木の根元に腰をおろしたミスティリーナは、セシリアにそうたずねている。
「大丈夫よ。それに、やっと手掛かりがつかめるかもなのよ」
「リアがそう言うなら、あたしに反対する権利はないよね」
ポツリとそう言ったミスティリーナからは、ため息しか漏れてきていない。彼女がそう言ってくれるのは、自分のことを心配してくれているからだ、ということをセシリアは理解している。その理由というものも歴然としている。なぜなら、女だけで旅をするのは無謀ともいえることだからである。
新月の日。ウェリオの宿に戻った二人を待っていたのは、どことなく焦った表情を浮かべたジャスティンだった。そして、彼の知らせを受けてセシリアはルディアに行くことをその場で決めたのだった。
「でも、本当に大丈夫なの?」
木の根元に腰をおろしたミスティリーナは、セシリアにそうたずねている。
「大丈夫よ。それに、やっと手掛かりがつかめるかもなのよ」
「リアがそう言うなら、あたしに反対する権利はないよね」
ポツリとそう言ったミスティリーナからは、ため息しか漏れてきていない。彼女がそう言ってくれるのは、自分のことを心配してくれているからだ、ということをセシリアは理解している。その理由というものも歴然としている。なぜなら、女だけで旅をするのは無謀ともいえることだからである。