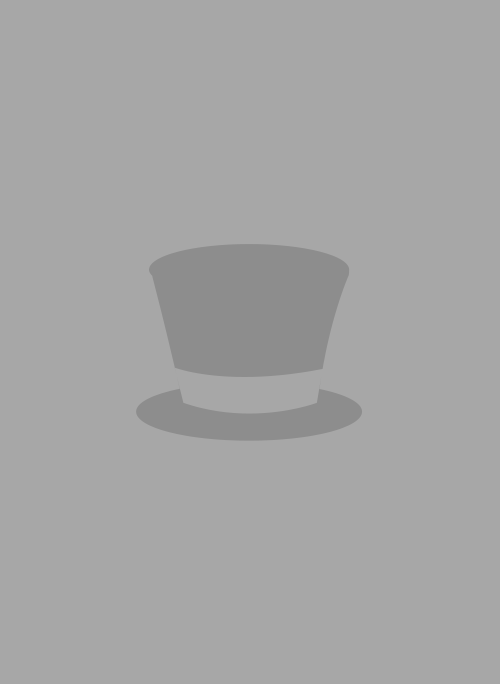「それはそうと、あたしが火の魔法しか使えないのが不安だって言わなかった?」
自分の魔法には自信をもっているのだろう。グラン・マに対して『どうして、そう言うのか』と言いたげな表情を浮かべている。ミスティリーナの声にゆっくりと目をあけたグラン・マ。彼女はミスティリーナの挑発的な態度にも顔色一つ変えようとはしていない。
「何回も言うけれど、聖王女をめぐる影は尋常じゃなく大きいんだよ。水晶玉を真っ黒にしてしまうくらいにね。それは、聖王女が聖王女である以上、仕方がない」
「だから、それとこれとがどうやったら結びつくのよ」
なかなか本題に入らないようなグラン・マの言葉に、ミスティリーナは苛々しはじめている。
「だから、火の魔法が効かない相手がいるかもしれないだろう」
自分の魔法には自信をもっているのだろう。グラン・マに対して『どうして、そう言うのか』と言いたげな表情を浮かべている。ミスティリーナの声にゆっくりと目をあけたグラン・マ。彼女はミスティリーナの挑発的な態度にも顔色一つ変えようとはしていない。
「何回も言うけれど、聖王女をめぐる影は尋常じゃなく大きいんだよ。水晶玉を真っ黒にしてしまうくらいにね。それは、聖王女が聖王女である以上、仕方がない」
「だから、それとこれとがどうやったら結びつくのよ」
なかなか本題に入らないようなグラン・マの言葉に、ミスティリーナは苛々しはじめている。
「だから、火の魔法が効かない相手がいるかもしれないだろう」