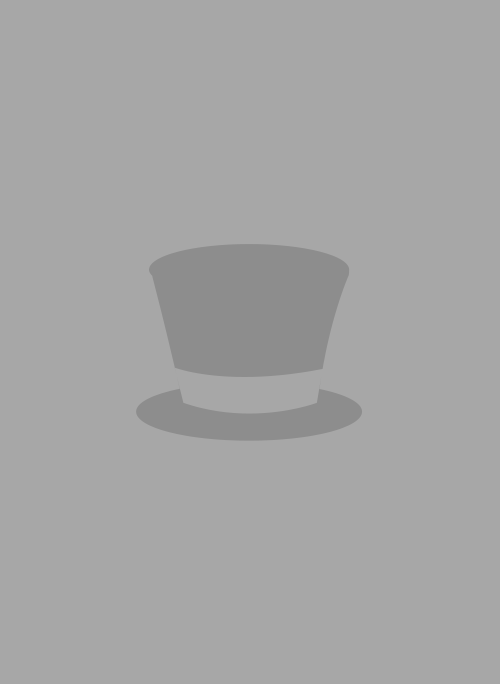「この分だと、何かが起きるんだろうね……リアも帰ってきているんなら、こっちに顔を出せばいいのに……」
そう呟いた彼女は商売道具でもある水晶玉を大切そうにしまうと、ゆっくりと立ち上がっていた。彼女がここに住み始めてからどれくらいの時間がたっているのか。誰もそのことを知ってはいない。いつの間にか彼女はここに住み着き、偶然のことからセシリアという後ろ盾を手に入れたのだ。もっとも、彼女の占いの腕を疑うものなど王都にはいない。セシリアという保護者がいなくても彼女は十分に生きていけるだろう。それにもかかわらず、彼女は何くれとなくセシリアに気を配っているのだった。
そんな彼女の滅多に変えられることのない表情。それが今はどこか不安げな色を浮かべている。彼女は古いタンスの扉をあけると、中に入っているものを大切そうに取り出していた。
そう呟いた彼女は商売道具でもある水晶玉を大切そうにしまうと、ゆっくりと立ち上がっていた。彼女がここに住み始めてからどれくらいの時間がたっているのか。誰もそのことを知ってはいない。いつの間にか彼女はここに住み着き、偶然のことからセシリアという後ろ盾を手に入れたのだ。もっとも、彼女の占いの腕を疑うものなど王都にはいない。セシリアという保護者がいなくても彼女は十分に生きていけるだろう。それにもかかわらず、彼女は何くれとなくセシリアに気を配っているのだった。
そんな彼女の滅多に変えられることのない表情。それが今はどこか不安げな色を浮かべている。彼女は古いタンスの扉をあけると、中に入っているものを大切そうに取り出していた。