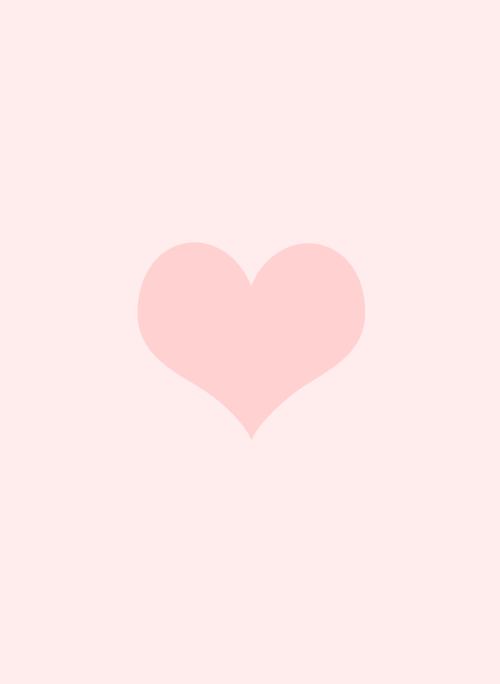「あ、待って!」
思わず声が出た。わたしに呼び止められて振り返ったこどもは首をかしげる。
このままだと夏丸が行ってしまう。
小さい頃からずっとわたしの傍にいてくれた親友だった。お母さんのいない寂しさを埋めてくれた……。正直、離れたくない。
でも……。
(いいよね?お母さん……)
少し迷ったが、わたしは自分の首から母の形見を外すとそれをこどもに差し出す。こどもはそれを受け取って小走りに戻っていくと、それを着物の女に渡した。着物の女はそれを首につけるとわたしに向かって深くお辞儀をした。わたしも深くお辞儀する。
頭をあげると、行列は再び鈴の音を鳴らしながらゆっくり歩き出していった。
列が見えなくなるまでわたしはその後ろ姿を見つめていた。
手のひらのかんざしをギュッと握りしめる。
和傘を開くと色鮮やかな花が頭の上に広がった。
示された道を下ると、ものの数分で見慣れた風景へと戻ってきた。振り返ると歩いてきたはずの道は見当たらない。まるで狐に……いや、猫に抓まれた気分だった。
家に帰るとおばあちゃんがそうめんを茹でて待っていてくれた。おじいちゃんが張り切って半分に割った竹を庭に組み立てている。おお、夏だ!
おばあちゃんが、夏丸がいないと言って首をかしげていたので「うーん、なんか嫁いでったみたい」というと目をパチクリさせてた。でもすぐ「そうかい」と言って笑ってた。
「あーあ、来年まで寂しくなっちゃうなぁ。早く元気な子産めよー」
「あら小夏、この傘どうしたんだい?」
竹を流れてくる冷えたそうめんを捕まえて、ちゅるるんっとすする。風に揺られチリチリンと風鈴が澄んだ音を鳴らした。
【End】
思わず声が出た。わたしに呼び止められて振り返ったこどもは首をかしげる。
このままだと夏丸が行ってしまう。
小さい頃からずっとわたしの傍にいてくれた親友だった。お母さんのいない寂しさを埋めてくれた……。正直、離れたくない。
でも……。
(いいよね?お母さん……)
少し迷ったが、わたしは自分の首から母の形見を外すとそれをこどもに差し出す。こどもはそれを受け取って小走りに戻っていくと、それを着物の女に渡した。着物の女はそれを首につけるとわたしに向かって深くお辞儀をした。わたしも深くお辞儀する。
頭をあげると、行列は再び鈴の音を鳴らしながらゆっくり歩き出していった。
列が見えなくなるまでわたしはその後ろ姿を見つめていた。
手のひらのかんざしをギュッと握りしめる。
和傘を開くと色鮮やかな花が頭の上に広がった。
示された道を下ると、ものの数分で見慣れた風景へと戻ってきた。振り返ると歩いてきたはずの道は見当たらない。まるで狐に……いや、猫に抓まれた気分だった。
家に帰るとおばあちゃんがそうめんを茹でて待っていてくれた。おじいちゃんが張り切って半分に割った竹を庭に組み立てている。おお、夏だ!
おばあちゃんが、夏丸がいないと言って首をかしげていたので「うーん、なんか嫁いでったみたい」というと目をパチクリさせてた。でもすぐ「そうかい」と言って笑ってた。
「あーあ、来年まで寂しくなっちゃうなぁ。早く元気な子産めよー」
「あら小夏、この傘どうしたんだい?」
竹を流れてくる冷えたそうめんを捕まえて、ちゅるるんっとすする。風に揺られチリチリンと風鈴が澄んだ音を鳴らした。
【End】