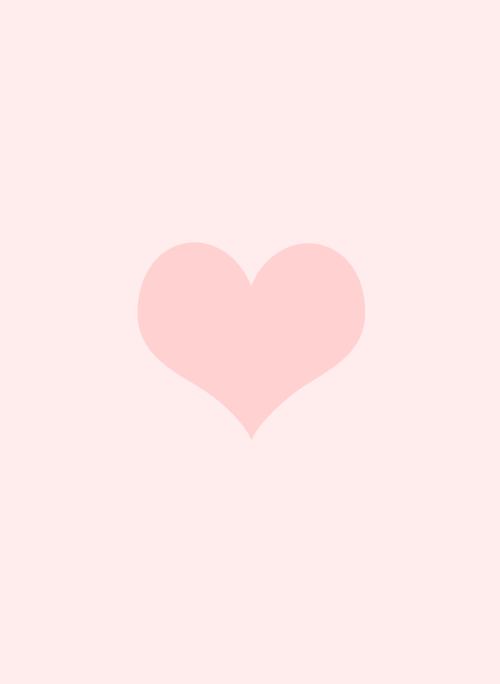写真で見た母は本当にわたしによく似ていた。まだ若いおじいちゃんとおばあちゃんの間に立っているのがまるで自分のように錯覚してなんだか変な気分。こうして客観的に見るとわたしってけっこう美人?なんちゃって。
生まれつき身体の弱かった母はわたしがまだ幼い頃に逝ってしまった。だからわたしには母との記憶がほとんどない。わずかに残る想い出だけだ。でもこうして写真みたり、話を聞いたりするとやっぱり親子なんだなぁとわかる。わたしと母の絆はこれだけでも十分だった。
母がいないことにさみしいと思ったことはあるけれど、不幸だと思ったことは一度もない。
男手一つでわたしをここまで育ててくれたお父さんや、美味しいご飯をたくさん作ってくれるおばあちゃんや、色んな遊びを教えてくれたおじいちゃん。とっておきの飛び込みスポットを教えてくれた白州の友達や、たくさん恋バナで盛り上がった学校の友達。それにそうだ、夏丸を忘れてはいけない。わたしが物心つく前からの一番古い親友だ。わたしの寂しさを埋めてくれた。
大好きな人たちに囲まれて、わたしは十分すぎるほど幸せだ。
そんなことをしみじみと感じながらアルバムを捲ると、ふと一枚の写真に目が留まった。
多分この家の庭で撮ったであろうその写真には、高校生くらいだろうか、白猫を抱き上げて笑う母の姿があった。
「夏丸・・・・・・?」
生まれつき身体の弱かった母はわたしがまだ幼い頃に逝ってしまった。だからわたしには母との記憶がほとんどない。わずかに残る想い出だけだ。でもこうして写真みたり、話を聞いたりするとやっぱり親子なんだなぁとわかる。わたしと母の絆はこれだけでも十分だった。
母がいないことにさみしいと思ったことはあるけれど、不幸だと思ったことは一度もない。
男手一つでわたしをここまで育ててくれたお父さんや、美味しいご飯をたくさん作ってくれるおばあちゃんや、色んな遊びを教えてくれたおじいちゃん。とっておきの飛び込みスポットを教えてくれた白州の友達や、たくさん恋バナで盛り上がった学校の友達。それにそうだ、夏丸を忘れてはいけない。わたしが物心つく前からの一番古い親友だ。わたしの寂しさを埋めてくれた。
大好きな人たちに囲まれて、わたしは十分すぎるほど幸せだ。
そんなことをしみじみと感じながらアルバムを捲ると、ふと一枚の写真に目が留まった。
多分この家の庭で撮ったであろうその写真には、高校生くらいだろうか、白猫を抱き上げて笑う母の姿があった。
「夏丸・・・・・・?」